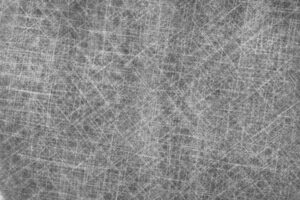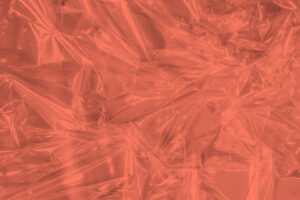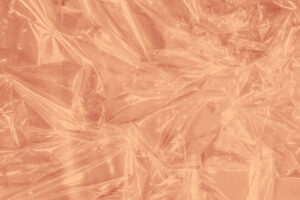スタートアップ企業は成長段階(フェーズ)に応じて戦略や重点が大きく変化します。創業直後のシード期、軌道に乗り始めるアーリー期、そして急成長するグロース期では、それぞれ直面する課題や取り組むべき事業開発のポイントが異なります。本記事では、日本のスタートアップを念頭に、各フェーズの特徴と課題、具体的な事業開発の進め方(バリュープロポジション設計やプロダクト開発、PMF達成の戦略)、資金調達のポイント(エンジェル投資家、VC、CVC、デットファイナンス等)、組織構築の戦略(採用・チームビルディング、文化醸成、インセンティブ設計)、さらにマーケティングと市場開拓戦略(B2BとB2Cの場合の違い)について網羅的に解説します。実務に直結する「使える知識」を意識しつつ、専門性と信頼感のあるトーンでまとめました。
目次
シード期:アイデアを形にし仮説検証する段階
特徴と課題
シード期は、ビジネスアイデアが生まれた直後からプロトタイプ開発・市場仮説の検証を行う段階です。プロダクトはまだ完成しておらず、多くの場合は試作品(MVP)の開発や事業計画書の作成、想定顧客へのヒアリング・アンケート調査などが中心となります。売上はほとんど期待できず、市場ニーズと事業モデルの仮説検証が主目的です。リソース(人材・資金)が極めて限られている中で、プロダクトの種を育てることが求められます。最大の課題は、この限られたリソースでプロダクトの方向性が正しいかどうかを見極め、次のステージに進むための土台を作ることです。
事業開発の進め方(バリュープロポジション設計・プロダクト開発・PMF戦略)
まずはバリュープロポジション(提供価値)の明確化が不可欠です。バリュープロポジションとは「顧客が望んでいて、競合相手は提供できず、自社が提供できる価値」のことです。シード期では、自社の製品・サービスがどんな顧客課題を解決し、なぜ顧客に選ばれるのかを一言で説明できるようにしましょう。価値仮説が不明瞭だと、この先の開発や顧客開拓もぶれてしまいます。
次に、ターゲット顧客の設定と課題検証を行います。想定した顧客セグメントを定め、その顧客が抱える課題やニーズを深く理解します。ヒアリングや簡易なユーザー調査を通じて、「本当に解決すべき問題か」「現在はどのように解決しているか(競合や代替手段)」などを確認します。ここで得た知見をもとに、製品コンセプトや機能の優先順位を絞り込みます。
そして、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)を開発し、早期に市場からフィードバックを得ることが重要です。限られた機能セットで構わないので、試作品やベータ版を作り、実際のユーザーに使ってもらいます。ユーザーの反応を観察し、「提供価値」が伝わっているか、仮説通りの課題解決が行えているかを検証します。例えばB2Cサービスであれば知人やコミュニティ内でユーザーテストを行い、B2Bビジネスであれば業界内の知り合い企業に協力を仰いでPoC(概念実証)を実施するとよいでしょう。こうした小規模な実験と学習を繰り返すリーンスタートアップ的なアプローチが、シード期のプロダクト開発には適しています。
フィードバック結果によってはピボット(方向転換)も検討します。仮説が誤っていた場合、顧客セグメントの見直しや製品コンセプトの修正を迅速に行いましょう。シード期は失敗が許容される段階です。大きなリソースを投下する前に軌道修正し、将来のPMF(プロダクトマーケットフィット)達成に向けて最も有望な種を選び抜く柔軟性が求められます。
資金調達のポイント(エンジェル、VC、CVC、デット等)
シード期は大規模な資金を必要としないため、調達手段は限られた範囲で行うのが一般的です。必要資金は数百万円程度にとどまるケースが多く、創業者の自己資金や家族・友人からの出資で賄う場合がほとんどです。不足する場合でも、この段階ではエンジェル投資家(個人投資家)からの出資や、インキュベーター・アクセラレーターといった起業支援プログラムからの支援を検討します。日本の場合、自治体や政府系の創業助成金・補助金を活用できるケースもあるため、スタートアップ支援施策を調べて応募するのも有効です。
実績やプロダクトがまだ不十分なシード期にVC(ベンチャーキャピタル)やCVC(事業会社のコーポレートベンチャーキャピタル)から出資を受けることは稀ですが、将来の大型調達を見据えて投資家とのネットワークを構築しておくことは重要です。例えばアクセラレーター経由でデモデイに出場し、VC関係者に存在を知ってもらうだけでも次フェーズの資金調達が有利になります。なお、銀行融資やデットファイナンス(負債による資金調達)はこの段階では信用力や事業実績が不足しており現実的ではありません。まずはエクイティ(株式)による調達や助成金でつなぎ、プロダクト開発と検証に集中しましょう。
組織構築の戦略(採用、チームビルディング、文化醸成、インセンティブ設計)
シード期の組織は創業メンバー数名程度の極小チームで、「人」そのものが最重要リソースです。事業アイデアの実現には優秀な仲間が欠かせませんが、知名度も資金も乏しい創業期スタートアップに人材を呼び込むのは容易ではありません。そこでビジョンや熱意に共感してもらえる仲間集めが鍵となります。この時期は人員の「量より質」を重視し、会社のミッションや価値観を深く共有できるメンバーを厳選して迎え入れましょう。具体的には、創業者の人脈をフル活用して声をかけたり、スタートアップイベントで出会った人に仲間になってもらうなど、人的ネットワークによる採用が中心になります。
採用できた初期メンバーには、広範な役割を担ってもらう必要があります。シード期では一人ひとりが「営業もしつつ開発もする」「企画もしつつバックオフィスも見る」といったように、複数の帽子を被るのが当たり前です。明確な部署分けや階層構造もないフラットな組織で、創業者はプレイヤーであると同時に全員の士気を高めるリーダーシップを発揮することが求められます。忙しい中でも企業文化の種を植えることも大切です。例えば「顧客志向」「チャレンジを称賛する」など、将来の文化の核となる価値観を言語化し、日々のコミュニケーションで共有していきます。人数が少ない今のうちにメンバー間の信頼関係を深め、心理的安全性の高いチームを作っておくと、後の成長ステージで組織が拡大しても一体感を保ちやすくなります。
インセンティブ設計の面では、資金に余裕がないシード期こそ株式・ストックオプションによる報酬設計を検討します。将来的な企業の成功時にリターンを得られるストックオプションは、金銭報酬を補完する強力なモチベーション策になります。日本ではストックオプション制度の活用が徐々に一般的になってきていますが、創業初期に制度を整備しておけば、アーリー期以降の採用競争でも魅力的なオファーを提示できるでしょう。
マーケティングと市場開拓戦略(B2B/B2Cアプローチの違い)
シード期のマーケティングは、大規模な広告展開よりも目の前のユーザー獲得と課題検証に重きが置かれます。プロダクトが完成していない段階では、まず少数のコアなユーザーに使ってもらい、その声を製品改良にフィードバックすることが目的となります。
- B2Bの場合
-
創業者自ら業界の知人や紹介を辿って潜在顧客にアプローチし、直接ヒアリングやデモを行う「泥臭い」方法が中心です。大企業向けビジネスであれば、いきなりトップ企業に売り込むよりも、まずは中小規模の企業や知見のあるメンター企業に協力してもらい、PoC事例や導入実績を作ることが重要です。日本市場では実績が信頼に直結するため、最初の1社を獲得し成功させることで、次の顧客開拓が格段に進めやすくなります。
また、業界イベントやピッチコンテストに参加して存在をアピールし、人脈を広げることも有効でしょう。限られたリソースではありますが、顧客候補との関係構築(リレーション営業)に時間を割くことが将来のパイプライン構築につながります。
- B2Cの場合
-
まずは身近なコミュニティからユーザーを獲得し、製品のフィードバックを集める戦略が考えられます。例えばSNSや友人ネットワークを活用してベータユーザーを募集したり、TwitterやInstagramでサービスのコンセプトを発信して興味を引き、少人数でも熱心に使ってくれるユーザーを見つけます。大規模な広告予算はないため、SNSでの情報拡散や口コミ、あるいはWebメディアで取り上げてもらうためのPR活動が中心です。
プロダクトのコアな価値に共感する一部のユーザーに刺さるメッセージを磨き上げ、熱狂的なファンを創り出せれば成功です。そのユーザーたちが周囲にサービスを薦めてくれるようになれば、次のアーリー期に向けた土壌ができあがります。
アーリー期:PMF達成と事業拡張の基盤作りの段階
特徴と課題
アーリー期は、シード期を経てプロダクトが市場に出始め、本格的に事業モデルの検証と拡大準備を行う段階です。一般的に従業員数が10人以下程度の小さな組織からスタートし、このフェーズで徐々に人員と顧客数が増えていきます。プロダクトの必要最低限の機能が出揃い始め、実際の顧客からフィードバックを受けて改善を繰り返すことで、プロダクトマーケットフィット(PMF)の達成を目指します。PMFとは「顧客が満足する商品を、最適な市場で提供できている状態」を指し、スタートアップの成否を左右する重要なマイルストーンです。
アーリー期の課題はまさに、このPMFをいかに早く確実に掴むかにあります。収益面では依然として赤字が続くケースが多く、事業を成立させる仕組みを証明しなければならない一方で、開発や人件費への先行投資は継続するため、キャッシュ消費が激しい時期でもあります。資金切れのリスクに備えつつ、事業の将来性を示す実績作りが求められるでしょう。また、組織面ではメンバーが増え始めることで、創業者だけでは回らない業務も出てきます。徐々に業務を仕組み化し始めないと、成長の妨げになることも課題となります。
事業開発の進め方(バリュープロポジション再検証・プロダクト改良・PMF戦略)
アーリー期における事業開発の最優先事項は、PMF(プロダクトマーケットフィット)の達成です。シード期に描いた仮説が市場で通用するか、本当に顧客が価値を感じてお金を支払ってくれるかを、この段階で見極めます。具体的な進め方として、まずユーザーからのフィードバック循環を高速化します。製品の初期バージョンをリリースしたら、ユーザーの使用状況データや直接の声を収集し、迅速に機能改善やUX向上に反映させます。開発チームはアジャイルな手法で短いサイクルのリリースを繰り返し、仮説検証を継続しましょう。例えば、「ある機能が使われていない→不要なので削減」「特定の使い方が目立つ→その用途に特化したUIに改良」といった微調整を繰り返し、顧客満足度を高めることが重要です。
次に最も熱心な顧客層を特定します。つまり、現在のユーザーの中でプロダクトに強い価値を感じて頻繁に使ってくれる顧客セグメントはどこかを見極めます。CTO for goodの解説にもあるように、「最も購買意欲の高い顧客層」を見つけ出し、その層で事業が拡大可能であることを実証することが求められます。この層こそが当面のプロダクトのビーチヘッド(攻略拠点市場)となり得ます。例えばB2Cサービスであれば、まずは20代女性の中でも特定の趣味を持つ層に受け入れられているなら、そこにリソースを集中投入し、更なる支持を固めましょう。B2Bであれば、特定業界の中小企業にはまっているなら、まずはその業界内でトップクラスのシェアを取るくらいの勢いで導入を増やします。狙う顧客層が絞り込まれてきたら、そのセグメント内で口コミや紹介が発生するような仕掛けも有効です。満足した顧客が同業他社や友人に薦め、新たな顧客を連れてきてくれる状態になれば、PMFに近いと言えます。
また、ビジネスモデル(収益モデル)の検証も並行して行います。プロダクトの利用者が増えても、収益化の方法が不明確では持続的な成長は見込めません。アーリー期には実ユーザーから収益を得る仕組みを試行します。価格設定をテストしたり、フリーミアムモデルでどの程度有料転換するかを確認したり、B2Bであれば初期導入費用と月額課金のバランスを検討します。ユニットエコノミクス(単価あたり収益とコストの採算)が将来的にプラスになる見込みかどうか、LTV(顧客生涯価値)とCAC(顧客獲得コスト)の比率は妥当か、といった指標にも注目します。もし収益モデルに難がある場合は、機能の有料・無料の切り分け方を変える、サービス提供方法を変える(例:直販からサブスクリプションへ)などピボット的な調整も検討します。
さらに、競合環境も注視します。もし類似サービスを提供する競合が現れた場合、自社の提供価値を再点検し差別化ポイントを強化します。他社との差別化戦略を練り直し、自社が選ばれる理由(バリュープロポジション)を改めて明確化します。「競合他社にはなく自社だけが提供できる価値は何か?」をチーム全員で再確認し、プロダクトやメッセージに反映させます。この問いに明確に答えられる会社こそがPMFに近づいている会社です。逆に言えば、PMF前のスタートアップの約半数はこの問いに即答できないとも指摘されています。それだけPMF前夜には自社の価値が定まっていないことが多いということです。アーリー期には何度でもこの問いに立ち返り、答えを磨き上げていきましょう。
資金調達のポイント(エクイティ調達、VC・CVC、補助金の活用、デットファイナンス検討)
アーリー期に入ると、事業を加速させるために本格的な資金調達が必要になります。多くのスタートアップはシリーズAラウンドと呼ばれるVCからの出資をこの段階で受けます。VCは成長可能性のあるスタートアップに数千万円から数億円規模の資金を投資しますが、そのためには上述したPMFの兆しや顧客獲得の実績、明確な成長戦略を示すことが求められます。投資家は「この事業を大きく伸ばせるか?」を厳しく見極めるため、データに基づいたピッチを準備しましょう。ユーザー数の増加率、リテンション(継続利用率)、トラクション(取引額や利用頻度など事業の勢いを示す指標)、そしてチームの実行力をアピールします。
資金調達の方法としては、引き続きエクイティによる出資が中心ですが、出資元の幅が広がります。独立系VCだけでなく、事業会社の戦略子会社であるCVCから資金提供を受けるケースも増えます。CVCは単なる資金提供だけでなく、親会社との事業提携や販路提供などシナジーを見込んだ支援をしてくれる可能性があります。ただし提携先企業との関係が密接になるため、将来の事業の独立性や他社との取引制限などには注意が必要です。
また、行政の支援策も引き続き活用しましょう。経済産業省やNEDOなどが実施するスタートアップ向け助成金や補助金、東京都など自治体の成長支援プログラムから資金や稼働資金を得ているスタートアップも多くあります。CTO for goodの指摘にもあるように、補助金・助成金の支援を上手に使い、運転資金を確保することもアーリーステージの重要な戦略です。助成金は資本の希薄化を招かずに資金を得られる点で魅力的ですが、申請手続きや報告義務など手間もかかるため、専任リソースが割けない場合は無理のない範囲で検討します。
デットファイナンス(負債による資金調達)については、アーリー期では慎重な検討が必要です。売上が立ち始めていても安定収益には至っていない場合が多く、銀行融資を受けても返済が事業の重荷になるリスクがあります。ただ、日本政策金融公庫の新創業融資など、スタートアップ向けの無担保融資制度を利用できる場合もあります。融資を受ける場合は、返済計画を現実的に立て、最悪追加の資金調達が長引いても倒産しないラインを見極めて借りすぎないことが大切です。最近ではVCからの出資と組み合わせて、ベンチャーデット(将来の売上や株式を担保とした融資)を活用する例も出てきました。デットは株式の希薄化を防げる利点がありますが、経営に与えるリスクとリターンを天秤にかけて判断しましょう。
組織構築の戦略(採用計画、チーム体制強化、文化の定着、ストックオプション制度など)
アーリー期では、チームがシード期の数名から徐々に拡大し始めます。シリーズA資金調達後は、事業成長に必要な人材を一気に採用していくケースもあります。組織づくりのポイントは、必要なスキルセットの明確化と計画的な採用、そして創業時の文化・バリューの定着です。
まず、人員計画としてプロダクト開発・営業・カスタマーサクセス・バックオフィスなど役割別に採用ニーズを洗い出します。シード期には全員がゼネラリスト的に動いていましたが、アーリー期では専門スキルを持つ人材を迎え入れることで事業の加速が期待できます。
例えばプロダクト開発速度を上げるために経験豊富なエンジニアを増員する、顧客開拓のために営業担当を初めて雇う、財務管理のために経理人材やパートタイムのCFOを入れる、といった具合です。ただし一度に多く採用しすぎると文化が希薄化する恐れがあるため、「このポジションを今採用することで事業上どんなボトルネックが解消されるか」を考え、優先順位を付けて採用しましょう。
採用面では引き続きスタートアップの認知度不足との戦いがあります。シード期と違い多少プロダクトや会社の実績が出てきたとはいえ、まだまだ知名度は高くありません。優秀な人材に興味を持ってもらうために、自社のミッション・ビジョンを発信していくことが大切です。ブログやSNS、イベント登壇などで事業の魅力や社会的意義を語り、「面白そうなことをやっている会社だ」と感じてもらえるよう露出を増やします。また、採用プロセスも整備し始めます。創業者一人で面接していた状態から、技術面接はCTOが行う、カルチャーフィットは別のメンバーも交えて複数人で評価する、といった形で採用の仕組み化を進め、公平で見極め精度の高い採用を目指します。
組織体制の強化では、社内コミュニケーションの仕組み作りがポイントです。人数が二桁に近づくと、全員が常に同じ情報を共有している状態を保つのが難しくなります。定例ミーティングや週次全体朝会を導入して目標や成果を共有したり、情報共有ツール(チャットや社内Wiki)を整備して誰でも必要な情報にアクセスできる環境を整えましょう。また、権限移譲も徐々に進めます。創業者がすべての細部まで決裁・指示していてはスピードが落ちますので、領域ごとに信頼できるメンバーに裁量を与え、自律的に動けるチームを育てます。例えば開発リーダーには技術判断を任せ、営業リーダーには顧客対応の裁量を持たせる、といった具合です。もちろん重要事項は経営陣で議論しますが、日常的な意思決定は現場に近い人が行えるようにすると組織が伸び伸び動けます。
企業文化の醸成にも引き続き注力します。シード期に芽生えた文化や価値観を、新しいメンバーにも浸透させる必要があります。入社時のオンボーディング研修でミッション・バリューを伝えたり、バリュー体現者を表彰する仕組みを作るなどして、「自社らしさ」を組織に根付かせます。アーリー期は会社のカルチャーを形作る重要な時期です。このタイミングで文化が定まらないと、グロース期以降に組織が大きくなった際に一体感を保つことが難しくなります。
インセンティブ設計では、シード期に導入したストックオプション制度を活用し、初期参加メンバーへの報いる仕組みや新規入社メンバーへの付与を検討します。会社の価値が上がるほどストックオプションの魅力も増しますので、将来の成功を全員で目指す一体感を醸成する上でも有効です。また、明確な目標設定とそれに対する賞与や評価制度を簡易的でも設け始め、メンバーのモチベーションを維持・向上させる工夫も行います。
マーケティングと市場開拓戦略(B2B/B2Cアプローチの拡大)
アーリー期のマーケティングは、仮説検証からスケーラブルな成長施策へシフトしていきます。プロダクトが市場で受け入れられる手応えを得始めたら、その成功パターンをより多くの顧客に展開していく必要があります。ただし闇雲に拡大するのではなく、シード期に掴んだコアユーザー層を起点に効率よくユーザー基盤を広げる戦略を取ります。
- B2Bの場合
-
引き続き顧客開拓は重要ですが、この段階ではリードジェネレーション(見込み顧客の獲得)手法を拡充していきます。具体的には、Webサイトを整備して資料ダウンロードや問い合わせを促すインバウンドマーケティングを開始したり、ホワイトペーパーや事例紹介資料を作成して見込み顧客に提供したりします。業界イベントや展示会への出展も効果的です。シード期は人脈頼みの営業が中心でしたが、アーリー期ではオンライン広告や業界専門メディアへの露出も検討します。特にニッチなB2Bプロダクトの場合、関連する業界ニュースサイトやメールマガジンに広告を出すとターゲット層にリーチしやすくなります。
また、初期の顧客から得た成功事例(ケーススタディ)をコンテンツ化し、自社サイトや営業資料で紹介することで信頼性を向上させます。これは日本市場で新参者が信用を得る上で非常に有効です。加えて、顧客対応体制も強化します。顧客数が増えてくると、導入後のサポートが事業の評判を左右します。専任のカスタマーサクセス担当を置き、既存顧客の活用促進や継続利用(リテンション)向上を図ります。満足した顧客は追加契約(アップセル)や他社紹介にもつながるため、単純に新規開拓一辺倒ではなく既存顧客の成功にも注力することで、安定成長の基盤を築きます。
- B2Cの場合
-
ユーザー規模を拡大するために、デジタルマーケティングへの投資を本格化します。具体的には、GoogleやFacebook(Instagram)、Twitter(X)といったプラットフォームでのオンライン広告を試し、どのチャネルが最も効率よくユーザーを獲得できるか検証します。少額からABテストを繰り返し、広告のクリエイティブやターゲティング精度を高めていきます。加えて、シード期に芽生えたユーザーコミュニティや口コミ効果を更に広げるため、紹介プログラム(リファラルキャンペーン)を導入するのも有効です。
既存ユーザーが友人を招待すると双方に特典が与えられる、といった仕組みでユーザーを増やしていきます。コンテンツマーケティングも強化しましょう。ブログやSNSで有益な情報発信や、サービスに関連するコンテンツを提供してファンを増やします。例えばサービスの使いこなし術や成功体験を紹介する記事を作成し、自社メディアやnoteなどで発信します。検索エンジン最適化(SEO)も意識して、潜在ユーザーが課題解決策を検索した時に自社サービスにたどり着くような記事作りを行います。さらに、メディア露出を増やす広報活動もこの時期に力を入れると良いでしょう。
資金調達を実施したタイミングでプレスリリースを配信したり、サービスのユニークな取り組みがあれば新聞・雑誌・オンラインニュースに売り込むなどして認知度を上げます。プロダクト面でもグロースハックの発想を取り入れます。ユーザーのアクティブ率やリテンションを向上させるために、UI/UXの改善やプッシュ通知・メール配信によるリマインド施策などを行います。データ分析基盤を整備し、ユーザー行動データからボトルネックを発見して改善を回す仕組みを構築します。B2Cサービスはスケールが命とはいえ、獲得したユーザーが定着しなければ意味がありません。ユーザーライフサイクル全体を意識したマーケティング(新規獲得→オンボーディング→活性化→休眠防止)を実践し、じわじわと「使い続けてもらえるユーザー」の母数を増やしていきます。
グロース期:事業の急拡大とスケーリングの段階
特徴と課題
グロース期は、PMFを達成したプロダクトを本格的にスケールさせる段階です。初期のコアユーザー獲得に成功し、顧客からの評価も得られた事業が、いよいよ多数のユーザーや市場へと急拡大していきます。ユーザー数や売上が飛躍的に伸び始め、年率数倍の成長が起こることも珍しくありません。例えば、それまで無料で提供していたサービスに有料プランを導入するなど収益化施策もスタートし、売上規模が一段上がるケースが多いです。
一方で、成長痛(Growing Pains)とも呼ばれる課題が噴出するのもこのフェーズです。急激なユーザー増加にシステムやサービス体制が追いつかず品質低下のリスクが高まったり、組織が大きくなることで情報共有や意思決定が複雑化したりします。加えて、売上が伸びてもそれ以上に支出(人件費、マーケティング費用、設備投資等)が増えるため、依然キャッシュフローは逼迫しがちですctoforgood.com。グロース期では「成長スピード」と「経営管理」の両立が大きなテーマとなります。市場では競合との戦いも本格化し、シェア獲得競争が激しくなります。競合他社も資金調達をして攻勢を強めてくる中、自社が市場でリーダーシップを取るための戦略が求められます。
また、将来的なIPO(株式上場)やM&Aを見据えた動きも視野に入り始めるのがこの段階です。社内では組織規模が数十人から百人規模へと膨らみ、創業時からのメンバーだけではカバーしきれない専門性やマネジメント力が必要になります。人・モノ・カネすべてにおいてスケールさせることが、グロース期の特徴であり課題と言えるでしょう。
事業開発の進め方(スケール戦略、新規事業・サービス拡張、プロダクト強化)
グロース期の事業開発は、基本となるビジネスモデルが実証された上でのスケール戦略が中心となります。まずコア事業については、市場浸透戦略の徹底です。つまり、現在狙っている市場セグメントにおいて可能な限りシェアを高めるために手を打ちます。営業力・マーケティング投下量を増やし、競合に先んじて顧客基盤を押さえにかかります。B2Bであれば主要な見込み顧客リストを洗い出しトップアプローチを仕掛けたり、代理店チャネルを構築して間接販売網を拡大したりします。B2Cであればオンライン広告の予算を大幅に増やしテレビCMや交通広告などマスマーケティングにも乗り出すことで、一気にユーザー数を拡大させます。
重要なのは、単にお金をかけるだけでなくROIをモニタリングすることです。CACが許容範囲に収まっているか、LTVが継続して向上しているか、データに基づきながら攻めと守りのバランスを取ります。グロース期は「とにかく規模を追う」フェーズと捉えられがちですが、無秩序に拡大して一時的な売上だけ伸ばしても持続しません。健全なユニットエコノミクスを維持しつつ成長させることで、次のレイター期(上場準備段階)への展望が開けます。
次に、プロダクトの拡張・強化です。既存プロダクトでPMFを達成したとはいえ、市場やユーザーの要望は進化し続けます。競合も新機能を投入してくるでしょう。そこでグロース期にはユーザーの声をさらに大規模に集め、プロダクトロードマップに反映させます。データドリブンな開発体制を整え、大量のユーザーデータを分析してエンゲージメントを高める機能改善や、新機能の投入を行います。また、技術的負債の解消もこの段階で計画的に進めます。
シード〜アーリー期の急造でシステムに負荷が生じている場合、アーキテクチャの刷新やコードのリファクタリング、人員増強による開発プロセス改善など、プロダクト基盤を強固にする投資も必要です。可用性やセキュリティを高めることは、大量ユーザーを抱えるフェーズでは欠かせません。
さらに、新サービスや事業の拡張も視野に入ります。コア事業が軌道に乗ったからといって気を緩めるわけにはいきません。シナジーのある周辺領域へのサービス拡充や、追加の収益源を生むビジネスラインの検討も行います。例えば既存プロダクトのプレミアム版を提供したり、ユーザー層に関連する別サービスを開発するなどです。
ただし本業がまだ成長途上であれば、リソースを分散しすぎないよう慎重に判断します。新規事業への進出は、市場シェアを固めてからでも遅くありません。とはいえ競合に先手を取られないために、将来有望な種を仕込んでおくことも大事です。ここは経営陣の戦略眼が試される部分でしょう。
提携やパートナーシップ戦略もグロース期ならではの施策です。自社単独ではリーチできない市場や不足する機能を補うため、他社との提携を模索します。例えば大企業との資本業務提携により大きな顧客基盤にアクセスしたり、自社APIを公開して周辺サービスとの連携エコシステムを構築したりします。海外展開もこの段階で具体化します。日本国内である程度シェアを取ったら、アジアや米国など海外市場への進出を検討するスタートアップも多いです。
その際、現地のパートナー企業と組んで進出する、現地子会社を立ち上げるなど戦略を練ります。ただし海外展開はコストもリスクも高いため、自社の足腰(財務基盤や本社組織)がしっかりしてから挑むのが基本です。
資金調達のポイント(大型調達、CVC・海外投資家、デット活用、IPO準備)
グロース期の資金調達は、さらなる事業拡大のための大型調達が中心となります。シリーズB、シリーズCといったラウンドで数億〜数十億円規模の資金を調達し、人材・マーケティング・設備に積極投資するケースが増えます。実際、日本のスタートアップでもシリーズBで平均3億円前後、シリーズCで平均4億円近い資金調達を行っているというデータもあります。この段階では国内外の大手VCや事業会社、さらには海外投資家(米国やアジアのファンド)が出資に加わることも珍しくありません。彼らはマーケットリーダーになり得る急成長企業を探しており、自社がまさにそれに該当することを示す必要があります。
具体的には、明確な市場優位性(競合に対する優位なポジション)、顧客基盤の拡大スピード、収益モデルの実証、強力な経営チームなどが評価されます。特にグロース期は競争が激化する局面であるため、「このタイミングで資金を入れれば市場を押さえられる」と投資家に思わせることが重要です。
資金調達手法としては引き続きエクイティが主軸ですが、デットファイナンスの活用も現実味を帯びてきます。売上や将来キャッシュフローの見通しが立ったことで、金融機関からの融資や社債発行、ベンチャーデットによる調達が可能になります。CTO for goodも指摘するように、グロース期では成長に伴い支出が急増するためキャッシュ管理を厳格に行い、必要に応じVCからの追加出資や銀行借り入れも行われます。
負債による調達は株式の希薄化を避けられるメリットがありますが、借入金の返済義務が生じるため、返済計画と成長見込みのバランスを慎重に検討する必要があります。特に金融機関との取引実績を作ることは、いざというときの資金繰りの選択肢を増やす意味でも有益です。日本のメガバンクや地方銀行も、成長企業向けに融資を行うケースが増えてきています。一定の売上規模や黒字化が見えてきたら、銀行借入による資金調達も交渉してみる価値があります。
グロース期後半になると、IPO(新規株式公開)やM&A戦略も視野に入ります。シリーズC以降の調達では「最後の上場前資金調達」という位置づけで、証券会社や上場準備ファンドが関与することもあります。上場を見据えてガバナンスやコンプライアンス体制を強化する、社内規程を整備するといった準備も資金調達と並行して進めます。
もっとも、日本では上場がゴールになりがちですが、上場はあくまで成長資金確保の一手段です。グロース期ではIPO後も見据えた持続成長可能なビジネスモデルを完成させておくことが肝要です。
組織構築の戦略(マネジメント体制、組織プロセス整備、企業文化の深化、人事制度)
グロース期の組織構築は、「スタートアップから企業へ」の転換点とも言える重要なフェーズです。社員数が二桁後半から三桁に達するころ、もはや全員が顔と名前を把握できない状況になり、経営陣の目が行き届かない領域も増えてきます。そこで、マネジメント体制の強化が不可欠となります。
具体的には、各部門にマネージャーや役職者を配置し、組織階層を整備します。創業メンバーから昇格したリーダーだけでなく、必要に応じて外部から経験豊富な人材を幹部クラスとして採用することも検討します。急拡大する組織では「将来の幹部候補になりうる人材の採用」や「権限移譲の進め方」がよく課題に挙がります。これらに対応するため、経営陣は自らのマネジメントスキルを磨くとともに、組織開発の専門家やHRの力を借りて計画的に組織デザインを行います。
組織プロセスの標準化も大きなテーマです。シード・アーリー期には人に依存して属人的に回していた業務を、誰が担当しても一定の成果が出せるようプロセス化します。営業手法のマニュアル整備、開発プロセスのドキュメンテーション、カスタマーサポート対応フローの整備など、各部署でノウハウを形式知化し、新人が入っても素早く戦力化できる体制を築きます。これは単に効率化のためだけでなく、事業クオリティの維持にもつながります。属人的だと人が抜けたときに品質低下しますが、仕組みがあれば組織として安定したサービス提供が可能になります。
企業文化の深化と人事制度の確立も欠かせません。数十人からなるチーム全員が同じ方向を向いて働けるようにするには、共通の文化と明確なルールが必要です。創業以来のミッション・ビジョン・バリューを改めて全社で共有し直し、新しい世代の社員にも腹落ちさせます。社内報や全社イベント、経営トップからの定期メッセージ発信などを通じて、企業文化を意識的に醸成します。一方で、人事制度(評価・報酬制度)も整備します。等級制度や評価基準を策定し、公正な評価・昇給昇格を行うしくみを作ります。
スタートアップの初期には不揃いだった給与レンジやタイトルも、組織が大きくなるにつれ不公平感が出ないよう標準化が求められます。また、社員の成長を支援する研修制度や1on1ミーティングの導入、福利厚生の充実など、「働きがい」と「働きやすさ」の両面から人材流出を防ぎ定着率を上げる施策も講じます。急拡大期にはどうしても人の出入りが激しくなるため、キー人材の流出を防ぐとともに、新規採用者が早期にフィットするよう受け入れ体制を強化することが重要です。
最後に、経営管理体制の強化です。財務・法務・労務といったバックオフィス機能を充実させ、内部統制やコンプライアンスにも目を向けます。上場を目指すのであれば、この段階で監査法人や証券会社と準備を進める必要があり、社内にCFOや管理部長を置いてプロジェクトを推進します。スタートアップらしいスピード感と、大企業的な管理体制のバランスを取る難しさはありますが、信頼性の高い会社になることで得られるメリット(大口取引の獲得や優秀人材の採用など)は大きいです。
創業者にとって組織が自分の手に負えないくらい大きくなることは嬉しくもあり不安でもありますが、適切にデザインされた組織と制度によって「人が人を育てる」循環が生まれれば、さらに強い成長エンジンが出来上がります。
マーケティングと市場開拓戦略(B2B/B2Cアプローチのスケール)
グロース期のマーケティング・営業戦略は、大きくスケール(規模拡大)に舵を切ります。ここまでに見つけた効果的なチャネルや戦術に対して、一気にリソースと予算を投入し、市場シェアを獲得しに行きます。ただし、単に焼畑的にばら撒くのではなく、データに基づく洗練されたマーケティングを展開することが求められます。
- B2Bの場合
-
本格的な営業組織を構築し、ターゲットとする市場セグメントごとに専任の営業チームやアカウントマネージャーを配置します。例えば中小企業向けチームとエンタープライズ(大企業)向けチームで戦略を分け、それぞれに適した提案資料やセールストークを用意します。リード管理にはCRMシステムを導入し、見込み顧客へのフォローアップや育成(リードナーチャリング)を自動化・効率化します。マーケティング部門も拡大し、オンライン施策(広告・SEO・ウェビナー等)からオフライン施策(展示会・セミナー・業界誌広告等)まで統合的にプランを回します。
加えて、この段階ではパートナー戦略が有効になる場合があります。販売代理店やコンサルティング会社などと提携し、間接販売チャネルを活用して自社ではリーチできない顧客層を獲得します。特に地方市場や特定業界に強いパートナーと組むことで、効率よく販路を拡大できます。また、大企業との協業も進め、彼らの顧客基盤に自社サービスを売り込ませてもらう仕組み(大企業のソリューションに組み込んでもらう等)を作るケースもあります。
顧客数が増大したことで、カスタマーサクセス/サポート体制もさらに強化・拡張します。ハイタッチな大型顧客向けには専任のカスタマーサクセスマネージャーを付け、定期的なビジネスレビューを実施して顧客満足度を維持します。中小顧客向けにはオンボーディングプログラムを標準化し、ウェビナーやオンラインヘルプで効率的にサポートします。解約(チャーン)をいかに防ぐかが事業価値に直結するため、プロアクティブなサポートで顧客ロイヤルティを高め、契約更新率の向上に努めます。
- B2Cの場合
-
ユーザー獲得に関しては、グロースマーケティングチームを組織し、データ分析とクリエイティブ制作に長けた人材を配置して、ユーザー獲得から育成までのファネル最適化にフルコミットします。広告運用ではより高度なターゲティング(類似ユーザー配信やリターゲティング等)を駆使し、1ユーザー当たりの獲得コストを常にモニタリングしながら予算配分を最適化します。オーガニック流入を増やすため、コンテンツSEOやSNSキャンペーンを地道に展開し、指名検索(ブランド名で検索されること)を増やすことで広告に頼りすぎないブランド力を育てます。
大規模ユーザー基盤を活かしたネットワーク効果の醸成も図ります。既に数万人・数十万人のユーザーがいるのであれば、ユーザー同士の交流フォーラムやコミュニティイベントを開催してユーザー参加型の盛り上がりを作ったり、ユーザー生成コンテンツ(UGC)を促進してサービス自体が宣伝塔になるような仕掛けを作ります。例えば人気ユーザーを公式アンバサダーに任命しSNSで発信してもらう、コンテストを開催して入賞者を顕彰するといった施策です。
また、プロダクト内でのバイラルループを組み込むことも有効です。ユーザーが友人を招待したくなる仕組みや、使えば使うほど他のユーザー価値も高まるような機能(ネットワーク効果)は、サービスの自己成長を促進します。市場拡大については、国内だけでなく海外市場へのアプローチも本格化します。日本で成功したB2Cプロダクトの中には、東南アジアや北米など海外に進出する例も増えています。
その場合、現地の文化や競合を踏まえたマーケティング戦略を新たに策定し、UIのローカライズや機能調整も行います。国外展開はハードルが高いですが、成功すれば事業の成長ポテンシャルが一気に拡大します。グロース期の大胆な挑戦として検討する価値があるはずです。
最後に、競合とのポジション争いにも戦略的に臨みます。同じグロース期にある競合他社がいる場合、市場でのプレゼンスを高めるためにブランディング投資も辞さない覚悟が必要です。具体的には、テレビCMや有名タレントを起用したキャンペーンなど大規模予算を投入し、自社名がターゲット顧客に確実に刷り込まれるような施策を行うこともあります。日本市場では一度ブランドイメージが確立すると顧客の信頼を得やすくなるため、資金に余裕が出てきたグロース期であればブランディングへの投資リターンも見込めます。
まとめ
シード期・アーリー期・グロース期と、スタートアップの成長に沿って事業開発のポイントを解説してきました。
各フェーズで直面する課題は異なりますが、一貫して重要なのは「顧客にとっての価値」を軸に意思決定することです。シード期ではその価値の種を見極め、アーリー期で確かな芽(PMF)へ育て、グロース期で大樹へと成長させるイメージです。その過程で、資金調達・組織作り・市場攻略という経営の主要要素をバランス良くマネジメントしていく必要があります。
日本のスタートアップ環境においても、近年は起業支援制度の充実やVC資金の増加によりチャレンジしやすい土壌が整ってきました。しかし最終的に生き残りスケールするスタートアップは、ご紹介したような各段階での綿密な戦略実行と、状況変化に応じた柔軟な方向転換ができた企業です。ぜひ本記事のポイントを参考に、自社のフェーズに合った戦略を見直し、実践に繋げていただければ幸いです。スタートアップの成長の旅路は険しいですが、適切な戦略と情熱を持って挑めば、次のユニコーン企業になる可能性も十分にあります。事業の成功を願っています。
参考文献・情報源
1. スタートアップの成長ステージに関する文献
2. 事業開発・バリュープロポジション関連
3. プロダクトマーケットフィット(PMF)とMVP開発
4. 資金調達戦略・投資家対応
5. 組織構築・チームマネジメント
6. マーケティング・市場開拓
7. グロース戦略・スケール戦略