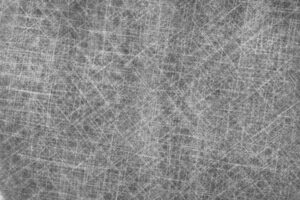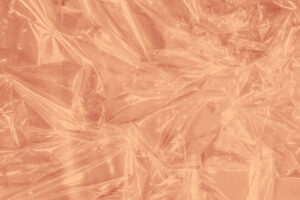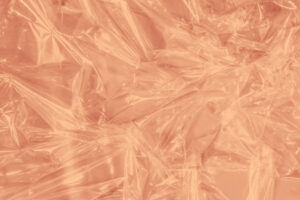現代のビジネスでは、クリエイティブディレクション(Creative Direction)の重要性が増しています。優れたデザインやブランド表現は企業戦略と一体となって初めて効果を発揮します。本記事では、経営者や新規事業責任者に向けて、クリエイティブディレクションの基本から実践までを解説します。デザイン発注時の注意点やブランディング戦略との連携方法、具体的な成功・失敗事例、そして最後にクリエイティブディレクター・ヨコタナオヤの視点もご紹介します。
目次
1. クリエイティブディレクションとは?基本概念と経営視点
クリエイティブディレクションとは、企業の広告制作やブランディング活動における「創造面の総指揮」を意味します。簡単に言えば、デザイナーやコピーライターなどクリエイティブチームの仕事を方向付け、最終アウトプットの品質とメッセージを統括する役割です。
クリエイティブディレクターは単に「見た目を良くする」だけでなく、企業が伝えたいビジョンやメッセージを深く理解し、それを形(デザインや言葉)に落とし込む責任者です。例えば、新商品の広告キャンペーンであれば、商品のコンセプトやターゲット顧客のニーズを踏まえ、「どんなビジュアルと言葉で伝えれば響くか」をプランニングし、制作陣をリードします。
経営者の視点から見ると、クリエイティブディレクションは戦略と創造をつなぐ架け橋です。優れたクリエイティブディレクターは経営戦略・事業目標を理解したうえでクリエイティブに反映させます。
単に「かっこいいから」「流行っているから」といった理由でデザインするのではなく、常に「それが自社の目的達成につながる表現か」を考えます。結果として、クリエイティブディレクションが適切に機能すれば、デザインは企業のブランド価値を高め、ターゲットに響く強力なコミュニケーション手段となるのです。
デザイン発注時のよくある誤解とリスク
経営者や事業責任者がデザインを発注する際、いくつかの誤解からトラブルが生じることがあります。
例えば、「プロに任せればこちらは何も伝えなくても良いだろう」という誤解です。クリエイターは魔法使いではありません。目的や背景を共有しないままでは、どんなに腕の良いデザイナーでも的外れな成果物になりかねません。発注側がビジョンや課題を明確に伝えなければ、「なんとなくオシャレだが使えないデザイン」になったり、時間とコストを浪費するリスクがあります。
もう一つの誤解は、「デザインは最後の仕上げ」程度に考えてしまうことです。商品やサービス開発が終わった後で場当たり的にデザインを依頼すると、戦略と噛み合わない表現になる恐れがあります。
たとえば、新ブランド立ち上げなのに社内でコンセプトが共有されておらず、各担当者がバラバラの指示を出してしまうケースです。このような状況ではデザイナーも困惑し、出来上がったものも一貫性を欠いた仕上がりになります。
誤解によるリスクを避けるには、発注側がクリエイティブディレクションの基本を理解し、適切な準備とコミュニケーションを行うことが不可欠です。次章からは、その具体的なポイントを見ていきましょう。
2. 企業がクリエイティブを発注する際の重要ポイント
効果的なクリエイティブ制作のためには、発注時点からいくつか重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは「目的の明確化」「クリエイティブブリーフの作成」「コミュニケーション手法」の3つに絞って解説します。
(1) 目的の明確化 — デザインの目的を戦略に結びつける
まず最初にすべきは、なぜそのクリエイティブが必要なのか、目的を明確にすることです。
ロゴ刷新ひとつ取っても、「なんとなく古いから」ではなく、「ブランドの認知向上」や「新ターゲット層へのイメージ転換」といったビジネス上の目的があるはずです。ここをはっきりさせずに進めると、「デザインは綺麗だが期待した効果が出ない」という事態になりかねません。
目的が明確であれば、クリエイティブチームへの指示も具体的になります。例えばウェブサイトのリニューアルであれば、「問い合わせ件数を前年比20%増やすため、ユーザビリティとブランディングを両立したサイトにしたい」など、ビジネスKPIと紐づいた目標を設定します。単に「かっこいいサイトにしたい」では、何をもって成功とするか判断できず、方向性も定まりません。
経営戦略とデザイン目的を統合することで、クリエイティブ制作は企業の目標達成に直結したプロジェクトとなります。目的が明確であればあるほど、後工程での意思決定(デザイン案の良し悪し判断など)も一貫性を保ちやすくなります。
(2) クリエイティブブリーフの作成 — 情報を整理し、共有する
目的が定まったら、それを具体化したクリエイティブブリーフ(Creative Brief)を作成しましょう。クリエイティブブリーフとは、プロジェクトの概要や狙いをまとめた文書で、いわば「クリエイティブの設計図」です。これを用意することで、発注側と制作側の認識合わせが格段にスムーズになります。
クリエイティブブリーフに盛り込むべき主な項目:
- プロジェクト概要:依頼するクリエイティブの種類と背景(例:「新製品Aのブランドサイト制作。20代女性への認知拡大が狙い」)。
- 目的・課題:そのクリエイティブで達成したい具体的目標(例:「オンライン購入のコンバージョン率向上」「ブランドの若返り」など)。
- ターゲット:想定するユーザーや顧客像。可能なら属性だけでなく、現状の認識や感じている課題も記載します(ペルソナを設定すると効果的です)。
- キー・メッセージ:伝えたい主なメッセージやコンセプト。一言で言えば何を訴求するデザインかを明らかにします。
- 競合・差別化ポイント:主要競合や既存デザインの傾向、それに対して自社が強調すべき独自性。
- トーン&マナー:デザインや文章の調子・雰囲気。例えば「親しみやすくカジュアル」「高級感と信頼性を両立」など、ブランドにふさわしい表現スタイルです。既にブランドガイドラインがある場合はそれを共有します。
- 成果物の仕様:デザインの形式やサイズ、納期や予算など実務的条件も明記します。納品形式(例:画像ファイルの種類)、利用媒体(Web・印刷・SNS等)によって制約があれば事前に伝えておきます。
このブリーフ作成プロセス自体が、発注側の考えを整理する機会になります。「本当は何を実現したいのか?」を自問し文章化することで、チーム内でも共通理解が生まれます。ブリーフは発注者とクリエイターとの「契約書」であると同時に「ジャンプ台」とも言われます。つまり、お互いの合意事項を示すと同時に、クリエイターの発想を助ける土台にもなるのです。
(3) クリエイティブチームとの適切なコミュニケーション
発注後は、クリエイティブチームとのコミュニケーションが成功の鍵を握ります。良いデザインを生み出すには、発注者(経営者やPM)と制作者(デザイナー等)の間で円滑な意思疎通が不可欠です。コミュニケーションについて、以下のポイントに注意しましょう。
- 初期段階でのすり合わせ:プロジェクトキックオフ時にブリーフの内容を直接説明し、質疑応答の場を持ちます。クリエイター側から質問や提案があれば真摯に耳を傾け、戦略意図を共有します。この段階で齟齬を無くすことで、後々の手戻りを減らせます。
- フィードバックは迅速かつ的確に:デザイン案が出てきたら、レビューとフィードバックを繰り返します。その際、単に「なんとなく気に入らない」「センスが違う」といった曖昧・主観的なコメントは避けましょう。良いフィードバックの基本は「具体的に」「建設的に」「目的に照らして」行うことです。
例えば、「この色は好きではない」ではなく「重要なメッセージ部分が背景色と近く埋もれているように感じます。もう少しコントラストを強められますか?」という伝え方をします。デザインの良い点も指摘し、改善点はプロジェクトの目的(ターゲットに伝わるか、使いやすいか等)に紐づけて伝えると、デザイナーも対応しやすくなります。
- 双方向のコミュニケーション:一方的な指示出しにならないように気をつけます。クリエイティブのプロであるデザイナーから見れば、発注側の提案が最適でない場合もあります。「ここはお任せします」ではなく「この部分は〇〇という狙いだが、より良い表現があれば提案してほしい」といった対話型の姿勢が理想です。発注者のビジネス知見とデザイナーの創造力を擦り合わせることで、当初の想定以上のクリエイティブが生まれることも少なくありません。
適切なコミュニケーションを続けることで、制作チームとの信頼関係が築かれます。その結果、たとえ途中で課題や変更が発生しても柔軟に対処でき、プロジェクトを良い方向へ導きやすくなるでしょう。
3. フレームワークの活用:ブリーフからフィードバックまで
優れたクリエイティブディレクションには、いくつかの定型フレームワークや考え方が役立ちます。ここでは、クリエイティブブリーフ作成、デザインプロセス設計、コンセプト設計とブランド戦略の連携について見ていきます。
(1) クリエイティブブリーフというフレームワーク
前述したクリエイティブブリーフは、クリエイティブ制作の標準的なフレームワークです。広告代理店やデザイン会社ではブリーフのフォーマットがあらかじめ用意されていることも多いですが、基本項目はどれも似ています。目的–ターゲット–メッセージ–根拠–トーンといった要素を一枚にまとめることで、戦略ストーリーが誰にでも見える形になります。
例えば広告業界でよく使われる8項目のブリーフでは、
- 広告の目的
- ターゲット
- 現状の認識(ターゲットが今どう思っているか)
- 将来像(どう感じてほしいか)
- インサイト(心を動かすポイント)
- メッセージ(何を伝えるか)
- 理由(信じられる根拠)
- トーン&マナー(表現の調子)
といった項目を埋めていきます。こうしたフレームを使うことで、抜け漏れなく戦略とクリエイティブの要点を整理できます。
ポイントは、各項目が一貫したストーリーになるよう繋げることです。ターゲットの現状認識からインサイト(潜在的な欲求やニーズ)を導き、それを満たすメッセージと提供価値を決め、最後にそれらをどんなトーンで伝えるか──これらが一本筋の通った論理で結ばれていれば、ブリーフを受け取ったクリエイターも迷いなく制作に入れるでしょう。
(2) デザインプロセスの設計とフィードバックの与え方
クリエイティブディレクションでは、制作プロセス自体のデザインも重要です。闇雲にデザイン案を作っては修正…では効率が悪いため、あらかじめプロセスに段階を設け、各段階でのゴールとフィードバック方法を定めておきます。
一般的なデザインプロセスは以下のようなステップに分かれます:
- リサーチ・コンセプト立案: ブリーフを基に市場や競合のリサーチを行い、コンセプト(方向性のアイデア)を言語化します。この段階で発注側とコンセプトの擦り合わせを行い、認識を共有します。
- ラフデザイン作成: コンセプトに沿ってラフ(大まかなデザイン案やワイヤーフレームなど)を複数作成します。色や構図の方向性など、大枠のイメージを確認する段階です。ここでは細部より全体感に対するフィードバックを行い、「選択と集中」をします(どの案を軸に進めるか決定)。
- デザインの詳細化: 選ばれた方向性でデザインを作り込みます。ビジュアル要素やコピーも具体的に詰め、ほぼ完成形に近いデザイン案を作成します。発注側は細かな点も含めチェックしますが、レビューの際は常に「この修正はプロジェクトの目的に照らして必要か?」を考えましょう。細部へのこだわりが戦略意図から逸れてはいけません。
- 最終確認・仕上げ: 最終案について誤字脱字や色味の最終調整、技術的要件の確認を行います。必要に応じて社内の他部門からフィードバックをもらい、ブランドガイドラインとの整合もチェックします。最終的に発注者が品質にゴーサインを出したら完成です。
各段階でのフィードバックのコツは、「前段階で合意したことから大きくブレないこと」と「指摘事項に優先順位をつけること」です。例えば詳細化の段階になってコンセプトに関わる大変更を要求すると大幅な手戻りになります。気になる点があれば早め早めに共有し、認識違いを潰しておくのが理想です。また、一度のレビューで指摘しすぎると混乱を招きます。重要度の高い修正(ユーザーに誤解を与える致命的な問題など)から優先し、細部のブラッシュアップは後に回すなど、段階的に伝えましょう。
プロセス設計と適切なフィードバックにより、プロジェクト全体をコントロールしやすくなります。デザイナー側もゴールまでの道筋が見えるため作業計画を立てやすく、精神的な安心感を持ってクリエイティブに集中できます。
(3) コンセプト設計とブランド戦略との連携
クリエイティブディレクションの核にあるのがコンセプト設計です。コンセプトとは、「このクリエイティブで伝えたい一貫したアイデアや世界観」のこと。これは企業のブランド戦略と矛盾しないものでなくてはなりません。
企業にはブランド戦略やビジョン、ミッションステートメントなどが存在するでしょう。それらは抽象度が高く、日々のマーケティング活動に落とし込むには解釈が必要です。クリエイティブディレクターは、ブランドのコアバリュー(核心的価値)やパーパス(存在意義)を踏まえつつ、個々のプロジェクトに合わせたクリエイティブコンセプトを策定します。
例えば、「伝統と革新」をブランドバリューに掲げる企業があるとします。この企業が若者向け新商品をPRするキャンペーンでは、コンセプトに「受け継がれる品質に新しい驚きをプラス」といったテーマを据えるかもしれません。これなら伝統(受け継がれる品質)と革新(新しい驚き)という両面を表現できます。具体的なクリエイティブでは、昔ながらの職人技術と最新テクノロジーを融合させたビジュアル表現やコピーライティングを考案する、といった具合です。
ブランド戦略とコンセプトを連携させることで、単発のクリエイティブ施策が全体のブランド物語の一部となります。結果として顧客の中に蓄積されるブランドイメージもブレにくくなり、長期的なファン作りにつながります。逆に、ブランドらしさを無視したクリエイティブは短期的に話題になっても企業資産として残りません。常に「我が社らしい表現か?」という問いを持ちながらコンセプト設計を行うことが重要です。
4. 国内企業の事例に学ぶ:成功と失敗のケーススタディ
ここで、日本企業における具体的なクリエイティブディレクションの事例を見てみましょう。成功事例と失敗事例を一つずつ取り上げ、その要因を紐解きます。同じ国内企業のケースから、実務へのヒントを学んでください。
成功事例:老舗和菓子店「とらや」のリブランディング
創業500年以上の老舗和菓子店「とらや」は、伝統を守りつつ大胆な挑戦をして若い世代や海外市場に成功裏に進出した例として知られます。和菓子離れが進む若年層にアプローチするため、とらやは数年前にブランド改革プロジェクトを実施しました。
クリエイティブディレクションのポイントは、「捨てない勇気」と「新しい挑戦」の両立でした。具体的には、長年培った和菓子の品質や格式といったブランドの核はしっかり守りながら、商品ラインナップやデザイン面で新風を吹き込みました。若者にも手に取りやすいよう洋菓子のエッセンスを取り入れた商品や、パッケージデザインのスタイリッシュ化、パリをはじめとする海外店舗展開などを行ったのです。その際、老舗の伝統美や職人技といった「とらやらしさ」は損なわないよう細心の注意が払われました。
結果として、とらやは新規顧客層の開拓に成功し、「伝統=古い」ではなく「伝統=品質と信頼の象徴」というブランドイメージを強化しました。この事例から学べるのは、クリエイティブディレクションにおいてコアの維持とイノベーションのバランスを取る重要性です。企業ビジョンを踏まえた上で、表現方法を時代やターゲットに合わせて変えていけば、長寿ブランドでも新鮮な魅力を発信できる好例と言えるでしょう。
失敗事例:コスメブランド「SHIRO(シロ)」の急激なブランド刷新
一方、新興コスメブランドの「SHIRO」が直面したリブランディングの失敗は、クリエイティブディレクションのリスクを如実に物語っています。SHIROはナチュラル志向のコスメブランドとして20〜30代女性に人気を博し急成長していましたが、ブランド設立10周年のタイミングでロゴマークや商品パッケージを全面刷新しました。
従来のロゴは親しみやすい丸みのある小文字表記の「Shiro」でしたが、新ロゴはすべて大文字のシャープな「SHIRO」に変更。ブランドカラーも象徴的だった白から黒に近いネイビーへ転換されました。ミニマルでシンプルだったパッケージデザインも一新され、全体的にモダンでクールな印象へ舵を切ったのです。このクリエイティブ戦略の狙いは「海外展開を見据えた存在感強化」でしたが、既存顧客への配慮やコミュニケーションが不足していました。
リブランディング発表後、SNS上では「急にブランドの雰囲気が変わって戸惑う」「昔のほうが良かった」「SHIROらしさが消えた」といったネガティブな声が噴出しました。さらに悪手だったのは、同時期に人気商品の生産終了や限定化を行ったことです。愛用していた商品を突然失った顧客の不満も相まって炎上状態となり、最終的に運営会社は公式サイトで異例のお詫び文を掲載する事態にまで発展しました。後日、一部製品の継続販売が決定され、なんとか沈静化しましたが、ブランドに少なからずダメージが残りました。
SHIROのケースからの教訓は、ブランドチェンジのスピードと顧客コミュニケーションのバランスです。特に既存ファンがついているブランドの場合、クリエイティブ面の大幅変更は慎重に計画する必要があります。デザイン自体が嫌われたというより、「愛着を持っていた世界観を突然変えられた」という心理的反発が大きかったのです。クリエイティブディレクションにおいて、ユーザーがそのブランドに抱くイメージや想いを事前にリサーチし、変化のプロセスに巻き込む努力(ティザーによる予告やストーリーの発信)が欠かせません。リブランディングはゴールではなく、既存顧客との対話の始まりという意識が必要でしょう。
5. クリエイティブディレクション実務の進め方
以上を踏まえ、実際にクリエイティブディレクションを進める際のポイントをまとめます。ここでは、デザイナー・エージェンシーとの協業方法と、発注後の進行管理・品質チェックのポイントに焦点を当てます。
(1) デザイナー・エージェンシーとの協業方法
社内にデザイナーがいる場合も、外部のデザイン会社や広告代理店に依頼する場合も、協業の基本姿勢は共通です。パートナーとして対等に協力し合う関係を築くことが大切です。
- パートナー選定と契約: 外部に依頼する場合、実績や得意分野を確認し、自社の課題にマッチするクリエイティブパートナーを選びます。契約段階では納期・成果物範囲・報酬・著作権の扱いなどを明確に取り決めておきます。ここで不明瞭な点があると後々トラブルになり得るため、経営者としてもしっかり目を通しましょう。
- ビジョンの共有: 協業開始時には、経営者や事業責任者自らプロジェクトのビジョンや背景を語る機会を持つと効果的です。トップの言葉でプロジェクトの意義や成功像を伝えることで、クリエイティブチームのモチベーションが上がり、一体感が生まれます。社外パートナーであっても、自社チームの延長として迎え入れる意識が大切です。
- 専門性の尊重: 協業ではお互いの専門性を尊重しましょう。発注側はビジネス戦略や顧客理解に長け、制作側はデザイン思考や表現力に長けています。発注者が細かいデザイン手法に口出ししすぎるとクリエイターの力を発揮できませんし、逆にクリエイターがビジネス要件を無視すると成果につながりません。それぞれの役割を認識し、「何を実現したいか」は発注側が示し、「どう実現するか」はプロに任せるというメリハリが重要です。
また、エージェンシーなど複数の外部パートナーが関わる場合、自社内にクリエイティブディレクション担当者を置くことも検討しましょう。社内のブランド担当者やマーケティング部門のディレクターがハブとなり、各制作会社との間でブリーフやフィードバックを一元管理すると、メッセージの齟齬が減ります。小規模な企業では、経営者自身がその役割を担うケースもありますが、時間的リソースや専門知識の面から補佐役を立てるのも有効です。
(2) 発注後の進行管理と品質チェックのポイント
クリエイティブ制作が走り出したら、進捗と品質の管理を怠らないようにします。優れたディレクションは最後までしっかり「見る」ことでもあります。
- マイルストーン管理: 前述のデザインプロセスごとにマイルストーン(日程と成果物の目安)を設定し、各段階でレビュー日程を確保します。たとえば「○月○日までにラフ案提出→翌日フィードバック返し」「△月△日デザイン第一稿提出→チームレビュー実施」といった具合に事前にスケジュール化します。これにより締め切り意識が双方に生まれ、ダラダラと納期が延びるのを防ぎます。
- 進捗共有とフォロー: 制作過程で不明点や課題が出れば、適宜ミーティングやオンラインツールで共有します。クリエイター側から相談があった場合は迅速に対応し、判断待ちでプロジェクトが止まらないようにします。経営者や責任者は他業務で多忙かもしれませんが、クリエイティブプロジェクトも重要な経営施策の一部です。スケジュールに組み込んでフォローしましょう。
- 品質チェック: 最終段階では細部の品質チェックを綿密に行います。デザインそのものの出来栄えはもちろんですが、企業視点で見るべきポイントがあります。ブランド一貫性(色やフォント、口調が他の媒体とずれていないか)、メッセージの伝わり方(自社が意図した通りの印象を与えるか、誤解を生まないか)、ユーザビリティ(Webなら操作しづらい箇所がないか、印刷物なら可読性は十分か)などです。可能であれば身近な第三者に客観チェックしてもらうのも良いでしょう。社内の別チームや顧客に近いスタッフに見てもらうと、思わぬ盲点に気づくことがあります。
- 最終承認プロセス: 品質チェックを経て問題がなければ、正式に成果物を承認します。社印やサインが必要な場合もあるでしょう。ここで注意したいのは、承認フローをあらかじめ決めておくことです。経営層の確認が必要ならスケジュールに組み込み、土壇場で「社長チェックで差し戻し」などとならないようにします。一度承認したものを後から変更すると追加コストが発生する場合も多いため、承認前の最終確認は慎重に行いましょう。
進行管理と品質チェックを適切に行えば、たとえ中間段階で多少の方向修正があっても、最終的に満足度の高いアウトプットに仕上がるはずです。逆にこれらを軽視すると、「納品されたが期待と違う」「予算と時間を大幅にオーバーした」といった失敗につながります。経営者としてプロジェクトの指揮を執る以上、ゴールまで伴走する姿勢を持つことが大切です。
6. ヨコタナオヤの視点:クリエイティブディレクションで成功するための考え方
最後に、クリエイティブディレクターであるヨコタナオヤの視点から、クリエイティブディレクションを成功させるためのキーとなる考え方をお伝えします。企業のビジョンをデザインに落とし込み、「その企業らしさ」を可視化していくためのステップについてまとめます。
企業のビジョンをデザインに落とし込む
クリエイティブディレクションの本質は、企業のビジョンや戦略をクリエイティブの言語(ビジュアルと言葉)に翻訳することです。私(ヨコタナオヤ)は日頃から「ビジョンの言語化と視覚化」を意識してプロジェクトに取り組んでいます。経営理念や事業の目指す方向性が明確であれば、それをどうすれば人々に伝わる形にできるかを徹底的に考えます。
例えば、「革新的な精神で市場に挑む」というビジョンを掲げる企業があれば、その“革新”を感じさせるデザイン要素(斬新な色使いやモチーフ、他にないユーザー体験など)を盛り込みます。同時に、市場や顧客が求める価値との接点も探ります。単に奇抜にすれば良いわけではなく、ビジョンとユーザーインサイトの交点にある表現こそが最適解です。経営者の頭の中にある抽象的な考えを引き出し、それを具体的なコンセプトワードやビジュアルイメージに落とし込んでいく作業とも言えます。
ポイントは、経営層とクリエイティブ側でビジョンの解釈をすり合わせることです。経営者にとって当たり前の言葉でも、他者には伝わりにくいことがあります。「我が社の○○という価値観を表現するとどんな色や形だろう?」と問いかけ、一緒に連想しながらデザインの方向性を決めていきます。これにより、経営者にとってもしっくりくるデザインコンセプトが生まれ、トップダウンとボトムアップが融合したクリエイティブが実現できます。
企業の「らしさ」を可視化するステップ
企業の「らしさ」(その会社らしい個性や雰囲気)をデザインで表現するには、次のようなステップを踏むと効果的です。
STEP
ブランドの核を言語化する
まず、企業の理念や強み、文化などからキーワードを抽出します。3つ程度のキーワードやフレーズ(例:「挑戦心」「温かみ」「職人魂」など)に絞り込み、これがブランドの軸だと全員で認識します。
STEP
イメージの共有(ビジュアルリサーチ)
次に、そのキーワードから連想される色・形・質感・フォント・写真イメージを集めます。いわゆるムードボードを作成し、「らしさ」を視覚的に探っていきます。たとえば「温かみ」がキーワードなら、丸みを帯びたデザインや手書き風のテクスチャ、柔らかな配色などが候補に上がるかもしれません。チームで画像資料を見ながら意見交換することで、言葉だけではズレていた解釈も修正できます。
STEP
コンセプト化とデザイン指針の策定
イメージが固まってきたら、「○○社らしさ」を一文のコンセプトにまとめます(例:「○○社は革新的でありながら人の温もりを感じる存在」など)。そしてそれを実現するデザイン指針を作ります。「ロゴは曲線と直線を組み合わせて革新性と親しみやすさを両立する」「カラーはブランドカラーの青を基調に、サブに柔らかなベージュを使うことで冷たさを中和する」など、具体的なクリエイティブ要素のルールを定めます。
STEP
試作とテスト
コンセプトに沿っていくつか試作デザインやモックアップを作り、社内外の反応をテストします。「らしさ」が伝わるかを確認するため、身近な社員に「このデザインからどんな印象を受ける?」と聞いてみると良いでしょう。狙い通り「温かくて革新的」と感じてもらえれば合格ですし、もしギャップがあるならどこでズレが生じているか分析します。
STEP
展開と一貫性の維持
コンセプトに合格点が出たら、様々な媒体に展開します。ロゴ、Web、パンフレット、SNS広告、店舗デザインに至るまで、一連のクリエイティブに共通のコンセプトエッセンスを浸透させます。このフェーズではアートディレクションの要素が強くなりますが、クリエイティブディレクターは各制作物の統一感をチェックし、「らしさ」がブレていないか目を光らせます。ガイドラインに沿っているか、各担当者が理解して作業しているか定期的にレビューを行いましょう。
以上のステップを経ることで、企業の「らしさ」は具体的なデザイン言語として可視化されていきます。これは単なる見た目の問題ではなく、企業のアイデンティティを社内外に浸透させるブランディングそのものです。ヨコタナオヤ自身、多くのプロジェクトで感じているのは、「良いクリエイティブディレクションは社員一人ひとりが自社のブランドを再認識する機会にもなる」ということです。デザインを作る過程で自社の価値を再定義し共有することで、プロジェクト後も社内に統一感と誇りが残ります。
クリエイティブディレクションで成功するための心得として、「ビジョンからぶれないこと」「ユーザーと企業をつなぐ共感を生むこと」「チーム全体でブランドを体現すること」が挙げられます。経営者とクリエイティブディレクターが二人三脚でこれらを実践できれば、どんなデザインプロジェクトでもきっと良い成果に結びつくでしょう。
経営者や新規事業責任者にとって、クリエイティブディレクションは決して専門外のブラックボックスではなく、戦略遂行のための有力な手段です。本記事で紹介したポイントや事例、新しい視点をヒントに、ぜひ自社のクリエイティブ施策に生かしてみてください。優れたクリエイティブはビジネスを加速させ、ブランドに魂を吹き込みます。戦略と創造力を結集して、あなたの企業らしい世界観を世の中に発信していきましょう。
参考記事
あわせて読みたい
不評の「SHIRO」リブランディング。消費者は何に怒ったのか?
ブランドづくりの基礎知識・ポイントからさまざまな事例、そして実践的に学べるセミナー、相談会まで。幅広いメニューで社会にCBOを増やしていきます。
emmis|エミーズ編集室
クリエイティブ ディレクターって?|経営者さんにも知ってほしい
広告やブランディングの分野で活躍する「クリエイティブディレクター」って何? 役割とその重要性について解説します。
FICC
ディレクターが大手有名企業のクリエイティブを生み出す上で意識している7つのこと | inside FICC | FICC
FICCはデジタルエージェンシーとして、クライアントが抱えるさまざまなビジネス課題を解決するため、デジタルマーケティングに取り組んできました。そんなFICCのクライアン...
あわせて読みたい
クリエイティブ ブリーフの作成方法:無料のテンプレートとガイド - Dropbox
クリエイティブ ブリーフの作成にお悩みではありませんか?エキスパート ガイドで優れたクリエイティブ ブリーフの作成方法を学習したら、Dropbox Paper の無料テンプレー...
note(ノート)
よいコミュニケーションが、よいデザインに繋がる|ハグリ / カロア
デザインのフィードバックって、難しく無いですか? デザイナーをしている私でさえ、正直難しいのだからデザイナー職ではない方からするとなおさら難しいと思います。確固...