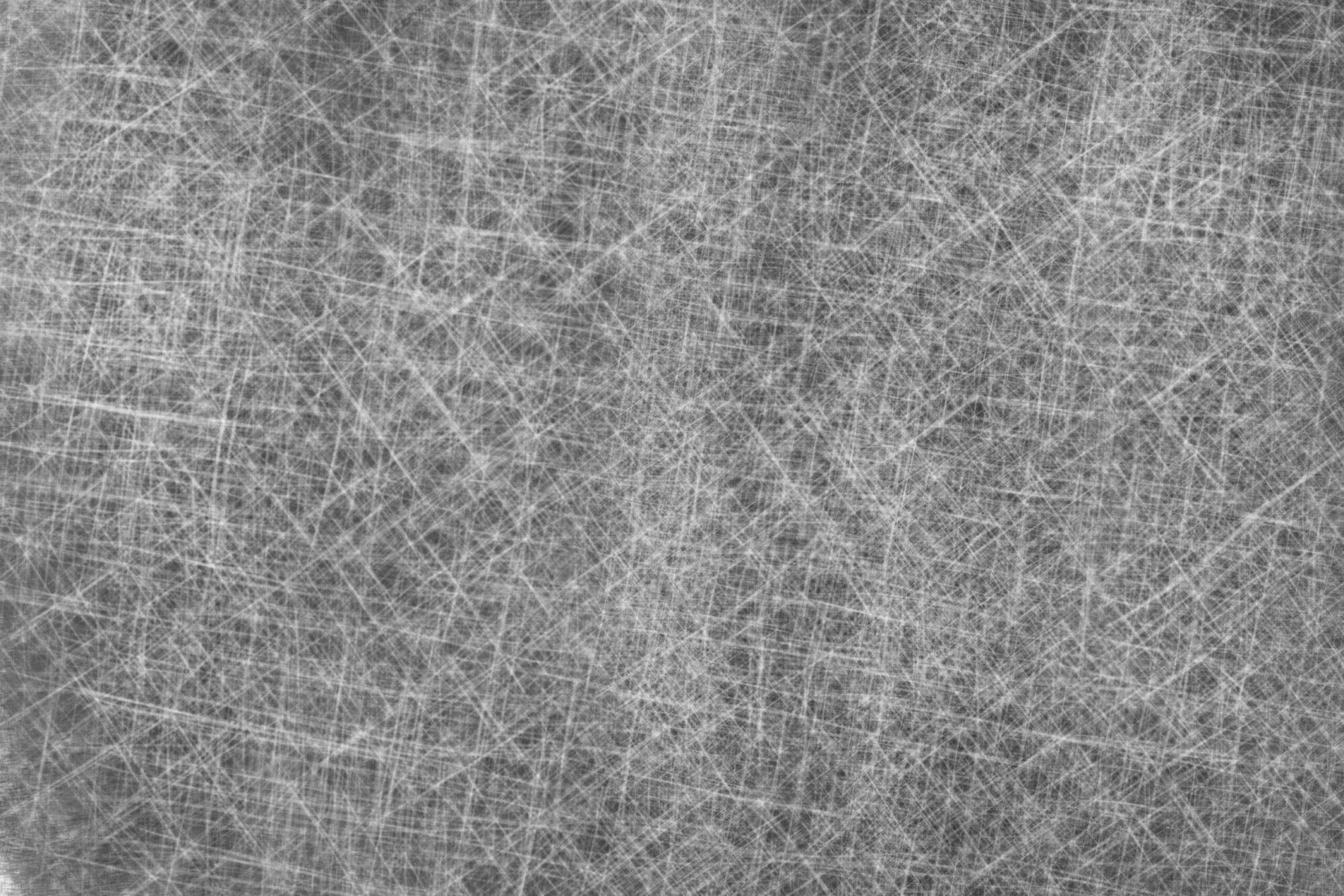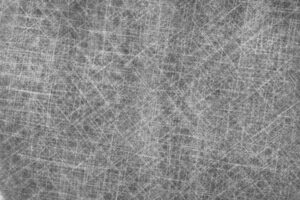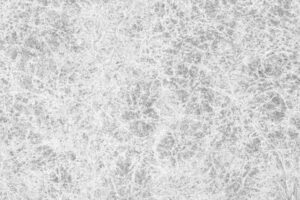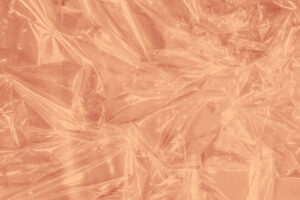ビジネスの世界で最近「ビジネスデザイン」という言葉を耳にする機会が増えてきました。急速な市場変化に対応し、新たな価値を創造するために注目される概念ですが、その意味や重要性がまだ十分浸透していない部分もあります。特にマーケティングや経営戦略と混同されやすく、「それって結局マーケティングのこと?」「経営戦略と何が違うの?」と思われるケースも少なくありません。
そこで本記事では、ビジネスデザインの定義を明確にしつつ、マーケティングや経営戦略との違いを整理してみます。新規事業開発や企業戦略に携わる方々にとって、ビジネスデザインの実務への活用ヒントも交えながら、その本質に迫っていきます。
目次
ビジネスデザインの定義
一般的な定義(学術的・実務的視点)
ビジネスデザインとは一言でいうと「ビジネスそのものを設計すること」です。従来の製品デザインやサービスデザインが個々のプロダクトやサービスの使い勝手・見た目を改善することに焦点があるのに対し、ビジネスデザインは企業全体のビジネスモデルや戦略、組織、オペレーションまで含めて総合的に見直すプロセスを指します
グッドパッチの定義によれば、「企業戦略とサービス/プロダクトを結びつけ、新たな価値創造を目指す手法」だとされています。つまり、企業の掲げる戦略(方向性)と具体的なプロダクトやサービス開発を橋渡しし、ユーザーにとって有用かつビジネス的にも価値のある新しい事業を創り上げていくアプローチです。
株式会社グッドパッチ
ビジネスデザインとは?重要性やプロセス、成功事例をわかりやすく解説|Goodpatch Blog グッドパッチブロ...
ビジネスデザインとは、企業戦略とサービス/プロダクトを結びつけ、新たな価値創造を目指す手法のことです。ユーザーインサイトに重きを置いた手法で、特に新規事業開発で...
ビジネスデザインの役割(企業や組織において何を担うのか)
ビジネスデザインの役割は、単に見た目の良い商品を作ることではなく、「どんな価値を提供し、それをどう持続可能なビジネスに仕立て上げるか」を構想することにあります。例えば顧客の抱える課題に着目し、それを解決するための新しいビジネスモデルを描く。その際にはプロダクト自体の機能やUXの設計はもちろん、収益モデル、顧客との関係性の構築方法、必要なリソース配置までをデザインします。
セゾンのビジネスコラムでは、ビジネスデザインを「顧客の課題を起点に、マーケティング施策(ブランディングや販促)や営業方法を検討し、新しいビジネスモデルを創出する行為」と説明しています。このようにビジネスデザインは、企業内の様々な機能(マーケティング・開発・営業・財務など)を横断しながら事業全体を設計する役割を担うわけです。
Credictionary
ビジネスデザインとは?定義や手法、事例などを徹底解説!
商品のコモディティ化やIT技術の発展に伴い、優れた製品を販売するだけではビジネスとして成立しなくなってきている。そのような変化を受けて、昨今は「良い製品を作る」だ...
マーケティングや経営戦略との違い
マーケティングとの違い
マーケティングとビジネスデザインは一見似た領域に思えますが、アプローチと視点が異なります。マーケティングは基本的に「顧客中心のアプローチ」であり、製品やサービスを売るために市場を分析し、ターゲット顧客のニーズを満たす戦略(4Pや販促施策など)を立案・実行する活動です。言い換えればマーケティングは「どう売るか」という運用面の設計にフォーカスしており、売上を上げる仕組みを作ることだと定義できます。
一方のビジネスデザインは「何を提供し、どうやって事業として成立させるか」というシステム全体の設計に踏み込みます。単なるプロモーション計画ではなく、提供価値そのものの発明やビジネスモデルの構築まで含めてデザインする点が大きな違いです。マーケティング活動もビジネスデザインの一部に含まれますが、それだけでは全体像を描けません。ビジネスデザインではマーケティングで得た顧客インサイトを活かしつつ、事業の構造(誰に何をどう提供し収益を得るか)をゼロから構想するところに重きがあります。「顧客視点」は両者とも重視しますが、ビジネスデザインは顧客視点+事業視点で、プロダクト開発から収益構造までデザインする点でマーケティングとは異なります。
経営戦略との違い
経営戦略(企業戦略)は企業が目標達成のために策定する全社的な計画です。リソース配分や成長分野の選定、競争優位の構築など「どのように勝つかを数字や計画で示す」のが経営戦略の役割と言えます。従来の経営戦略手法はKPIや効率性を重視し、過去の延長線上で計画を立てる傾向があります。
これに対しビジネスデザインは、「そもそも何を提供すれば市場で独自の価値を発揮できるか」「ユーザーにとって本当に望ましい体験は何か」という視点から事業やプロダクトそのものを設計します。極端に言えば、経営戦略が「山登りのルートを計画する」ことだとすれば、ビジネスデザインは「どの山に登るか、そのための新しい登山道具をどう作るか」を考えるような違いがあります。具体的には、経営戦略は中長期計画・予算策定・目標設定などマクロ視点の活動ですが、ビジネスデザインはデザイン思考を取り入れたユーザー体験の創出やビジネスモデルの再構築といったミクロとマクロを行き来する活動です。
現代のビジネス環境では変化が激しく、計画通りにいかないことも多いですが、ビジネスデザインのアプローチは顧客体験や未来の市場予測を中心に据えて柔軟にイノベーションを模索できる点で、従来型の経営戦略を補完・拡張する役割を果たします。つまり、経営戦略=方向性と目標の設定、ビジネスデザイン=価値創造の仕組みづくりと捉えると、その違いが明確になるでしょう。
どのような場面でビジネスデザインが有効か
以上の違いを踏まえると、ビジネスデザインが特に威力を発揮するのは「未知の領域に新規事業を立ち上げるとき」や「既存事業を抜本的に見直してイノベーションを起こしたいとき」です。マーケティング施策では捉えきれないような潜在的ニーズの発掘や、新しい収益モデルの構築が求められるケースで、ビジネスデザイン的な発想が有効になります。
また、社内に断片化しがちな戦略立案部門・商品開発部門・クリエイティブ部門を横断し、一体となってプロジェクトを進める必要がある場面でも、このアプローチが役立ちます。たとえば「ユーザー体験を核にしたサービス開発」や「デジタルトランスフォーメーションに伴う新規ビジネス創出」など、正解が一つでない課題に取り組む際に、ビジネスデザインの手法によってチーム全員がビジョンを共有し、素早くプロトタイピングと検証を回しながら進めることができるのです。
ビジネスデザインの活用方法
企業における実践例
ビジネスデザインは実際の企業活動で様々な形で活用されています。例えば、大手企業が新規事業開発部門を立ち上げ、スタートアップのようにユーザー中心のプロダクト開発を行うケースです。ある飲料メーカーでは、従来の延長線上にないデジタルサービスを生み出すためにビジネスデザインの専門チームを結成し、消費者の生活シーンを徹底的にリサーチした上でヘルスケア領域の新サービスを創出しました。また、サービスデザインの考え方とビジネス戦略を結びつけてブランド構築を行っている例もあります。
たとえば有名アパレル企業では、ブランドの世界観(ストーリー)から店舗体験、ECサイト、SNS発信に至るまで一貫した体験を設計することで、新ブランドを短期間で市場に定着させました。このように新規事業開発、サービスデザイン、ブランド構築などの場面で、ビジネスデザインの実践例が増えています。
ポイントは、どの場合も単なるアイデア止まりでなく実装(Implementation)まで見据えていることです。ビジネスデザインではプロトタイプ(試作品や試行)を通じて早期に市場からフィードバックを得て、それを事業設計に反映させながら前に進めていきます。「絵に描いた餅」で終わらせず実ビジネスに落とし込むところまで寄与するのが、ビジネスデザインの強みと言えるでしょう。
ビジネスデザインのフレームワーク
ビジネスデザインを進める際には、いくつか有用なフレームワークや手法があります。代表的なものの一つがデザインシンキング(デザイン思考)です。デザインシンキングは「人間中心設計」とも呼ばれ、ユーザーの潜在ニーズを共感を持って探り出し、発想を広げプロトタイピングとテストを繰り返す方法論で、ビジネスデザインの発想の土台になります。もう一つはリーンスタートアップの手法です。これはスタートアップ企業で生まれた手法ですが、新規事業の不確実性に対処するためにMVP(実用最小限の製品)を素早く市場に出して検証し、データに基づき迅速にサービスを改善していくアプローチです。
ビジネスデザインでは仮説検証型で事業を磨き込むためにリーンスタートアップ的なスピード感とサイクルを取り入れます。さらにシステムデザイン(システム思考)も有効です。これはビジネスを一つのシステム(顧客、提供価値、収益構造、パートナー、生態系などの要素が絡み合う全体)として捉え、部分最適ではなく全体最適を追求する考え方です。システム思考の視点を持つことで、ビジネスデザインは短期的なアイデアに留まらず、長期的に持続するモデルかどうか、周囲の環境変化に適応できる柔軟性があるか、といった点まで検討します。
こうしたフレームワークを組み合わせて使うことで、ビジネスデザインのプロセスは体系立てて進めやすくなります。例えば最初にデザインシンキングでユーザー調査→アイデア創出→試作品テストを行い、その後リーンスタートアップの考え方でビジネスモデルの仮説検証→ピボット(方針転換)を繰り返し、並行してシステム思考で事業全体の整合性チェックをする、という具合です。
重要なのは手法自体が目的ではなく、あくまで良いビジネスをデザインするための道具だということです。自社の状況に合わせて適切なフレームワークを活用し、チームの創造性と戦略思考を引き出すことが、ビジネスデザイン成功のポイントになります。
実務に落とし込む際のポイント
ビジネスデザインを実践する上で留意すべきポイントも整理しておきます。
まずクロスファンクショナルなチーム編成です。ビジネスデザインは多角的な視点が求められるため、マーケター、デザイナー、エンジニア、ビジネス企画担当など多様なメンバーが協働するのが理想です。部門横断のチームを作り、序盤から一緒にユーザー調査やアイデアワークショップを行うことで、サイロ化した組織では見えなかった洞察が得られます。
次にユーザーとの対話を恐れないこと。机上のプランニングではなく、ユーザーインタビューや観察を通じてリアルな声を拾い上げ、それを出発点にするのがビジネスデザインの鉄則です。プロトタイプをユーザーに使ってもらい、フィードバックを即座に事業仮説へ反映させるような俊敏さ(アジリティ)も重要です。
さらに、経営層のコミットメントも欠かせません。ビジネスデザインは時に従来の延長にはない大胆な施策や試行錯誤を伴うため、トップダウンで一定のリソース投下と意思決定の迅速化が図られないと、組織の中で失速してしまう恐れがあります。
最後に「失敗から学ぶ文化」を育むこともポイントです。新しいビジネスをデザインする以上、不確実性は避けられません。小さな失敗を早めに経験し、そこから学んで軌道修正することをポジティブに捉える文化・マインドセットをチーム内に醸成しておけば、ビジネスデザインのプロジェクトは継続的な学習プロセスとなり、成功確率がぐっと高まるはずです。
まとめと今後の展望
ビジネスデザインは単なる流行り言葉ではなく、これからの時代に求められる包括的なビジネスアプローチです。市場や技術の変化が激しい現代では、従来型の経営戦略やマーケティング手法だけでは新たな成長機会を捉えきれない場面が増えています。そうした中で、ビジネスデザインは「ユーザー体験」「事業モデル」「組織の動き」を統合的にデザインし直すことで、企業にイノベーションをもたらす鍵となります。今後さらにデータ活用やAIの進展によって顧客ニーズの多様化・細分化が進めば進むほど、デザインとビジネスの融合が重要になると考えられます。
実際、海外ではデザイン出身の経営者や、デザインコンサル会社が戦略策定から関わる例も増えてきています。日本においても「デザイン経営」などの言葉で、経営にデザインの発想を取り入れようという動きが活発です。ビジネスデザインはまさにその実践形と言えます。
企業や個人がビジネスデザインを活用するには、日頃からユーザー視点とビジネス視点の両方を磨くことが大切です。マーケティングや財務の知識と同時に、デザイン思考やプロトタイピングのスキルも学んでみる。あるいはプロジェクト単位でデザイナーやエンジニアと混成チームを組んで小さな実験的プロジェクトを回してみると、組織に新しい風を吹き込むきっかけになるでしょう。最初は小さな成功体験からでも構いません。その積み重ねが組織全体のビジネスデザイン力を高め、ひいては競争優位につながっていきます。
ビジネスデザインが今後さらに重要になる理由は明快で、それは「変化に対応し、未来を創造するため」だと考えられます。市場の未来予測をしながらもユーザーの声に耳を傾け、新しい事業の種を見つけ出し育てていくビジネスデザインのアプローチは、不確実性の高い時代の羅針盤となります。
マーケティング担当者や企業の戦略部門の方も、ぜひビジネスデザインの考え方を取り入れてみてください。自身の専門スキルにデザイン思考や事業設計の視点が加わることで、これまでにない発想や打ち手が見えてくるはずです。ビジネスデザインという新たな地図を手に入れて、ぜひ次のビジネスチャンスを描き出してみましょう。
参考文献・出典リスト