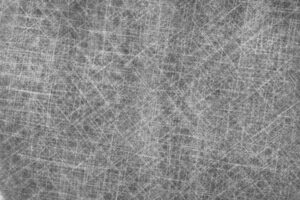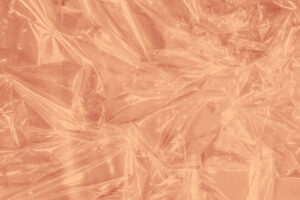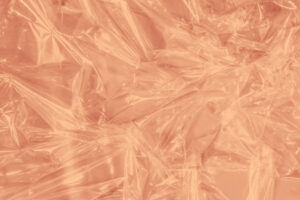はじめに
デザインを単なるビジュアルやブランディングの要素ではなく、経営資源として活用する「デザイン経営」について解説します。デザインシンキング(デザイン思考)やHCD(人間中心設計)といったフレームワークを適切に活用しながら、デザインを経営戦略に組み込む方法を具体的な事例とともに紹介します。
目次
デザイン経営とは何か
まず「デザイン経営」とは何かを整理します。デザイン経営とは、企業がデザインを経営の中心に据え、製品・サービス開発や組織運営においてデザインの考え方を活かす経営手法です。
経済産業省と特許庁が2018年に発表した「デザイン経営宣言」では、デザイン経営を「デザインを企業価値向上のための重要な経営資源として活用する経営」と定義しています。この宣言以降、日本でもデザインを経営戦略に取り入れる動きが加速し、政府レベルでデザイン経営の推進が表明されました。
つまり、デザインを人材・資本・技術と並ぶ経営資源として位置づけ、企業価値を高める手段とする考え方です。
デザインを経営資源とする意義も明らかです。デザインを単なる見た目の良さではなく、ユーザー視点でニーズを的確に捉える手段と捉えることで、他社にはないイノベーションを生み出し、ブランド力を向上させることができます。事業戦略段階からデザイン思考を取り入れることで、プロダクトやサービスの方向性を市場や顧客の求めるものに合致させやすくなります。その結果、顧客から選ばれる確率が高まり、競争優位性を築けるのです。事実、世界的に見てもデザイン主導の企業は業績面で高い成果を上げている例が多く、デザインを軽視できない時代になっています。
では企業の成長におけるデザインの役割とは具体的に何でしょうか。
デザイン経営を実践すると、企業内にユーザー中心の発想やクリエイティブな問題解決文化が根付きます。これにより市場の変化に柔軟に対応でき、新規事業やサービスの創出につながります。強いデザイン戦略を持つ企業はブランドイメージが一貫し、顧客ロイヤルティ(忠誠心)が高まります。
結果としてリピーターやファンを増やし、長期的な売上成長や企業価値向上に寄与します。デザインは単なる装飾ではなく、企業のビジョンを体現し価値提供を最適化する役割を果たすのです。
デザイン経営の実践方法
次に、デザイン経営をどのように実践していくか、その方法を見ていきましょう。
経営の上流段階からデザインの視点を取り入れること
デザインを経営戦略に組み込むプロセスとして重要なのは、経営の上流段階からデザインの視点を取り入れることです。
具体的には、新製品やサービスの企画段階でデザイナーやデザイン部門が参画し、ユーザー体験や市場ニーズを踏まえた意思決定を行います。ビジョン策定や戦略立案のフェーズで、デザインの方向性(例えばプロダクトデザインやブランドデザインの方針)を経営陣が共有し、事業計画とデザイン方針を整合させます。
また、組織構造の面でもデザイン部署と他部署が密接に協働できるよう、クロスファンクショナルなチームを編成することが効果的です。開発チームにデザイン担当を配置し、構想段階からユーザー視点で議論する仕組みを作ることで、デザイン経営が社内プロセスに組み込まれていきます。
デザイン経営を支えるフレームワーク
デザイン経営を支えるフレームワークとして、デザインシンキング(デザイン思考)とHCD(人間中心設計)があります。
- デザインシンキング
-
デザイナーの思考プロセスを活用した問題解決手法で、「共感→問題定義→発想→試作→テスト」というステップでユーザーの潜在ニーズに応えるイノベーティブなアイデアを生み出すアプローチ
- HCD
-
Human-Centered Designの略称で、ISO規格にも定義されたユーザー中心設計手法
HCDでは製品やサービス開発においてユーザーの利用状況や要求を深く理解し、試作品による評価を繰り返して最適な解決策を導くことを重視します。これらのフレームワークを活用することで、経営者やチームは主観や思い込みではなく実利用者の視点に立った判断を下しやすくなります。
結果として、開発の初期段階で方向修正を行ったり価値を検証したりできるため、無駄な投資を抑えつつユーザーに響く製品・サービスを生み出せます。
経営者の意思決定におけるデザインの活用
これもデザイン経営の重要なポイントです。トップマネジメントがデザインを単なる現場任せにせず、自ら意思決定に組み入れる姿勢が求められます。例えば、新規事業の立ち上げ時に経営者自らユーザーインタビューの結果やデザイナーが作成したプロトタイプを確認し、戦略の方向性を判断材料にするケースがあります。
また、経営方針を社内外に示すプレゼン資料や報告書の作成にもデザインの力を取り入れます。実際に、ある先進企業では経営方針書のドラフト作成段階からデザイナーが関与し、企業の思いやビジョンを一貫したストーリーとして伝えられるよう工夫しています。これにより、戦略メッセージに視覚的・感情的な訴求力が生まれ、社内の共感や社外ステークホルダーへの理解が深まります。さらに、経営層にデザイン出身者を登用する動きも広がっています。
Chief Design Officer(CDO)などの役職を設け、経営陣にデザイン責任者が加わることで、意思決定テーブルに常にデザインの観点がもたらされるようになります。経営トップがデザインの価値を理解し、意思決定プロセスに組み込むことが、真のデザイン経営実践には不可欠なのです。
デザイン経営の成功事例(国内企業)
実際にデザイン経営を取り入れて成功している国内企業の例を見てみましょう。ここでは、大企業から中小企業まで、デザインを経営の核として成果を上げている事例を紹介します。
無印良品:デザインを基盤にしたブランド戦略
無印良品(株式会社良品計画)は、デザイン経営の象徴的な成功例の一つです。無印良品はその名の通り「ノーブランド」をコンセプトに、シンプルで機能的なデザインの商品を展開してきました。「これでいい」という徹底したコンセプトのもと、余計な装飾や機能を削ぎ落としたデザイン哲学がブランドの核に据えられています。創業当初から一貫して「無駄をなくし、本質を追求する」という思想で商品開発とブランド構築が行われ、生活者に長く愛される強固なブランドイメージを築き上げました。
具体的な事例として、2014年に無印良品が発売したキッチン家電のラインナップがあります。著名なプロダクトデザイナーである深澤直人氏を迎えてデザイン監修を行い、既存の家電にはないミニマルで洗練されたデザインを実現しました。例えば冷蔵庫では、生活空間に調和するフラットな扉面とシンプルなハンドルを採用し、キッチンに置いても存在感が主張しすぎない「暮らしに溶け込むデザイン」を追求しました。これらの製品は「無印良品らしさ」が随所に感じられる仕上がりで、発売当時大きな話題となりブランド価値をさらに高めています。
また、無印良品は商品開発を支える仕組みとして「アドバイザリーボード」という社外の有識者・デザイナーで構成された委員会を設置し、ブランドコンセプトから逸脱しないよう定期的に助言を受ける体制を持っています。これにより、事業領域が多角化(家具、住宅、ホテル、食品など)しても一貫したブランド体験を提供し続けることに成功しています。無印良品のケースからは、明確なデザインコンセプトの設定と組織的なデザインガバナンスによってブランド戦略を強化し、経営成果に結びつけていることが分かります。
ソニー:デザインとテクノロジーの融合によるイノベーション
ソニーは、日本企業の中でも早くからデザインを経営の核に据えてきた企業です。同社は「Create New Standard(新しい基準を創造する)」という哲学を掲げ、1950年代以降次々と革新的な製品を世に送り出しました。特に1961年にソニーの社内にデザイン専門部署が設立されて以来、デザイン経営を先駆けて実践してきた歴史があります。トランジスタラジオやウォークマン、トリニトロンテレビなど、ソニーが生み出した数々のヒット商品は技術力と優れたデザインの融合によって市場に新たな価値を提供しました。
ソニーのデザイン経営がユニークなのは、製品デザインやブランディングのみならず、経営の意思疎通や物語づくりにもデザインを活用している点です。たとえば、ソニーでは経営陣が中長期ビジョンや経営方針を社内外に示す際、その資料作成に初期段階からデザイナーが関与します。経営メッセージ自体を一つの「デザインされた体験」と捉え、受け手にソニーの目指す未来像が直感的に伝わるよう工夫しているのです。このように企業のストーリーをデザインする取り組みは、ブランドへの共感を高め社員のモチベーションや社外からの評価向上にも寄与しています。
さらにソニーは、自社内で培ったデザイン経営の知見を外部にも提供し始めています。2020年には子会社としてソニーデザインコンサルティングを設立し、他企業に向けたデザイン活用の支援サービスを開始しました。これは、ソニーが長年実践してきたデザインと経営の融合ノウハウが一つの付加価値サービスとなりうることを示しています。ソニーの事例から学べるのは、デザインを単なる製品価値ではなく企業活動全体の価値創造プロセスに組み込むことで、持続的なイノベーションとブランド強化を実現できるという点です。半世紀以上にわたりデザインを経営の原動力としてきたソニーは、日本におけるデザイン経営の草分け的存在と言えるでしょう。
中小企業のデザイン経営実践例
デザイン経営は大企業だけのものではなく、中小企業こそ大きな効果を発揮する場合があります。
その代表的な例として中川政七商店の取り組みを紹介します。中川政七商店は1716年創業の老舗企業(奈良の麻織物商)ですが、2000年代に入り現経営陣が大胆な経営改革を行いました。同社13代目の中川政七氏(現在は会長)は、「もの作りからブランド作りへ」の転換を掲げ、従来卸売が中心だったビジネスモデルを直営小売中心に見直しました。
単に良い製品を作って卸すだけでは自社のブランド価値は高まらないと判断し、自ら消費者と接点を持つ直営店を拡大するとともに、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを掲げたのです。この明確なビジョンのもと、企業文化としてデザイン(ブランディング)を浸透させ、社員一人ひとりがビジョン実現に向けて創意工夫する組織作りを進めました。
中川政七商店はまた、自社だけでなく業界全体の活性化を目指し、培ったノウハウを活かしたコンサルティング事業も展開しました。例えば、同社が初めて手掛けたコンサルティング案件として有名なのが、長崎県の波佐見焼の卸問屋「マルヒロ」の再生支援です。マルヒロと協力して生活者に訴求する新ブランド「HASAMI」を立ち上げたところ、シンプルでモダンなデザインの波佐見焼シリーズが大ヒットしました。
その結果、マルヒロはわずか10年で粗利500万円から売上3億円規模の企業に成長し、地方の伝統産業に新風を吹き込む成功事例となりました。これはデザイン経営の力が中小企業でも如実に成果を上げたケースと言えるでしょう。
このように中川政七商店の事例から学べるのは、中小企業であっても明確なビジョンとデザイン戦略を据えることでブランド価値を飛躍的に高められるという点です。同社は長年社是すら存在しなかった組織に初めてビジョンを定着させ、それを軸に商品開発から販売チャネル、さらには業界支援まで一貫したストーリーを描きました。
結果として自社の成長のみならず、関わる他社の成長も促すという好循環を生み出しています。中小企業だからこそ経営資源が限られますが、デザインの力を戦略的に使うことで独自のポジションを築き、競争力を高めることが可能だと言えるでしょう。
デザイン経営の導入ステップ
自社にデザイン経営を導入するには、段階的な取り組みと組織風土の醸成が必要です。以下に、企業がデザイン経営を取り入れる際の基本的なステップを示します。
STEP
企業文化としてのデザインの浸透
まずは社内の意識改革です。デザインの重要性を経営トップ自らが発信し、社是やビジョンにデザイン志向を組み込みます。社員に対してもデザインの価値や効果を啓蒙し、部門を越えてデザインについて議論しやすい文化を醸成します。例えば、定期的なワークショップや勉強会を開いてデザイン思考を体験してもらう、成功事例を社内共有する、といった施策が有効です。
全員が「デザインは自分たちの仕事にも関係がある」というマインドセットを持つことで、ボトムアップでのアイデア提案や改善活動が活発になります。
STEP
組織内でのデザイン人材の育成
次に、人材面の強化です。専門のデザイナーを採用・配置するだけでなく、既存社員のデザインリテラシーを高める取り組みを行います。具体的には、デザイン思考やHCDの研修を提供したり、有志のデザインプロジェクトを立ち上げたりすることが考えられます。社内にHCD専門家などの資格取得を奨励し、ユーザーリサーチやUXデザインのスキルを持つ人材を増やすのも良いでしょう。
また、「デザインの出来る人」だけに依存しないよう、職種横断的なチーム編成でプロジェクトを進めることで、メンバー全員がデザインプロセスに触れる機会を作ります。重要なのは、デザイン人材を組織内で継続的に育成し、彼らが活躍できる環境(評価制度やキャリアパスの整備)を用意することです。
STEP
デザインとビジネスの連携を強化する方法
最後に、実践フェーズとしてデザインとビジネスの連携を具体化します。プロジェクト運営において、デザイナーと経営層・ビジネスサイドが密にコミュニケーションを取り、一緒に意思決定する場を設けます。例えば、新商品開発ではマーケティング担当・エンジニア・デザイナーが初期段階からチームを組み、ユーザー調査結果やデザインコンセプトを共有しながら仕様を決めていきます。
また、デザインレビューのプロセスを正式に設け、経営層が節目ごとにプロトタイプやデザイン案をレビューしてフィードバックするようにします。これにより「作っては経営会議で否決される」といった無駄を防ぎ、共通認識のもとで開発が進行します。さらに、デザイン投資の効果をビジネス指標(売上、NPS顧客満足度、ブランド指標など)と結びつけて測定・検証する仕組みを導入することも大切です。定量効果を追うことで社内でのデザインに対する信頼感が高まり、ビジネス目標とデザイン活動が一体となって推進されるようになります。
以上のステップを踏むことで、企業は徐々にデザイン経営へシフトしていくことができます。ポイントは、一朝一夕に全てを変えるのではなく、トップダウンの方針とボトムアップの実践を組み合わせて少しずつ組織を変革することです。デザイン経営は導入してすぐ劇的な成果が出るものではありませんが、腰を据えて取り組むことで長期的に企業に独自の強みと競争力をもたらすでしょう。
ヨコタナオヤの視点:デザイン経営の実践経験と考察
最後に、筆者であるヨコタナオヤの視点から、デザイン経営を実践してきた経験と考察をお話しします。私はこれまでいくつかの企業プロジェクトでデザイン経営の考え方を取り入れ、事業成長に貢献するデザイン戦略の策定に関わってきました。
具体例の一つとして、中小メーカーの新規サービス開発プロジェクトを担当した際の経験があります。プロジェクト開始当初、その企業には明確なブランドコンセプトがなく、開発現場と経営陣との間で製品の方向性にズレが生じていました。そこで私は、デザインシンキングの手法を用いて経営陣と開発チームの合同ワークショップを実施しました。ユーザーへの共感マップ作りやプロトタイプ検討を皆で行うことで、「誰のどんな課題を解決するプロダクトなのか」をチーム全体で再定義したのです。
このプロセスを経て、経営者も含めプロジェクトメンバー全員が目指すべきユーザー体験を共有できました。その後の開発ではデザインコンセプトが意思決定の軸となり、当初ぼんやりしていた製品アイデアが磨かれていきました。結果として、リリースしたサービスは市場で好評を博し、新規事業ながら早期に黒字化を達成する成功につながりました。この経験から、デザイン経営のアプローチが組織のベクトル合わせに極めて有効であることを実感しました。
また別のケースでは、既存事業のブランド刷新プロジェクトでデザイン経営を実践しました。老舗のBtoB企業で、自社プロダクトの販路拡大に伸び悩んでいたところに参画したのですが、まず着手したのはブランドの再定義とビジュアル・UXの一新です。経営陣にヒアリングして感じたのは、自社の強みや価値をうまく顧客に伝えられていないという課題でした。そこで、私は外部のデザイナーやエンジニアとも協働しながら、企業のストーリーを可視化するブランディングを提案・実行しました。具体的には、新しいロゴ・パッケージデザイン、使いやすさを追求したUI設計、そしてそれらに一貫性を持たせるブランドガイドラインの策定です。
さらに、営業ツールやウェブサイトも統一したトーン&マナーで刷新し、顧客が企業の世界観を体験できるようにしました。当初は「本当にデザインを変えるだけで売上が上がるのか」という懐疑的な声も社内にありましたが、刷新後は徐々に効果が現れました。展示会での反応が明らかに向上し、新規顧客から「製品のデザインやパンフレットがおしゃれで印象的だった」という声が寄せられたのです。結果として既存顧客との取引額も増加し、リブランディングから1年で前年対比120%の売上成長を達成できました。このプロジェクトを通じて痛感したのは、デザイン戦略が企業の提供価値を再定義し、顧客との新たな接点を創出する強力なドライバーになりうるということです。
もちろん、デザイン経営を取り入れる過程では課題もありました。最大の壁は社内の意識改革です。伝統的な企業ほど「デザインは後工程の飾り」といった固定観念が根強く、初めはデザイン部門と経営層との意思疎通がうまくいかない場面もありました。この課題に対して私が意識した解決策は、小さな成功体験を積み重ねて理解を得ることでした。
例えば、最初は大規模な改革ではなく、既存製品のパッケージデザイン改良やWebサイトのユーザビリティ改善など、比較的短期間で効果が見えやすい施策から着手しました。改善後に売上や問い合わせ件数など具体的な数字が動いた段階で、その成果を社内で共有し「デザインの力」であることを示しました。そうすることで少しずつ社内の見方が変わり、「もっと他の領域でもデザインの力を借りてみよう」という前向きな意見が増えていきました。
もう一つの課題はデザインのROI(投資対効果)の捉えにくさです。デザイン施策は短期的な数値効果として現れにくい場合も多いため、費用対効果を疑問視されがちです。この点については、KPIを工夫して設定するようにしました。売上やアクセス数だけでなく、ユーザーテストでの満足度指標やSNSでのエンゲージメントなど、デザインの効果を測る別軸の指標をあらかじめ定めモニタリングしました。定量データと言葉にならない定性フィードバックの両方を集めることで、「デザインに投資する意味」を経営陣にも納得してもらうよう努めました。
総じて、私の経験からデザイン経営を成功させるカギは「ビジョンの共有」「継続的な対話」「検証と改善のサイクル」だと感じています。デザインと経営を結びつけるには、経営者と現場が共通のビジョンを持ち、お互いの言語で語り合う土壌が必要です。そして、小さくても確実な成果を積み上げながら、PDCAを回してデザイン施策を磨いていくことが大切です。
デザイン経営は単なる流行りの経営手法ではなく、自社の存在意義や顧客との関係性を見つめ直すための鏡のようなものだと思います。デザインの力で企業の可能性を引き出し、ステークホルダーすべてに価値を届ける――そんな経営を目指して、これからも試行錯誤を続けていきたいと考えています。
参考文献