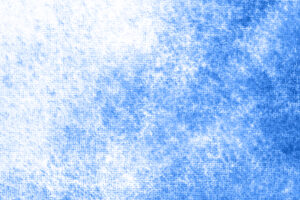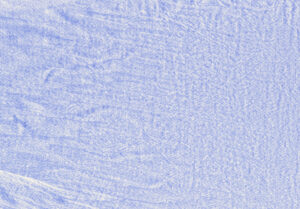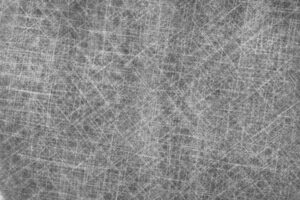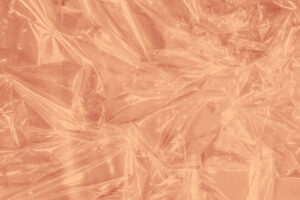はじめに
現代の経営環境では、「ビジョン設計」を出発点とした事業開発がますます重要になっています。単に目先の利益やマーケットトレンドに流されるのではなく、自社の存在意義(パーパス)や将来像といったビジョンに根ざした戦略こそが、長期的な企業価値を生み出す源泉となるからです。ビジョン主導の経営(パーパス・ドリブン経営)は、組織内外のステークホルダーを結束させ、持続的なブランド戦略とイノベーションを可能にします。
本記事では、ビジョンを軸に事業をデザインする重要性について、実践的なフレームワーク(パーパス・ドリブン経営、デザイン思考、ナラティブ・ブランディングなど)を用いて解説します。ビジョン定義から組織文化設計、そして事業設計へのプロセスを順に追いながら、国内企業の具体的な成功事例や、筆者(ヨコタナオヤ)の経験に基づく手法も交え、企業が実践できるポイントを紹介します。
目次
ビジョン定義:パーパスを基点に据える経営
まず取り組むべきは、自社のビジョン(パーパス)定義です。
パーパス・ドリブン経営とは何か?
パーパス・ドリブン経営とは「パーパス(企業の社会的存在意義)を起点とした課題解決の考え方」であり、企業が存在する理由や果たすべき使命を明確化し、それを簡潔な言葉で表現することから始まります。明文化されたパーパス(存在意義)は、単なるスローガンではなく、経営判断や事業開発の根幹を成す羅針盤となります。
ビジョンを定義する際には、社会課題や顧客の根源的なニーズに目を向け、自社の強みを活かしてどのような価値を提供できるかを検討します。
【事例】LIFULLの「しなきゃ、なんてない。」に見るパーパス・ブランディング
例えば、住宅・生活サービスを手掛ける株式会社LIFULLでは、企業理念「あらゆるLIFEを、FULLに。」をもとにブランドパーパスを策定し、「まだ手付かずの問題でも、視点を変える発想で豊かさに変えていく」「誰もが自分らしい人生を実現できる社会へ」というビジョンを掲げました。このパーパスを起点に生まれたコンセプトが「しなきゃ、なんてない。」です。
従来の既成概念に縛られず、自分らしい選択肢を追求できるという物語性を持たせることで、提供するサービスの方向性が定まり、ユーザーにも企業姿勢が伝わりやすくなっています。
これはナラティブ・ブランディングの手法をビジョン策定段階から活用した例と言えます。ビジョンを単なる理念としてではなく、“物語”として社内外に語れる形にすることで、共感を生み、後の戦略展開に厚みを持たせることができます。
ビジョンを明確化するためのステップ
私自身も企業のコンセプトメイキングに携わる際は、まず経営者やチームと対話しながら「何のためにこの事業を行うのか」「社会にどんな変化を起こしたいのか」を言語化する作業から始めます。
ビジョン設計の段階で時間をかけてパーパスを磨き上げることが、以降のブランドデザインやプロダクト開発の質を大きく左右するからです。明確なビジョンが定まれば、戦略上の意思決定に一貫性が生まれ、多少環境が変化してもブレない軸ができます。反対にビジョン不在のままでは、目先の施策が場当たり的になり、長期的なブランド価値を損ねかねません。
例えば筆者が関与したプロジェクトでも、当初うまくいかなかった新規サービスが、改めて「このサービスが実現したい未来像は何か」を定義し直した途端、機能やデザインの方向性が明確になり事業が軌道に乗ったケースがありました。
ビジョン定義は地味なプロセスに思えるかもしれませんが、事業デザインの出発点として最も重要なステップなのです。
ビジョン定義に活用できるフレームワーク
- パーパス・ドリブン経営
前述のように、自社の存在意義(パーパス)を明確化し、それを経営の軸に据える手法です。ステークホルダーとの対話やワークショップを通じて、「自社が社会に提供できる独自の価値は何か」を掘り下げ、短い言葉で表現します。ここではサイモン・シネックの「Whyから始めよ」のゴールデンサークル(Why/How/What)を参考に、自社の“Why”を定義するのも有効でしょう。
- ナラティブ手法によるビジョン言語化
ビジョンを物語として語るために、社史や創業者の想い、顧客のストーリーなどを織り交ぜてビジョンステートメントを作成します。例えば「○○な世界を創る」といった未来像を描き、その実現のために生まれたエピソードを付加することで、単なる理念以上の説得力を持たせます。社内向けにはそのビジョンにまつわる体験談を共有したり、映像やスローガンを作成して浸透を図ることも効果的です。
組織・文化設計:ビジョンを組織に浸透させる
定義したビジョンは、組織の隅々にまで浸透させ、日々の行動や意思決定に反映されてこそ意味を持ちます。組織・文化設計のフェーズでは、ビジョンを支える企業文化・風土や仕組みをデザインしていきます。
パーパス・ドリブン経営を実践するには、社員一人ひとりがビジョンに共感し、自分事として捉えることが不可欠です。そのために有効なのが、ビジョンに基づいたバリュー(価値観)や行動指針の策定です。
例えば、美容業界向け製品を展開するタカラベルモント株式会社では、パーパス「美しい人生を、かなえよう。」を掲げ、このビジョンを体現するための5つの行動指針「タカラベルモント ウェイ」を定めています。
具体的には次のような内容です。
- 美と健康の本質・可能性の追求 – 自社の強みである美容・健康分野で本質的価値を探究し続ける
- 「らしさ」を大切に – 個々人や地域の多様性・独自性(らしさ)を尊重する
- 変化や失敗を恐れずチャレンジ – 革新を起こすために現状に安住せず挑戦を続ける
- オープンマインドと愛情を持って仕事に向き合い続ける – 開かれた姿勢と顧客・同僚への思いやりを持って業務に取り組む
- 知識・技術を惜しみなく提供して顧客の課題を解決し共に成長する – 専門性を共有し顧客とともに課題解決・成長を実現する
このように明文化された行動指針は、ビジョンを日常の意思決定レベルにまで落とし込む役割を果たします。社員は自分の行動をこれらの指針に照らし合わせることで、ビジョンに沿った判断がしやすくなります。
タカラベルモントの例では、社員が新製品開発や顧客対応を行う際にも、「美と健康の本質を追求できているか」「失敗を恐れず挑戦しているか」といった問いを立てやすくなり、結果的にビジョン実現へと組織が一丸となって進む文化が醸成されています。パーパスで示した在り方を現場で実行するために、行動指針を定め運用することが重要だと同社も強調しています。
また、組織文化にビジョンを浸透させる手法としてはインナーブランディング(社内ブランディング)活動が有効です。具体的には、ビジョンやバリューを社内報・ポスター・朝礼などで繰り返し発信したり、ビジョン体現者を称える表彰制度を設けたり、採用時にミッションへの共感を重視するなどの施策が考えられます。
筆者の経験上、単に経営理念集を配布するだけでは文化は変わりません。ワークショップ形式で全社員が自社のビジョンについて議論し、自分の言葉で語れるようにする、幹部自らビジョンに基づいた意思決定を示して模範を見せる、といった双方向の取り組みが欠かせないと感じます。実際、ある企業では経営トップが毎月ビジョンに絡めたメッセージを発信し続けた結果、数年で社員の意識調査における企業理念の理解度・共感度が飛躍的に向上した例もありました。
ビジョンを組織文化に定着させるには、経営層から現場までの継続的なコミュニケーションと仕組みづくりが重要なのです。
組織・文化設計に活用できるフレームワーク
- バリュー策定と評価制度連動
ビジョンに沿った具体的な行動規範(バリュー)を3〜5個程度設定し、人事評価や表彰制度に組み込む手法です。これにより社員の行動がビジョンと一致しやすくなります。例)「チャレンジ精神」をバリューに掲げる企業で、新提案数や改善提案を評価項目に入れる等。
- インナーブランディング施策
社員がビジョンを共有・体現できるようにする社内広報・研修施策です。たとえば、ビジョンに関するストーリー動画の社内上映、ビジョンに基づく社員ワークショップ開催、バリュー体現エピソードを社内SNSで募集・共有する、といった具体策があります。
- リーダーシップ・ナラティブ
経営トップ自らがビジョンにまつわる物語を語り、社員にビジョン達成への意欲を喚起する手法です。創業の想い、顧客の感動事例、将来ビジョンが実現した社会の姿などを織り交ぜて語ることで、頭ではなく心で理解できる文化を作ります。
事業設計:ビジョンを事業戦略へ落とし込む
ビジョンが定まり組織に行き渡ったら、いよいよそれを具体的な事業設計・戦略に落とし込んでいきます。ここではビジョンを軸に、新規事業や製品・サービスをデザインし、また市場におけるブランド戦略を構築する段階です。
ビジョンで掲げた理想や目的を、実際の価値提供(プロダクトやサービス)と顧客との接点(ブランド体験)に反映させることが求められます。
ユーザー視点の事業開発(デザイン思考)
共感→問題定義→創造→プロトタイピング→テストの流れ
ビジョンを具現化した事業を生み出すには、ユーザー課題に深く向き合うデザイン思考(Design Thinking)のアプローチが有効です。デザイン思考は人間中心の問題解決手法で、「共感→問題定義→創造→プロトタイピング→テスト」のプロセスを経てイノベーティブな解決策を導きます。
自社のパーパスに沿った事業アイデアであっても、それがユーザーに受け入れられるものでなくては持続的なビジネスにはなりません。そこでデザイン思考を取り入れ、ビジョンに共感するユーザーは何を求めているのか、どんな体験が提供できるのかを探っていきます。
実際、デザイン思考を経営に導入した企業の73.8%が、導入後に「売上と利益が増加・向上した」と回答しています。ユーザー視点で発想し、新しい価値を創造することが競争力に直結するためです。
あわせて読みたい
ビジョンイズム | 株式会社ビジョン
株式会社ビジョンのコーポレートサイトです。海外渡航される方に快適なモバイルインターネット環境を提供する『グローバルWiFi』をはじめ、さまざまな情報通信サービスを提...
【事例】任天堂Wiiの開発プロセスとビジョンの体現
例えば任天堂株式会社のゲーム機「Wii」は、日本企業におけるデザイン思考の成功事例としてよく知られています。発売当時、テレビゲームが家族のコミュニケーション断絶を招いているという社会課題に着目し、「家族で楽しめるゲーム」というコンセプトを据えて開発が進められました。誰にでも使いやすい直感的なリモコン型コントローラーの設計や、リビングに置いても邪魔にならない本体デザインなど、何度もユーザーテストを重ねたプロトタイプから生まれたWiiは、結果的に世界的な大ヒットを記録し、「ゲーム=子供のもの」という常識を覆しました。このようにビジョンに沿ったユーザー体験を追求することで、競合と差別化された革新的な事業を生み出すことが可能になります。
【事例】オムロンのゼロイベント構想とウェアラブル血圧計
また、医療機器分野のオムロンヘルスケア株式会社は「高血圧が引き起こす脳・心血管疾患ゼロ(ゼロイベント)の実現」というビジョンを掲げ、ユーザーの日常に溶け込む血圧管理ソリューションを次々と開発しています。同社は1973年に家庭用電子血圧計を発売して以降、「家庭で血圧を測る」という新たな文化を根付かせることに成功し、全世界で累計1.5億台以上を販売しました。
さらに2019年には、日中いつでも装着して血圧を測定できる腕時計型ウェアラブル血圧計『HeartGuide』を発売しています。この製品開発では「血圧計を身につけていると周囲に思われたくない」というユーザーの声に徹底的に寄り添い、見た目は一見スマートウォッチのようにデザインされました。その結果、従来は高血圧症患者が主なユーザーだった血圧計を、「健康管理意識の高い一般の人々」までターゲットを広げることに成功し、新たな市場ニーズを開拓しています。
この事例は、ビジョン「ゼロイベント」を起点にユーザー共感を重視したデザイン思考を適用することで、事業戦略上のイノベーションと市場拡大を実現した好例と言えるでしょう。
筆者自身、事業コンセプト策定からデザイン・開発まで携わる際には、必ずユーザーの声を直接聞く機会を設けています。ビジョンに共感してくれるであろうターゲット顧客像を描き、その人々の課題や望む未来を深掘りすることで、ビジョンが単なる理想論でなく現実のプロダクトやサービスに落とし込まれていきます。「ビジョンによって定まった北極星」と「ユーザーから引き出したインサイト(洞察)」の両方が交わる地点こそが、ヒットする事業アイデアの着地点だと感じています。
デザイン思考のワークショップなどを通じてチーム全員がユーザー目線とビジョン目線を行き来しながら発想することで、ブレないかつ需要にマッチしたサービス設計が可能になります。
ブランド戦略:ナラティブ・ブランディングによる価値の可視化
ビジョンを体現する事業を構築した後は、その価値を市場に伝え、顧客や社会との関係性をデザインするブランド戦略が重要です。ここでも起点となるのはビジョンであり、単に機能や価格を訴求するのではなく、ビジョンに根ざしたナラティブ・ブランディング(物語戦略)によってブランドを築くことが効果的です。
ナラティブ・ブランディングとは?
ナラティブ・ブランディングとは、企業や商品のメッセージを一貫した“物語”として構築し、生活者をその物語の主人公に巻き込んでいくマーケティング手法です。消費者は商品そのものではなく、その背後にあるストーリーや共感できる世界観に心を動かされるものです。したがって、自社のビジョンに基づく物語を描き、それをブランドコミュニケーション全体で発信することで、顧客の共感とエンゲージメントを高めることができます。
【事例】味の素冷凍食品の「手間抜き」ナラティブ戦略
たとえば、味の素冷凍食品株式会社は「冷凍食品=手抜き」という世間のネガティブな固定観念を転換するナラティブ戦略を展開しました。同社はビジョンとして「食を通じて人々のゆとりや健康を支える」という志向を持ち、冷凍餃子に関して「手抜きではなく、手間抜き」という新たな物語を打ち出したのです。
公開されたWeb動画では、冷凍餃子ができるまでに工場で144もの工程を経ていることを紹介し、「最後の仕上げはあなたのフライパンで。」というメッセージで締めくくられています。つまり、家庭で調理する“ひと手間”以外の大部分はメーカーである味の素が引き受けている、一緒に料理を作っているのだという物語を共有したのです。
このキャンペーンによって、消費者は「時短で美味しい料理を提供できる自分」にポジティブな価値を見出し、商品に対する見方が「手抜きの妥協」から「大切な時間を生み出すソリューション」へと変容しました。これはビジョンに紐づくブランド・ナラティブが消費者の認識と行動を変えた典型例と言えるでしょう。
【事例】ユニ・チャーム「#NoBagForMe」プロジェクト
他にも、ユニ・チャーム株式会社が生理用品ブランド「ソフィ」において「#NoBagForMe」プロジェクトを通じ、生理をタブー視せず誰もが気兼ねなく語れる社会を目指す物語を発信した例や、スタートアップ企業COTENが「世界史データベースを一緒に作る仲間(COTEN CREW)」という参加型の物語で共感者から支援を募った例など、ナラティブを活用した国内企業のブランド戦略は増えています。
共通するのは、自社のパーパス(存在意義)を出発点に具体的で共感性の高いストーリーを描き、それを商品・サービスやプロモーション施策に一貫して反映させている点です。物語に共感したステークホルダーはファンや支持者となり、単なる顧客以上のロイヤルティを示してくれるようになります。
顧客との関係構築におけるストーリーテリングの力
筆者がブランドプロデュースを行う際も、まずその企業やプロダクトが持つ背景や想いを深くヒアリングし、「どんな物語ならターゲットの心に響くか」を考え抜きます。デザイン(視覚要素)やコピーライティングも、この物語を表現するための手段です。たとえ予算をかけた広告を打てなくとも、SNSで共感を呼ぶストーリーが語れれば口コミでブランドは広がりますし、逆に物語なきブランドは大量露出しても消費者の記憶に残りません。
ビジョンを軸にしたナラティブ・ブランディングによって、企業は商品の機能的価値以上の文化的・感情的価値を提供でき、それが競合との差別化と長期的なブランド資産形成につながっていくのです。
まとめ:ビジョンから戦略への一貫性が成功を導く
ビジョンを起点に「ビジョン定義 → 組織・文化設計 → 事業設計」というプロセスで事業をデザインしていくことの重要性と手法について述べてきました。最後にポイントを整理します。
- ビジョン(パーパス)を明確化する
自社の存在意義や目指す未来像を言語化し、経営の土台とする。社会的視点を持ったビジョンは企業の指針であり、あらゆる戦略の判断基準となる。
- 例:LIFULLの「しなきゃ、なんてない。」のように、理念を端的で共感しやすい言葉に落とし込む。
- ビジョンを組織文化に浸透させる
ビジョンに基づく価値観・行動指針を定め、人事制度や日常業務に組み込むことで、社員一人ひとりがビジョンを体現できる環境を整える。
- 例:タカラベルモントの5つの行動指針により、社員の具体的な行動がビジョンと一致するようデザイン。経営トップ自らがビジョンを語り続け、社内の意思決定に反映させることで一体感を醸成する。
- ユーザー起点で事業開発する
ビジョンを具現化する新規事業やプロダクトを考える際には、デザイン思考を用いてユーザーの潜在ニーズや課題を発見し、創造的な解決策を形にする。ビジョンとユーザー視点の交差点にこそ革新的アイデアが生まれる。
- 例:任天堂Wiiは「家族の絆を取り戻す」というビジョンから生まれたユーザー体験型商品。オムロンは「ゼロイベント」という目的を掲げ、ユーザーに寄り添った血圧計の開発で新市場を切り開いた。
- ビジョンを軸にブランド戦略を展開する
製品・サービスの提供だけでなく、その価値を伝える物語(ナラティブ)を構築し、一貫したブランド戦略に落とし込む。ビジョンに沿ったストーリーは顧客や社会の共感を呼び、ブランドの熱狂的な支持につながる。
- 例:味の素冷凍食品は「手間抜き」という物語で商品価値を再定義し、ブランドイメージを向上させた。このようにナラティブ・ブランディングでブランド体験をデザインする。
ビジョンを起点にした事業デザインは、時間も手間もかかるアプローチです。しかし、紹介したような各社の成功事例が示すとおり、その労力は長期的な競争優位と企業ブランドの確立によって十分に報われます。
私自身も関わったプロジェクトを振り返ると、やはり初期に描いたビジョンが明確であった企業ほど、組織ブレなく事業成長を遂げていると実感します。逆にビジョンなき戦略は場当たり的になり、いずれ壁に突き当たるものです。
不確実性の高いVUCAの時代だからこそ、自社の軸となる「目的」を据えて経営を舵取りする重要性が増しています。ビジョン→戦略→実行の一貫性を確保することで、社員・顧客・社会が一体となった価値創造のサイクルが回り始めるはずです。
ビジョンを起点に事業をデザインすることは、企業にとって羅針盤を手に航海に出るようなもの。明確な羅針盤を持った企業こそ、荒波の市場環境でもぶれずに進み、やがて大きな成果地に辿り着けるのだと考えます。
参考記事