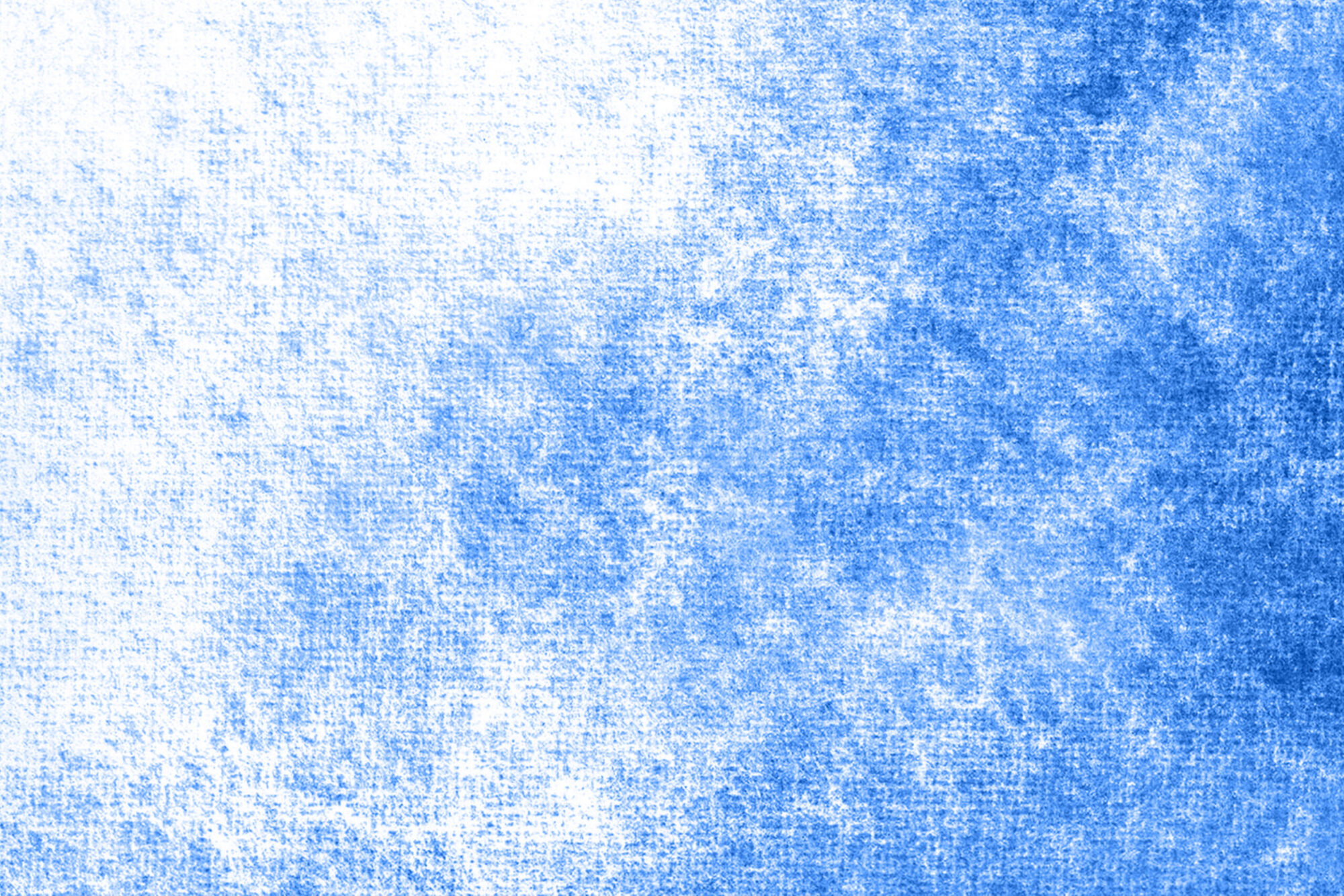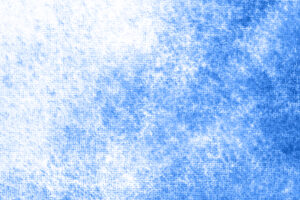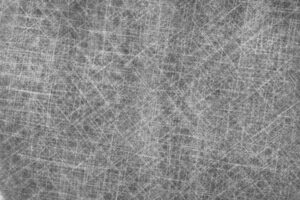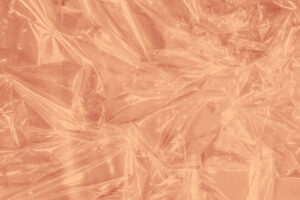目次
1. ブランド戦略と組織変革の関係性
企業が持続的に成長するためには、「ブランド」と「組織」を切り離して考えることはできません。ブランドの内側=組織文化、ブランドの外側=市場での認知というように、ブランド戦略と組織変革は表裏一体の関係にあります。企業文化や従業員の振る舞いがブランドの一貫性を支え、逆にブランドのビジョンが社員の行動指針となるサイクルを築くことが重要です。
実際、社内にブランド戦略を浸透させ「インナーブランディング」を強化することで、社員がブランドの価値観を共有し、優秀な人材を引き付ける効果も期待できます。
例えばスターバックスでは、スタッフ自身がスターバックスの熱心なファンであり、そのブランドらしさを深く理解しているため、自発的にブランドを体現する行動が取れると言います。このようにブランド戦略と組織文化の連携が図られることで、企業は内外から強いブランドを築き、持続的な成長基盤を整えられるのです。
2. 商品ではなく「関係性」で価値を生み出す時代へ
かつてのビジネスモデルでは、優れた商品やサービスそのものが価値の源泉と考えられてきました。しかし現在では市場環境や顧客の価値観が変化し、企業と顧客の長期的な関係性こそが価値を生む時代になっています。顧客は単に商品を消費するだけでなく、そのブランドが提供する体験や共感できる世界観を求めています。
例えば、スターバックスはコーヒーという「商品」以上に、居心地の良い空間やコミュニティといった付加価値を提供し、顧客の心を掴むことに成功しました。また、アウトドアブランドのスノーピークは1998年から顧客参加型のキャンプイベントを開催し、愛好者同士や経営陣が交流するコミュニティを育んでいます。こうした取り組みにより、ブランドと顧客との絆が強まり、生涯にわたるファンを生み出しているのです。
一方で、時代の変化に対応できず商品中心の発想に固執した企業は苦戦を強いられています。カゴメの例では、トマト製品で確立したブランドがありながら、総合食品メーカーを目指してコーヒーや紅茶事業に手を広げた結果、大量の在庫処分と値崩れに陥りブランドイメージを損ねてしまいました。
この失敗から立て直すためにカゴメは取扱商品を絞り、自社の存在意義を「トマトと野菜」に再集中するブランド戦略を打ち出して信頼を回復しています。この事例は、企業が本来提供すべき価値(カゴメなら「野菜の力」)から逸脱した商品展開を行うと、顧客との関係性が崩れブランドが危機に陥ることを示しています。逆に言えば、自社のブランドパーパス(存在意義)に基づき顧客との関係性を構築していくことが、現代の持続的な成長には不可欠なのです。
3. ブランド価値を実装するための3つのステップ
強固なブランド価値を組織の中で実現し、それを市場で発揮するには次の3つのステップが有効です。
STEP
戦略を「組織の意思」として共有する
まずブランド戦略やビジョンを経営層だけのスローガンに終わらせず、組織全体の意思として共有します。具体的には、ビジョン・ミッション・バリュー(VMV)を言語化し、経営者だけでなく社員一人ひとりが自分事として理解できる状態を作ります。ビジョン策定は単なるお題目ではなく、企業が「何者で、どこへ向かうのか」を示す羅針盤です。このプロセスではワークショップや対話を通じて社員の声も取り入れ、戦略が単なるトップダウンの指示ではなく組織の総意となることを目指します。
私自身、複数の企業のブランド立ち上げに関わってきましたが、初期段階でビジョンや理念をしっかり定義し共有できたケースでは、事業のブレが少なく組織文化の醸成もスムーズでした。逆にここを疎かにすると、後になって理念浸透のための組織変革に大きなコストがかかります。スタートアップでも設立初期に理念を明確化することが、文化形成と事業の軸ブレ防止に特に重要だと痛感しています。
STEP
ブランドの世界観を「体験」に変換する
次に、策定したブランドのビジョンや世界観を、顧客やユーザーが体感できる具体的なプロダクトやサービス体験に落とし込みます。ブランドの約束やストーリーが、商品コンセプトや接客対応、空間デザインなどあらゆる顧客接点に反映されるように設計します。言い換えれば、ブランドの世界観=顧客体験となるよう変換する段階です。
例えば、「Natural」「Organic」「Smart」というブランドコンセプトを掲げたスーパーホテルでは、ロゴデザインの刷新だけでなく、客室やアメニティに天然素材を用い、朝食にも健康志向メニューを取り入れるなど、コンセプトを具体的な宿泊体験に落とし込みました。これにより顧客はホテル滞在を通じて同社の世界観を五感で感じ取り、ブランド価値を実感できるようになったのです。またAppleなどは製品そのもののデザインやユーザーエクスペリエンス(UX)に徹底してブランド哲学を反映し、市場を席巻しました。
このステップでは、マーケティング部門だけでなく開発・営業・カスタマーサポートなど部門横断で協力し、ブランド体験を統合的に設計することが重要です。ブランド戦略が現場の体験に落とし込まれることで初めて、顧客にとって意味のある価値として実現されます。
STEP
変革を「日々の行動」に落とし込む
最後に、ブランド戦略に基づく変革を社員一人ひとりの日々の行動レベルまで定着させます。華やかなビジョンも現場で実践されなければ絵に描いた餅です。組織文化や風土の醸成を通じて、社員が日常業務の中で自然とブランド価値を体現できるようにする仕組みづくりが求められます。
例えばスターバックスでは、「従業員=パートナー」としてミッションやバリューを共有し、現場のバリスタが自発的にブランドらしい行動(心温まる接客やコミュニティ活動など)を取れる文化を培っています。これを支えるのが評価制度や研修、社内コミュニケーションです。
ブランド理念に沿った行動を評価・表彰したり、成功事例を社内で共有したりすることで、変革を推進するカルチャーの醸成につなげます。また、経営トップ自らがブランド理念を体現した意思決定や発信を続けることも重要です。リーダーが日々の言動でブランド価値を示すことで、社員もそれに倣い行動を変えていきます。
日本企業の例では、ある飲料メーカーが社内プロジェクトで「ブランドらしい振る舞い10か条」を社員と共に策定し、朝礼での唱和や現場での実践チェックリストに組み込んだケースがあります。小さな行動変容の積み重ねが、やがて大きな組織文化の変革となり、ブランド価値を盤石なものにしていくのです。
4. フレームワークで見るブランド戦略と組織変革の統合
上述のステップを支援するために、近年はいくつかの有用なフレームワークが活用されています。ここではブランド戦略と組織変革の統合に役立つ代表的な手法と、そのポイントを解説します。
- パーパス・ドリブン経営
「パーパス(存在意義)」を起点に経営を行う考え方です。企業の社会的意義や使命を明確化し、それをブランド戦略と組織運営の軸に据えます。パーパスは単なるミッションステートメントではなく、企業が社会にどう役立つかを示す根源的な価値観です。パーパス・ドリブン経営では、この価値観を製品開発やサービス提供、人事制度に至るまで反映させます。
例えば、自動車メーカーのマツダは「前向きに今日を生きる人の輪を広げる」というパーパスを掲げ、その実現に向けた長期ビジョン「MAZDA 2030」を策定しました。
このパーパスはブランドメッセージにも組織文化にも浸透しており、社員の誇りや意思決定の拠り所となっています。パーパスが明確だと、ブランドの方向性と組織の価値観にブレが生じにくく、社内外のステークホルダーとの強い紐帯を築けるのが利点です。
- OKR(Objectives and Key Results)
OKRは目標と主要な成果指標を設定・共有する目標管理フレームワークです。ブランド戦略と組織の成長目標を定量的に統合する手法として注目されています。
具体的には、企業全体の野心的なObjective(目的)を設定し、それを実現するための測定可能なKey Results(主要成果)を各部署・個人にブレイクダウンします。OKRを導入すると、組織全体で「何が今期の最重要目標か」が透明化され、部署横断での協力体制が築きやすくなります。
例えばブランドの観点では、「顧客ロイヤルティ指標を前年比○%向上させる」というObjectiveを掲げ、これを各現場のKR(リピーター増加数、NPSスコア向上など)に落とし込みます。定期的な進捗確認により、全員がブランド戦略上のゴールに向けて日々の業務を調整できます。
私が支援したある企業でも、OKRで「ブランド認知度向上」をトップObjectiveに据え、開発・営業・カスタマーサクセスの各チームがそれぞれ関連KRを設定したところ、組織横断でブランドプロジェクトが推進されるようになりました。OKRは戦略(ブランド目標)と戦術(日々の活動)のブリッジとなり、組織変革をドライブする強力なエンジンになります。
- ナラティブ・ブランディング
ナラティブ(物語)を活用してブランド価値を高めるアプローチです。企業の歴史や創業者の想い、商品開発の背景など、ブランドにまつわる物語を戦略的に発信し、顧客や社員がその物語を共有・共感することでブランドを強化します。単なる広告コピーではなく、ストーリーとして語れるブランドを構築する点に特徴があります。
例えば、スポーツブランドのNikeは「Just Do It」のスローガンのもと、挑戦するアスリートの物語を発信し続けています。近年では社会課題に対する姿勢も物語に組み込み、あるキャンペーンでは人種差別への反対という強いメッセージを打ち出しました。賛否両論を巻き起こしながらもそのストーリーに共感する支持層を明確にし、結果としてブランド価値を一段高めることに成功しています。ナラティブ・ブランディングは社内にも効果を及ぼします。社員が自社ブランドの物語を誇りに思い語れるようになると、採用ブランディングやエンゲージメント向上にもつながります。
国内企業でも、老舗企業が創業○○年の歴史や職人技にまつわるストーリーをリブランディングに活用したり、スタートアップがビジョン実現に向けた挑戦の物語を発信してコミュニティを醸成したりといった事例が増えています。「ブランドは語るもの」という視点で戦略を再構築することが、組織と市場の双方で共感を呼ぶ鍵となるでしょう。
以上の他にも、近年はエンゲージメント経営(従業員のエンゲージメントを高める施策全般)やデザイン思考(ユーザー共感に基づく問題解決手法)などがブランドと組織を結び付ける文脈で活用されています。重要なのは自社の状況に応じて適切なフレームワークを選び、戦略と文化を橋渡しする道具として使うことです。
フレームワークはあくまで手段なので、導入すること自体が目的化しないよう注意しながら、組織変革とブランド構築の両輪を前進させていきましょう。
5. 戦略と文化の融合による変革事例
では、実際にブランド戦略と組織文化の融合によって企業が変革を遂げた事例をいくつか見てみます。
- スタートアップのブランド戦略と組織文化の確立
創業間もないスタートアップ企業では、初期段階で明確なビジョンやバリューを定め、それを社内文化に落とし込むことが成長のカギになります。
例えばあるIT系スタートアップでは、「世界にインパクトを与えるプロダクトを創る」というビジョンを掲げ、創業当初からコアバリュー(行動指針)を5つ定義して社員に共有しました。急拡大する組織においてもこのバリューを評価制度や日々の朝会で徹底し続けた結果、新しいメンバーも含め社員全員が意思決定のよりどころを共有し、ブレないブランドイメージを対外的にも発信できています。「人材が流動的で先が読めないスタートアップだからこそ、文化とブランドを意図的にデザインする必要がある」というのが、その会社の創業者の言葉でした。
実際、明文化されたビジョンが採用ブランディングにも寄与し、「このビジョンに共感したい」という人材を引き付ける好循環を生んでいます。スタートアップにとってブランド戦略と組織文化の確立は、単なるマーケティング上の差別化だけでなく生存戦略そのものと言えるでしょう。
- 伝統産業のビジネスモデル転換支援: 長年続く老舗企業や伝統産業が時代の変化に適応する際にも、ブランドと組織の同時変革が成功のポイントになります。
例えば創業100年以上のある老舗メーカーは、主力商品が市場縮小する中で大胆な事業転換を迫られました。同社はまず企業の存在意義を再定義し、「○○文化を未来につなぐ」という新たなブランドパーパスを策定。次に、そのパーパスに沿って事業ポートフォリオを見直し、新規事業(例:サブスクリプションサービスや海外展開)に着手しました。もちろん新しいビジネスモデルに社内の意識改革が追いつかなければ成功はおぼつきません。そこで経営陣は組織開発チームを設置し、従来の職人気質な風土に革新性を取り込む文化醸成プログラムを展開しました。
具体的には、若手とベテランの混成プロジェクトによる新商品開発コンペを実施したり、外部からデジタル人材を招聘して社内研修を行うなど、新旧融合を図る取り組みを行いました。結果として、社員のマインドセットが徐々に変わり、「挑戦と伝統が調和する」独自の組織文化が醸成されています。その文化はそのままブランドメッセージにも表れており、近年のプロモーションでは「伝統に革新を纏う」といったコピーで新ブランドを打ち出しています。老舗企業がビジネスモデル転換に成功する裏には、ブランド戦略の刷新と組織文化変革を両輪で進めた地道な努力があるのです。
- 大企業の組織変革とブランド再生事例: 大企業においても、経営不振や環境激変を乗り越える局面で、ブランドと組織を一体で再生させた例があります。代表的なのが日本航空(JAL)のケースです。JALは2010年に経営破綻し公的支援を受けましたが、僅か2年で驚異的な業績回復を遂げました。その背景には、「JALフィロソフィ」という経営理念を全社員3万5千人に浸透させる徹底したインナーブランディング施策がありました。再建プロセスではまずJALのブランド価値(安全とおもてなし)を社員一人ひとりが再認識し、自社の提供価値を根本から見直すことから始めています。経営トップ自らが全国の現場を回り理念を説き、社員同士でもサービス向上に向けた提案や成功事例を共有する場を設けました。
その結果、「新生JAL」の価値観が隅々まで共有され、社員の意識と行動が大きく変わりました。例えば破綻前には考えられなかった現場主体の改善提案が多数上がるようになり、乗客へのサービス品質も向上しました。これら組織文化の変革がブランドイメージの回復につながり、顧客からの信頼を取り戻すことに成功しています。
JALの事例は、ブランド再構築=組織文化再構築であることを示す象徴的なケースと言えるでしょう。またこの他にも、トヨタ自動車が全社的な品質文化の醸成によって「トヨタ品質」のブランドを守り抜いた例や、任天堂が社内に「娯楽を届ける」という理念を徹底することでゲーム事業の浮き沈みを乗り越えてきた例など、戦略と文化の融合による変革は数多く存在します。
6. 「ブランドの未来」は戦略と組織のデザインで決まる
以上見てきたように、企業が長期的に成長し続けるためには、ブランド戦略と組織設計(文化・仕組み)の融合が欠かせません。ブランドの未来は、戦略と組織のデザインに委ねられていると言っても過言ではありません。では、その未来を切り拓くために実務レベルで企業が取るべき具体的アクションを整理してみましょう:
- ビジョン・理念の徹底言語化と共有
まず自社のビジョンやパーパスを明文化し、経営陣から新入社員に至るまで共有します。企業説明会から朝礼、社内報まであらゆる機会を通じて繰り返し語り掛け、理念が全員の判断基準になる状態を目指します。
- 組織とブランドの目標を統合
OKRなどを活用して、ブランド戦略上の目標と各部門・個人の目標を紐付けます。四半期ごとにブランド指標と事業KPIの両面で進捗をチェックし、ずれがあれば早期に修正します。こうすることで日々の業務とブランド戦略が乖離せず、一体となって前進します。
- 顧客体験のデザイン
自社ブランドが提供したい価値を顧客が確実に感じ取れるよう、顧客体験(CX)を丁寧に設計します。顧客の旅路(カスタマージャーニー)上の各接点で、ブランドらしさを演出する仕掛けを組み込みます。店舗やWebサイトのデザイン、接客トーク、商品パッケージに至るまで一貫した体験を提供しましょう。
- 文化浸透の仕組み化
社内研修や評価制度を見直し、ブランドのバリューに沿った行動を促進します。例えばバリューを体現した社員を表彰したり、1on1ミーティングで日々の業務をブランド視点でフィードバックするなど、文化浸透を日常業務に組み込みます。
- リーダーシップとコミュニケーション
経営トップやミドルマネジメントが率先してブランド戦略×組織変革の重要性を語り、模範を示します。トップダウンとボトムアップ双方のコミュニケーションを活性化させ、全社的な巻き込みを図ります。必要に応じて社内公募制度などで変革推進メンバーを募り、全員参加型のブランドづくりにするのも有効です。
- 社外との対話と学習
顧客やパートナー企業との対話を通じて、自社のブランド提供価値が適切に伝わっているかフィードバックを得ます。また他社の成功事例から学び、常にブランド戦略と組織運営の改善サイクルを回します。ブランドの約束と現実にギャップが生じていれば、速やかに原因を分析し対策を講じます。
最後に肝心な点は、一貫性と継続性です。ブランド戦略と組織変革の統合は一朝一夕で完了するものではなく、経営環境の変化に合わせて常に進化させていく取り組みです。短期的なキャンペーンや単発の研修で終わらせず、長期的視点で戦略と文化の両面から組織をデザインし続ける姿勢が求められます。
私自身、ブランドプロデューサーとして現場に関わる中で、「文化は戦略に従う」だけでなく「文化が戦略を推進する」瞬間を何度も目にしてきました。社員がブランドの意義を本当に理解し腹落ちしたとき、戦略は現場の創意工夫によって想像以上の成果を上げるものです。その状態を作り出すのが経営者の腕の見せ所であり、ブランドの未来を形作るデザインワークと言えるでしょう。
組織と人の力でブランドに命を吹き込み、市場で輝きを放つ——そのような「価値を生み出す仕組み」を社内に築けた企業こそが、これからの不確実な時代においても揺るぎない成長を遂げるのではないでしょうか。
参考記事
〖ブランド戦略とは?〗事例と成功させるための5つのステップを解説!(株式会社パラドックス)
ブランディングメディア|PARADOX...
【ブランド戦略とは?】事例と成功させるための5つのステップを解説!
ブランド戦略とは、ブランドの認知を広げ、価値を高めるために行う戦略のことであり、経営に影響を与える重要な戦略です。この記事では、私たちパラドックスが考えるブラン...
ブランディング戦略とは? 5つのステップと有名企業の成功&失敗事例を紹介!(THE OWNER)
「スノーピーク」!ブランドでは珍しいファンコミュニティの作り方(InterFM ラジオ番組『お店ラジオ』)
インターエフエム [ 89.7MHz TOKYO...
「スノーピーク」!ブランドでは珍しいファンコミュニティの作り方
3/6(日)9pm - 9:30pmお店ラジオ supported by スマレジいらっしゃいませ!事業投資家の三戸政和さんと、スマレジ代表の山本博士さんでお送りしている『お店ラジオ』。今...
「思想の言語化」が鍵だった!採用ブランド戦略の構築フローを紐解く。(note|ヤマグチタツヤ)
note(ノート)
「思想の言語化」が鍵だった!採用ブランド戦略の構築フローを紐解く。|ヤマグチタツヤ
こんにちは、ヤマグチタツヤです。 コーポレートブランディングの一環で採用ブランディングのお手伝いをすることもあるのですが、 「採用ブランディングで普段何やっている...
パーパスドリブンとは?日本企業の取り組み事例6選を紹介(タナベコンサルティング)
長期ビジョン・中期経営計画策定の...
パーパスドリブンとは?日本企業の取り組み事例6選を紹介|タナベコンサルティングの長期ビジョン策定支援
自社の利益だけでなく社会的な利益にかなった企業活動が求められ現代。「パーパスドリブン」の概念が重要になります。パーパスドリブンの重要性と、日本企業の取り組み事例...
OKRとは?KPIとの違い、正しい設定方法と具体例(株式会社KWAVE)
株式会社KWAVE
OKRとは?KPIとの違い、正しい設定方法と具体例 | 株式会社KWAVE
ビジネスにおいて、目標達成のための効果的なフレームワークは必要不可欠です。その中でも、OKR(Objectives and Key Results)は、組織の目標設定とその達成を効果的に行...
3万5千人のスタッフにJALブランドを浸透させ、再生へと、加速する。(JAL事例紹介記事)
ソリューションサイト
【日本航空株式会社様】3万5千人のスタッフにJALブランドを浸透させ、 再生へと、加速する。(経営理念...
2010年の会社更生法の適用から、わずか2年。 営業利益約2,000億円と 驚くべきスピードで業績回復を果たしている日本航空(以下JAL)。 現在、3万5千人のJALグループのフラ...