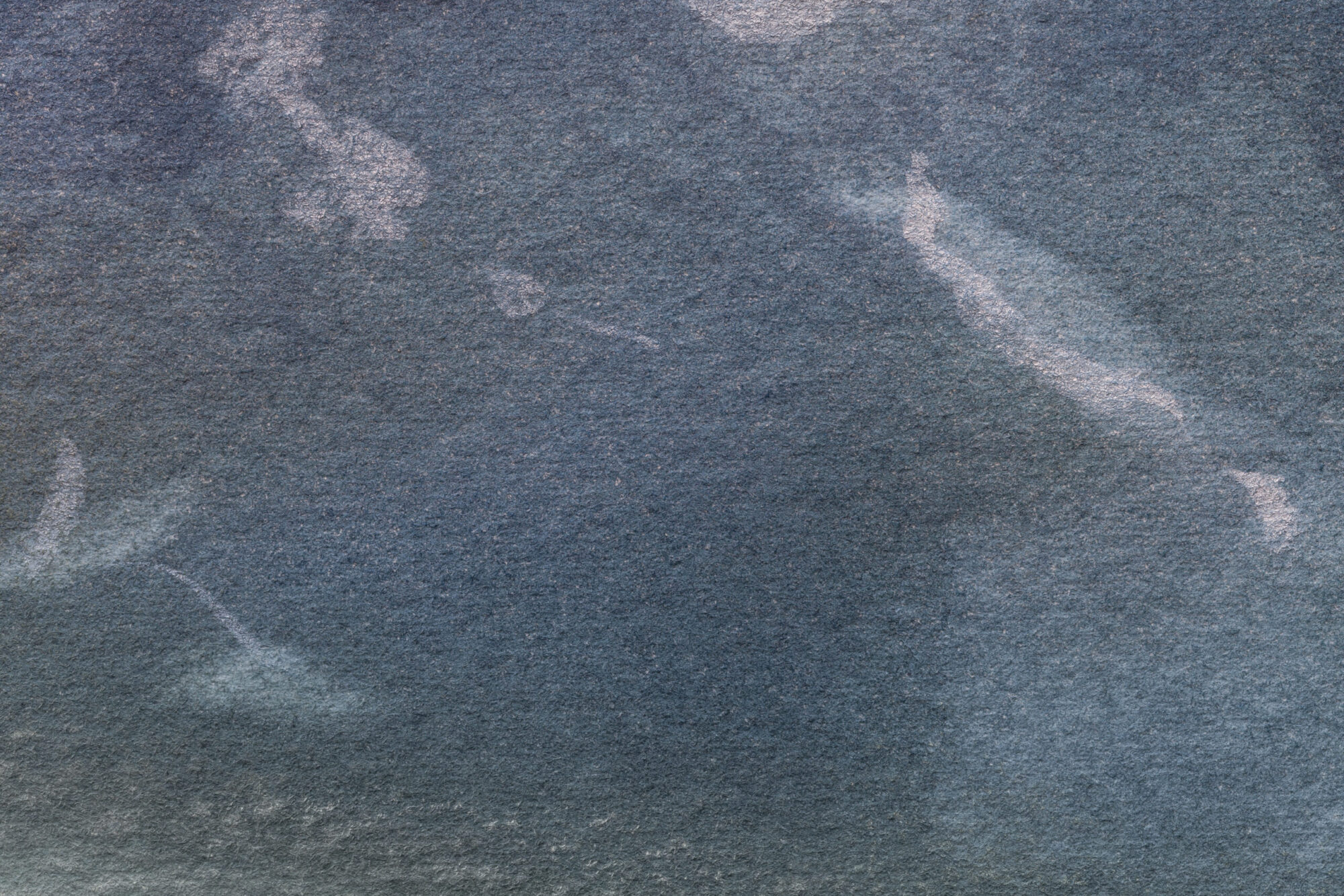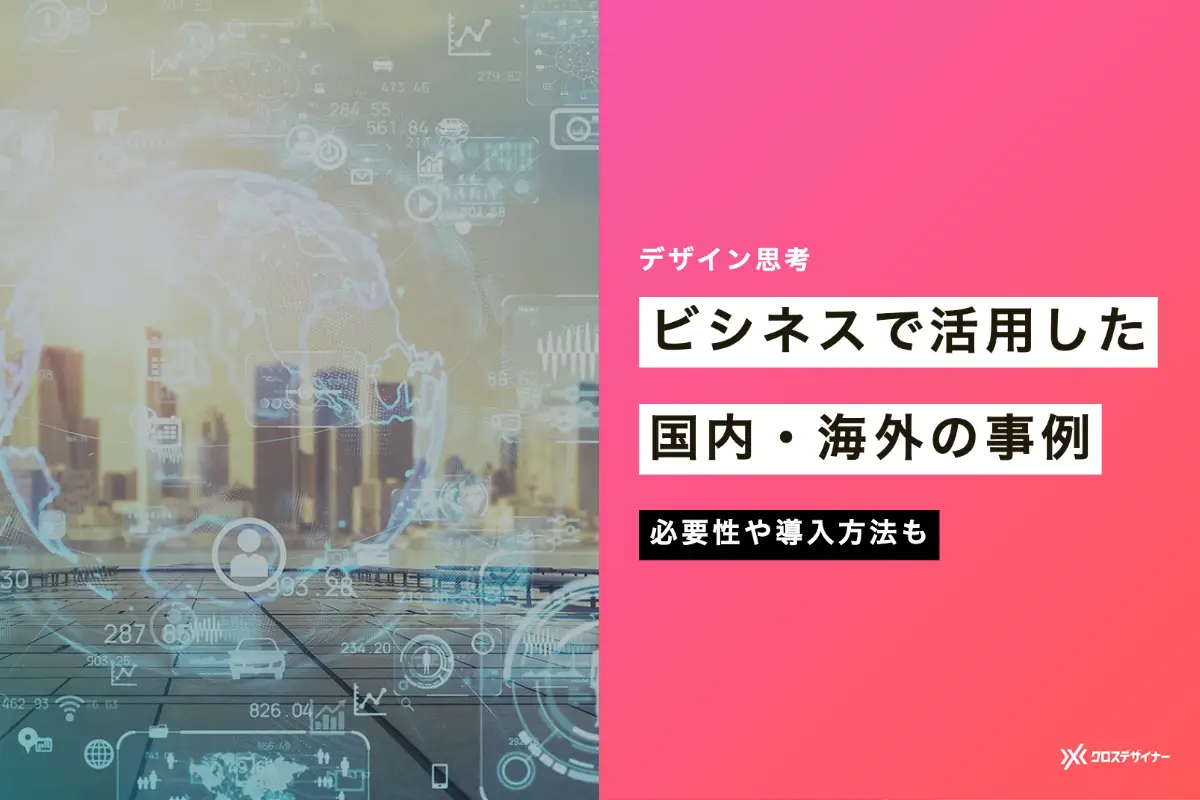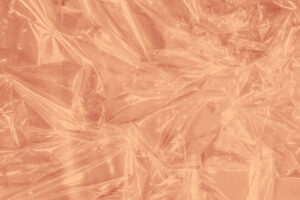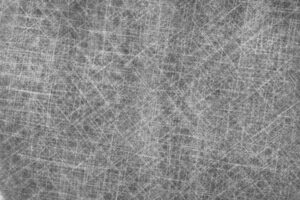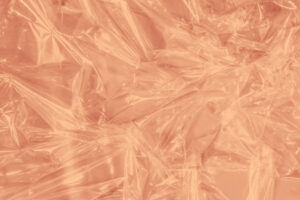目次
はじめに
現代のビジネス環境では、戦略とデザインの統合が企業ブランディングの成否を分ける重要なポイントになっています。優れた商品やサービスだけでなく、企業の理念や価値観を視覚的に表現し伝えることが、競争優位性の確立につながるからです。企業価値の多くがブランドなど無形資産によって構成されると言われる中、戦略とデザインを一体化させて企業の価値を「見える化」することが求められています。
この記事では、戦略的なデザイン手法を活用し企業価値を可視化する方法について、具体的な国内企業の事例を交えながら解説します。専門的な内容を実務に落とし込めるように、デザイン思考やブランド・アーキタイプ、ビジュアルアイデンティティ戦略といったフレームワークも紹介し、企業ブランディングに役立つポイントを探っていきます。
戦略とデザインを統合する意味と重要性
戦略とデザインを統合するとは、経営戦略・ブランド戦略と、ロゴや製品デザインなどのビジュアル表現を一貫した方針で結びつけることです。企業のミッション・ビジョン(存在意義や目指す将来像)に沿ってデザインを活用することで、企業の価値観や強みをステークホルダーに効果的に伝達できます。これにより、単に見た目が良いデザインを作るのではなく、デザイン自体が企業の価値を体現し、ビジネス目標の達成に貢献するようになります。
戦略とデザインの統合が重要視される背景には、市場環境の変化と無形資産の重要性があります。近年、顧客は企業の提供する体験全体から価値を判断する傾向が強まっています。製品の機能や価格だけでなく、その企業の理念や社会的役割に共感して選ぶケースも増えました。デザインはそうした企業の理念・価値を視覚的に表現する役割を担います。統合された戦略デザインにより、社内外の人々に「この企業は何を大切にしているのか」が直感的に伝われば、信頼感やブランドエクイティ(ブランド資産)の向上につながります。
例えば、企業ブランディングの成功例からは一貫したメッセージとデザインが収益性や顧客ロイヤリティを高めることが明らかになっています。自社の核となるメッセージがデザインに落とし込まれていると、広告や商品パッケージ、ウェブサイトなどあらゆる接点で統一感が生まれ、顧客の記憶に残りやすくなります。その結果、中長期的には市場で選ばれ続ける強いブランドとなり、売上や企業価値の向上に寄与します。
企業価値を可視化するためのフレームワーク活用
戦略とデザインを効果的に統合するには、いくつかのデザインフレームワークを活用することが有効です。ここでは代表的な手法である「デザイン思考」「ブランド・アーキタイプ」「ビジュアルアイデンティティ戦略」の3つについて、その概要と実務での役立て方を見てみましょう。
デザイン思考:ユーザー視点で価値を創造する
デザイン思考(Design Thinking)は、もともとデザイナーの発想プロセスを起点にした問題解決手法ですが、現在では新規事業開発や経営戦略にも広く取り入れられています。デザイン思考のプロセスは一般に「共感→定義→創造(発想)→試作→テスト」の5段階で構成されており、徹底的にユーザー(顧客)の視点に立ってニーズを探り出し、それに応えるアイデアを具現化する点が特徴です。
ビジネス戦略の立案段階からデザイン思考を活用することで、企業の提供価値がより顧客本位なものになります。例えば製品開発において、マーケティングデータだけでなくユーザーへのインタビューや観察を行い潜在的な課題を発見することで、戦略そのものに顧客体験の視点を組み込めます。そのうえでプロトタイプ(試作品)をデザインし、ユーザーテストで得たフィードバックを戦略に反映させれば、戦略とデザインが一体となったソリューションが生まれます。
日本企業でもこのアプローチで成功している例があります。たとえば富士通株式会社は2016年から全社的にデザイン思考の導入を進め、従業員の発想力育成に力を入れていることで知られています。またオムロンヘルスケア株式会社では、ユーザーの声を丹念に拾うデザイン思考のプロセスから生まれたウェアラブル血圧計を商品化しました。この製品は「日中でも手軽に血圧を測りたい」という潜在ニーズを掘り起こし、腕時計型というデザインで実現したものです。見た目も従来の医療機器らしくないスマートなデザインにすることで、「健康管理を頑張っている」と周囲に知られたくないユーザー心理にも配慮しています。こうした事例に見るように、デザイン思考は顧客インサイトと企業戦略をつなぐ架け橋となり、新しい価値創造と企業ビジョンの具現化に役立ちます。
ブランド・アーキタイプ:企業の人格を定め一貫性を生む
ブランド・アーキタイプは、企業やブランドに人格(キャラクター)を与えるフレームワークです。心理学者ユングの提唱した元型(アーキタイプ)の概念をマーケティングに応用したもので、12種類の典型的な人格像から自社ブランドの性格を定義します。例えば「英雄(Hero)」「無邪気(Innocent)」「アウトロー(Outlaw)」「魔法使い(Magician)」といったアーキタイプがあります。自社のブランドをこれらになぞらえて位置づけることで、ブランドが発するメッセージやトーン&マナーに一貫性を持たせることができます。
ブランド・アーキタイプを活用すると、社内のブランド理解が深まり戦略的な意思決定がしやすくなる利点があります。企業の価値観や約束したい顧客体験が明確になるため、デザイン面でもブレない指針が得られるのです。
例えば、「魔法使い(Magician)」を自社のアーキタイプと定めたブランドは、顧客に驚きや感動を提供することを重視します。この場合、視覚デザインでは神秘的で創造性に富んだ表現を用い、コピーライティングでは「想像を超える体験」「夢を実現する」といった語り口になるでしょう。
有名な例を挙げれば、スターバックスはブランド・アーキタイプの理想的な活用例と言われます。スターバックスは大量の広告を打たず、店舗という空間デザインや接客体験そのものにこだわる戦略をとってきました。その根底には「日常に魔法をもたらす場所を作る」という思想があり、まさに魔術師(Magician)のアーキタイプでブランドを統一しています。店内の照明や音楽、香りに至るまで五感に訴える演出で顧客に特別なひとときを提供し、ロゴの人魚(サイレン)も異世界的な雰囲気を醸し出しています。このようにアーキタイプを定めることで、企業のビジュアルから言葉遣いまで軸が通り、結果的に企業の価値観が消費者に伝わりやすくなります。
中小企業でもブランド・アーキタイプは有用です。例えばアウトドア用品メーカーが「探検家(Explorer)」のアーキタイプを採用すれば、「未知への挑戦」「自由と冒険」をキーワードにデザインコンセプトを作り込むことができます。その結果、ロゴや広告ビジュアルに冒険心が感じられる写真や書体を使い、製品もタフで機能的な印象に統一するといった具合に、デザインが企業の人格を体現するようになります。ブランド・アーキタイプは企業の内側にある価値を引き出し方向付けするフレームワークであり、戦略とクリエイティブの橋渡しに有効なのです。
ビジュアルアイデンティティ戦略:視覚要素で価値を表現する
ビジュアルアイデンティティ戦略とは、企業の視覚的なブランド表現を体系的に構築することです。具体的には、ロゴマーク、色彩、書体(タイポグラフィ)、レイアウト様式、さらには名刺・封筒から店舗デザイン・ウェブサイトまで、視覚に訴えるあらゆる要素に一貫したルールを定めます。その目的は、企業の理念や差別化ポイントを視覚言語としてデザインに落とし込み、誰が見ても「あの会社だ」と認識できるようにすることです。
ビジュアルアイデンティティ戦略を考える際には、自社のコアバリュー(核となる価値)をどのような視覚要素で表現できるかがポイントになります。例えば「先進性」「革新」が価値軸の企業ならば、ロゴにはシャープでモダンなフォントを用い未来志向を感じさせるデザインにする、配色も鮮烈な色やコントラストの強い組み合わせで大胆さを示す、といった選択が考えられます。一方「安心感」「伝統」を重んじる企業ならば、ロゴは安定感のあるシンボルマークや落ち着いた書体にし、色も紺や深緑など信頼感のあるトーンを選ぶでしょう。このように、視覚デザインの細部に至るまで戦略に裏付けされた意味を込めることが重要です。
実務上はまずブランドガイドラインを策定し、デザイナーだけでなく社内の関係者全員がそのルールを共有します。ガイドラインにはロゴの使い方(最小サイズや余白の規定など)、公式カラーコード、フォントの指定、写真やイラストのスタイル、レイアウトのグリッドシステムなどを盛り込みます。これにより、広告代理店やWeb制作会社など外部パートナーが関与する場合でも、常にブランドの視覚表現がブレずに統一されます。一貫性のあるビジュアル展開は企業のアイデンティティを強固にし、価値観を明確に印象付ける効果があります。
また、ビジュアルアイデンティティ戦略は単なるデザイン規定ではなく、企業戦略の変化に合わせて進化させるべきものです。市場環境やターゲット層が変われば、視覚表現も最適化する必要があります。ただし変えすぎるとブランド認知がリセットされてしまうため、戦略目標を踏まえた上で徐々にアップデートしていくのがコツです。後述する事例にもあるように、ロゴ刷新やブランドカラーの変更は企業の節目(創立◯周年や事業転換期など)に戦略的に行われることが多いです。ビジュアル面から企業のメッセージを伝えるこの戦略は、戦略デザインの成果を最も直接的に可視化するプロセスと言えるでしょう。
戦略デザインの成功事例(国内企業)
それでは、戦略とデザインの統合によって企業価値の可視化に成功した国内企業の具体的な事例を見てみましょう。ここでは過去の記事で取り上げていない新たな例として、業種の異なる3社をピックアップしました。それぞれデザイン手法の活用やブランド戦略の工夫によって企業価値を高め、市場で存在感を示したケースです。
事例1:湖池屋(Koikeya) – 老舗菓子メーカーのブランド再構築
スナック菓子メーカーの株式会社湖池屋は、長年親しまれてきた老舗ブランドを持ちながら、市場環境の変化に合わせたブランド改革に成功した好例です。湖池屋はポテトチップス「コイケヤポテトチップス(うすしお味)」で有名ですが、2010年代半ば、市場での競合激化や価格競争への対応が課題となっていました。そこで2016年頃から戦略的なリブランディングに着手し、企業の価値を改めて訴求する取り組みを行いました。
湖池屋の戦略デザイン改革のポイントは、大きく二つあります。一つは商品戦略の刷新、もう一つはビジュアルアイデンティティの強化です。商品戦略では、まず看板商品だった「うすしお味」のポテトチップスをリニューアルし、名称も「じゃがいもと塩」に変更しました。シンプルな名前に変えることで素材そのもののこだわりを前面に出し、「良質なじゃがいもと塩を使ったプレミアムなポテトチップス」という印象付けを狙ったのです。また、塩を使わないヘルシー志向の新商品「ポテトの素顔」や、大豆を使った高タンパクのお菓子など、老舗として培った技術で素材を活かす新商品ラインを次々に投入しました。これにより、安価で大衆的なお菓子というイメージから、素材と製法にこだわる品質志向のブランドへとポジショニングを転換しています。
ビジュアル面でも湖池屋は大胆な変更を行いました。長らく使われてきた親しみやすいロゴデザインを見直し、漢字の「湖池屋」をあしらったシンプルかつ堂々としたロゴを新たに採用します。配色もモノトーン基調に切り替え、パッケージデザインは白や黒をベースにした洗練されたデザインに統一されました。例えば高価格帯シリーズ「プライドポテト」では、余計な装飾を省いた上質な質感の袋に商品名と社名ロゴを配置し、老舗の風格と高級感を演出しています。こうした統一感あるデザイン展開によって、湖池屋は「日本初のポテトチップスメーカー」という伝統と品質を強調し、他社との差別化に成功しました。
結果として湖池屋は、プレミアム路線の商品がヒットし、新たな顧客層の獲得と売上増加を実現しています。「安いお菓子」の代名詞から、「ちょっと特別なおやつ」として選ばれるブランドへとイメージ転換できたことは、戦略とデザインの統合効果と言えます。企業が持つ本来の強み(国産スナックのパイオニアであること)をデザインで可視化し、現代の消費者ニーズ(高付加価値・健康志向)にマッチさせた好例でしょう。
事例2:メルカリ – グローバル展開を見据えたリブランディング
フリマアプリで知られるスタートアップ企業の株式会社メルカリは、急成長する中でブランド戦略とデザインを再構築し、企業価値を高めた事例です。メルカリは日本発のCtoCマーケットプレイスとして2013年にサービス開始後、瞬く間に国内トップクラスのユーザー数を獲得しました。その後アメリカや欧州など海外展開も進める中で、2019年にブランドのリブランディング(再構築)を実施しています。
メルカリのリブランディングは、グローバル市場への対応とサービスビジョンの明確化が軸にありました。まず目に見える変化として、ロゴデザインが刷新されています。旧ロゴは「Mercari」の文字とカラフルな箱型アイコンの組み合わせでしたが、新ロゴではシンボルマークと社名ロゴタイプの両方が一新されました。シンボルマークは赤を基調とした立方体のデザインで、開いた箱の中に球体が浮かぶようなグラフィックになっています。このデザインには「人とモノが行き交う場」「思わぬ掘り出し物との出会い」というメルカリのサービスコンセプトが込められており、シンプルながらも遊び心のあるグローバル共通のアイコンとなりました。社名ロゴタイプも視認性の高いサンセリフ体に変更され、どの国のユーザーにも読みやすく親しみやすい印象を与えています。
また、UI/UXデザインの統一と向上も戦略デザインの重要な側面でした。リブランディングに合わせてアプリのユーザーインターフェース(UI)も改良が加えられています。画面上の色使いやアイコン、フォントなどビジュアル要素を新しいブランドガイドラインに即して整備し、ユーザー体験を損なわない範囲で徐々にアップデートしました。例えば、旧来はややポップで雑多な印象だったカテゴリーアイコンやイラスト類を、新しい統一感のあるスタイルに変更し、全体として洗練されたシンプルな画面デザインになっています。これにより、「フリマアプリ=初心者でも簡単・安心」というメルカリの提供価値がUIを通じて表現され、国内外のユーザーに違和感なく受け入れられる基盤ができました。
メルカリのケースでは、デザイン思考的な発想も随所に見られます。ユーザーリサーチの結果を踏まえ、色覚に配慮したカラーパレットを採用するなど、細部までユーザー目線を反映したデザイン改善が行われました。これらの取り組みの結果、メルカリはブランドイメージを統一しつつ多様な市場への対応力を高め、上場企業としての信頼感も醸成しています。社内的にも新しいミッション・バリューを設定し直し、それを体現するデザインを全社員で共有したことで、組織一丸となってグローバル戦略を推進できる土台が築かれました。戦略(グローバル展開・ユーザー信頼の獲得)とデザイン(ロゴ・UI刷新)の見事な統合により、企業価値を次のステージへ引き上げた好例と言えるでしょう。
事例3:ヤンマーホールディングス – 100周年に統一ブランドで価値再定義
建機・農機メーカー大手のヤンマーホールディングス株式会社(ヤンマー)は、創業100周年を契機に戦略とデザインを融合させて企業ブランドを再構築した事例です。ヤンマーといえば長年、農業用機械のメーカーとして日本では知られ、テレビの「ヤン坊マー坊天気予報」のキャラクターなど親しみやすいイメージがありました。しかし事業実態は農機だけでなく舶用エンジンやエネルギーシステムまで多岐にわたり、グローバルにも展開しています。2012年前後、同社はブランド認知の不一致(社名の知名度はあるが企業の本当の姿が正しく伝わっていない)という課題に直面し、100周年プロジェクトとして大規模なブランディング戦略を遂行しました。
ヤンマーの戦略デザイン改革で特筆すべきは、内外両面からのブランディングです。まず内的(インナー)ブランディングとして、企業理念やビジョンの再定義が行われました。新たなブランドステートメント「A SUSTAINABLE FUTURE(持続可能な未来へ)」を掲げ、これを社員一人ひとりに浸透させる施策を展開しています。具体的には、本社社屋をコンセプトに合わせて新築・デザインし直し(大阪に完成したヤンマー本社ビルは環境配慮と先進性を体現する建築として話題になりました)、社内報や研修を通じて社員にブランド理念を共有しました。さらに、社内のデザイン思考ラボを設立してユーザー(農業従事者や建設業者など)の声を商品開発に反映する仕組みを強化し、社員自らがブランド価値を体現する文化づくりに力を入れました。
外的(アウター)ブランディングとしては、ビジュアルアイデンティティの全面リニューアルが挙げられます。ヤンマーは100周年を機にロゴマークを含むVIを刷新しました。それまでのヤンマーのロゴタイプは親しみやすい筆記体風でしたが、新ロゴは「FLYING-Y(フライングワイ)」と呼ばれるシャープなシンボルマークに変更されています。このシンボルは、社名の由来であるトンボ(豊作の象徴とされる「オニヤンマ」)の羽とアルファベットのYをモチーフにデザインされました。先端が鋭角的な形状は、未来を切り拓く先進性と精密な技術力を表現し、情熱や挑戦を示す赤色でカラーリングされています。新ロゴに合わせてコーポレートカラーや書体も定め直し、製品の塗装デザイン、従業員のユニフォーム、営業車両、パンフレット、公式サイトに至るまで順次切り替えていきました。その結果、農業機械メーカーとしての親しみやすさは残しつつも、世界で戦う技術ブランドとして一貫した高級感と先進性が演出されています。
このヤンマーの取り組みは長期にわたり進行し、社内外のステークホルダーの協力も得ながら進められました。たとえばユーザーや販売代理店へのヒアリングを行い、新しいブランドメッセージへの共感を醸成するコミュニケーションも行っています。最終的にヤンマーは、「環境に優しく最先端技術で社会に貢献するプレミアムブランド」という企業価値を明確化し、それを誰の目にも見える形(デザインと行動)で示すことに成功しました。古い企業イメージを脱却し、新生ヤンマーとして国内外で存在感を高めたこの事例は、戦略デザインの総合力を物語っています。経営陣のリーダーシップの下、企業ビジョンとデザインコンセプトを練り上げ、社員がそれを自発的に体現し、顧客にも伝播させた好例と言えるでしょう。
戦略とデザインを統合するためのポイント
以上の事例から見えてくる、戦略とデザインを統合して企業価値を可視化するための共通ポイントを整理します。実務で取り組む際に意識したい点をいくつか挙げてみましょう。
- 企業の核となるメッセージを明確にする:まず自社のビジョン・ミッション・バリューなど、軸となる考え方を言語化します。これが定まっていないとデザインに落とし込む指針も定まりません。ブランド・アーキタイプのようなフレームを使って「企業の人格像」を描くのも有効です。湖池屋の例では「老舗の品質主義」、ヤンマーでは「持続可能な未来」という明確なテーマがデザインの核になっていました。
- ステークホルダー視点で考える:戦略デザインは自己満足になってはいけません。常に顧客やユーザー、社員などステークホルダーの視点で、自社の価値がどう伝わるかを考えます。デザイン思考を取り入れてユーザーインサイトを得る、社員へのヒアリングで内部の価値観とのギャップを埋めるなど、相手目線での検証が重要です。メルカリが色覚への配慮を取り入れたように、小さな配慮が信頼を生みます。
- 一貫性と統一感を徹底する:企業ロゴやカラー、フォントからトーン&マナーに至るまで、一度決めたブランドアイデンティティはあらゆる媒体で統一して使いましょう。顧客との接点ごとにデザインやメッセージがバラバラだと企業価値は十分に伝わりません。ガイドラインの整備と社内外への周知徹底で、統一されたブランド体験を提供できるようにします。特にグローバル展開時には現地ごとに表現がブレないよう注意が必要です。
- 社内浸透と社員の巻き込み:戦略とデザインの統合を成功させるには、社内の理解と協力が欠かせません。ただロゴを変えただけでは企業価値の向上には直結しないからです。ヤンマーのように社員教育や内部プロジェクトを通じて、新しいブランドの意味を共有しましょう。従業員一人ひとりがブランドの担い手(ブランドアンバサダー)となり、日々の業務や行動で体現することで、外部にも自然と企業の価値観が伝わっていきます。
- 時代の変化に合わせて柔軟に進化する:ブランド戦略とデザインは一度作ったら終わりではなく、環境変化に応じて見直しが必要です。ただし軸はぶらさず、進化させることが大切です。市場トレンドやテクノロジーの進歩、社会的課題などを捉えて、自社の価値提供をアップデートすると同時に、それを表すデザイン表現も最適化します。メルカリのようにグローバル化でロゴを刷新したり、湖池屋のように健康志向ブームに合わせ商品とデザインを変えていくなど、戦略目標に応じたリニューアルをタイミングよく行いましょう。
- 効果測定とフィードバック:ブランディング施策やデザイン変更が企業価値向上に寄与しているか、定量・定性の両面で測定することも大事です。ブランドに関する認知度調査や顧客アンケート、売上や株価の推移、人材応募数の変化などKPIを設定し、PDCAサイクルで改善していきます。戦略とデザインの統合効果は測りにくい面もありますが、例えばWeb解析で新デザイン後のユーザー行動を追う、SNS上のブランド言及をモニタリングする等、データに基づく検証を行えば次の打ち手が見えてきます。
おわりに
戦略とデザインを統合して企業の価値を可視化することは、ブランディングの本質とも言えます。デザインは単なる装飾ではなく、企業戦略を表現する強力な手段です。逆に、デザインの力を借りずに言葉だけで自社の価値を伝えるのは困難です。両者を融合させることで、企業は初めて自らの存在意義を鮮明に示し、顧客や社会との強い結びつきを作ることができます。
筆者(ヨコタナオヤ)の経験上、戦略デザインを成功させるには「自社の物語をデザインに語らせる」意識が重要だと感じます。企業が大切にしてきた想いやこれから実現したい未来像を、一貫したビジュアルと言葉に落とし込んでいく作業です。それは時に手間がかかり社内調整も必要ですが、完成した時には社内外に驚くほどの共感と理解を生みます。実務では小さな改善の積み重ねかもしれませんが、常に戦略とデザインの両輪で考えるクセをつけておくことで、ブランド価値向上の機会を逃さず捉えられるでしょう。
変化の激しい時代だからこそ、企業の根幹にある価値を見失わず、しかし表現方法は柔軟に進化させていく姿勢が求められます。戦略とデザインの統合を通じて、自社らしさが光り顧客に選ばれるブランドを築いていきましょう。
参考記事
ブランディングとデザインをつなげ...
404 / NOT FOUND
株式会社ライデン(RYDEN Inc.)は、クリエイティブと戦略の両面から「長期に渡って利益を創出できる強靭なブランド」づくりを支援し、クリエイティブにおける最高のビジネ...
起業家の成長を支える春日井コワー...
ブランドアーキタイプ実践の教科書|スターバックスに学ぶ成功の本質と失敗の教訓
ブランドアーキタイプを“型”ではなく“触媒”として体験設計に活かす実践講座。スターバックスの事例から成功の本質と失敗の教訓を読み解き、3つの典型ミスを避ける具体的チ...