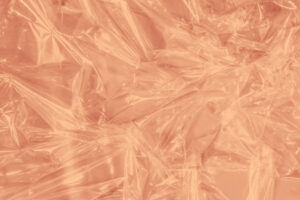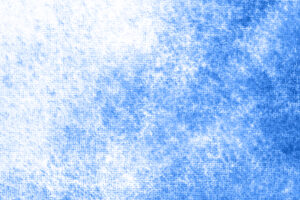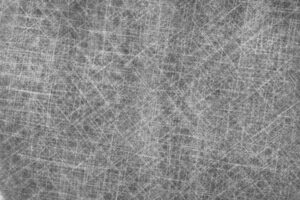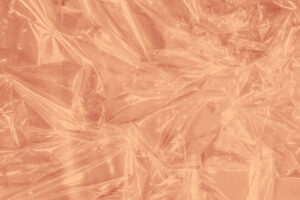目次
ブランド戦略の本質とは?
「ブランディング=ロゴや広告」というイメージを持たれがちですが、それはブランド構築の一部に過ぎません。ブランド戦略の本質は、企業や製品の存在意義や価値観といった「スタンス(立ち位置)の明確化」にあります。ロゴのデザインや派手な広告以上に、「自社は何者で、何を大切にし、顧客にどんな価値を提供するのか」をはっきり示すことが、真のブランディングと言えるのです。
企業がブランド戦略を持つ目的は、自社ならではの価値を打ち出し競合との差別化を図るとともに、顧客からの信頼と共感を獲得することにあります。実際、ブランド戦略(企業ブランディング)は顧客との信頼関係を築き、ブランドロイヤリティ(愛着やリピート購入)を向上させるための重要な取り組みだとされています。
ブランドイメージが確立された企業は、価格競争に陥りにくく、熱心なファンの支持によって持続的な成長が期待できます。そのためには短期的な宣伝効果だけでなく、中長期的に一貫したブランド体験を提供し続ける視点が欠かせません。
要するに、ブランド戦略とは「自社の核となる約束(約束する価値)を定め、それを社内外に一貫して示し続ける活動」です。単なるイメージ作りではなく、企業の理念やビジョンを市場に伝わる形に落とし込み、顧客との継続的な関係性を築くことがブランド戦略のゴールなのです。
ブランド戦略のフレームワーク
ブランド戦略を検討する際には、マーケティングのフレームワークを活用すると効果的です。中でも代表的なのがSTP分析とブランド・エクイティ理論です。それぞれ、ブランド戦略を体系立てて考えるための軸を提供してくれます。
- STP分析(Segmentation / Targeting / Positioning)
-
STP分析は、市場を細分化し(Segmentation)、狙うべき顧客層を定め(Targeting)、競合に対する自社の立ち位置を明確にする(Positioning)一連のプロセスです。マーケティングの権威フィリップ・コトラーが提唱した基本フレームワークであり、自社の「誰に・何を・どのように」提供するかを明らかにします。
ブランド戦略においてSTP分析を行うことで、ターゲット顧客のニーズに合ったブランド体験やメッセージを設計でき、競争の激しい市場でも独自のポジションを築く指針となります。実際、明確に差別化された独自のポジションこそがブランドの特徴を端的に示し、顧客の心に残るブランドを作り上げます。例えば高品質な日常着で世界展開するユニクロは、「LifeWear」というコンセプトのもと幅広い層に訴求するポジショニングを確立し、グローバルブランドへ成長しました。
- ブランド・エクイティ理論
-
ブランド・エクイティ(Brand Equity)とは、ブランドが持つ無形の資産価値のことです。カリフォルニア大学のデービッド・A・アーカーは、ブランド・エクイティを「ブランド名やシンボルに結び付いた資産や負債の集合で、製品やサービスの価値を増大させるもの」と定義し、ブランド認知、知覚品質、ブランドロイヤリティ、ブランド連想などで構成されるモデルを提唱しました。
平たく言えば、ブランドが持つ信頼や好感度といった目に見えない価値を数値化・蓄積していく考え方です。ブランドエクイティが高まれば、消費者が商品を選ぶ際に有利になり、価格プレミアム(高くても選ばれる)や新製品投入時の受け入れ易さなどマーケティング上のメリットが大きくなります。ただしブランド価値は放っておくと徐々に目減りしてしまうため、継続的に育成・投資していくことが重要だとされています。
こうしたフレームワークは、ブランド戦略を「分析→設計→実行」するうえで強力なガイドになります。ただし、「分析手法はあくまで手段であり、最終的にはそこで得た洞察をもとに自社ならではのブランドの物語を紡ぎ、一貫して届けることが重要だ」と私は考えています。
つまり、STP分析で導き出したターゲット像や差別化要素、ブランド・エクイティで重視すべき価値要素を踏まえつつ、自社のビジョンに根差したブランドコンセプトやメッセージを創り上げることが大切です。その上で、商品開発からマーケティング施策に至るまで軸のブレないブランド体験を提供していく――これが実務でフレームワークを活用するポイントです。
成功事例:国内企業のブランディング
では、具体的に国内企業がどのようにブランド戦略を構築・実践して成功しているのか、重複のない事例を見てみましょう。業種や規模は異なりますが、それぞれ自社の強みを活かしたブランド戦略によって競争優位を確立しています。
事例①:ユニクロ — 「LifeWear」で日常着に特別な価値を提供
ユニクロは、日本発ながら世界的に成功したファッションブランドです。同社は**「LifeWear」**というブランドコンセプトのもと、シンプルで高品質、そして機能的な日常衣料を提供する戦略を打ち出しました。これは単なる低価格路線ではなく、「毎日着る服で生活をより良くする」という明確な価値提案です。
実際この戦略は、シンプルさ・快適さ・持続可能性といった価値観に共感する多様な層の顧客を惹きつけ、ユニクロが幅広い世代に受け入れられるブランドへと成長する原動力となりました。
例えば、ヒートテックやエアリズムのような機能性インナーを開発し、「肌着」をテクノロジーで進化させることで他社との差別化に成功しています。また著名デザイナーやキャラクターとのコラボレーションによってブランドの新鮮さを保ちつつ、一貫して「生活を豊かにする普段着」という軸からブレない商品ラインナップを展開している点も特徴です。
明確なコンセプトとグローバル展開戦略の両立により、ユニクロは世界中で支持されるブランドとなりました。
事例②:バーミキュラ(愛知ドビー) — 職人技が生んだ調理器ブランド
バーミキュラは、愛知ドビー株式会社が手掛ける高機能ホーロー鍋のブランドです。老舗の鋳物メーカーである同社は、自社の職人技術を活かし無水調理を可能にする画期的な鍋を開発、ブランド化しました。ブランディングにあたっては「手料理と、生きよう。」という力強いブランドスローガンを掲げ、製品を通じて提供したい世界観を明確化しています。このスローガンには、「丁寧な料理を楽しむ豊かな暮らし」というメッセージが込められており、単なる鍋以上の価値提案となっています。
さらに同社は、顧客視点に徹したコミュニケーション戦略でも成功を収めました。専用のコールセンターを設けて顧客からの相談に応じるなど、購入後のサポート体制を充実させています。また、新製品発売前には料理の専門家や有名ブロガーに試用してもらいフィードバックを得るといった取り組みも行い、商品開発とマーケティングを一体化させています。YouTubeを含むSNSマーケティングにも積極的で、レシピ動画やユーザーストーリーを発信することでブランドファンを増やしました。
その結果、バーミキュラは高価格帯にもかかわらず「一生ものの鍋」として熱狂的な支持を得るブランドに成長しています。職人技術という強みと顧客共創型の戦略を組み合わせた好例と言えるでしょう。
事例③:星野リゾート — マルチブランド戦略で独自の宿泊体験を提供
星野リゾートは、日本を代表する総合リゾート運営企業であり、独自のブランド戦略によって高付加価値な宿泊体験を提供しています。同社は「界」「リゾナーレ」「OMO」など多数のサブブランドを展開し、それぞれ明確なコンセプトを打ち出すマルチブランド戦略を採用しています。各ブランドごとにターゲット顧客や提供価値を細かく定義しつつ、全体としては「ホスピタリティ溢れる唯一無二の体験」という星野リゾート共通のビジョンが貫かれています。
この戦略を支えるのが、ブランド品質の徹底管理と顧客視点でのサービス改善です。星野リゾートでは各施設・ブランドの認知度や顧客満足度を定期的に計測し、ユーザーの声を施設運営に反映させる仕組みを持っています。
たとえば宿泊客のアンケートやSNS上の反応を細かく分析し、サービス内容やブランドメッセージにブレがないように調整しています。こうした努力により、「星野クオリティ」と呼ばれる統一感のある高品質なブランド体験が実現されているのです。
また、同社は地域文化の発信や環境・社会貢献(SDGs)にも積極的で、そうした取り組みを記事やSNSで情報発信することでブランド価値の向上を図っています。単にホテルの設備や価格で勝負するのではなく、「その土地ならではの体験価値」をブランドの核に据えたことで、国内外の顧客から高い評価と共感を得ている事例です。
ブランド戦略の実務的な進め方
最後に、経営者や事業責任者が自社でブランド戦略を実践するためのステップを整理します。ブランド戦略は一朝一夕に完成するものではありませんが、以下のプロセスを踏むことで着実にブランド力を強化していくことができます。
STEP
ビジョン・ミッションの明確化
まずは企業の最終的な目標であるビジョン(将来どうありたいか)と、存在意義であるミッション(社会・顧客に何を提供しどんな問題を解決したいか)を定義します。ビジョン「○○を実現する未来を目指す」、ミッション「△△な価値を提供し社会に貢献する」といった形で言語化しましょう。
これを明確にすることで「ブランド戦略のゴール」が社内共有され、組織全体が同じ方向を向きやすくなりますcarryme.jp。ビジョンとミッションが定まっていれば、後の施策もぶれにくくなり、社員一人ひとりがブランドの意義を意識して行動しやすくなります。
STEP
競合・ターゲット分析(フレームワーク活用)
次に市場環境と自社の現状を分析します。ここで先述のフレームワークを活用しましょう。例えばSWOT分析で自社の強み・弱み、機会・脅威を洗い出し、ブランドの差別化ポイントを探ります。
またSTP分析で市場をセグメント分けし、狙うターゲット層と自社のポジションを定義します。分析の結果、「どんなユーザーに」「どんな世界観・価値を」提供するのかが具体化されてくるはずです。この段階で市場における自社の立ち位置(ポジショニング)と、競合との差別化戦略の骨子を掴んでおくことで、次のブランドアイデンティティ策定がスムーズになります。
STEP
ブランドアイデンティティの確立
分析から得た自社の強み・顧客インサイトと、ステップ1で定めたビジョン・ミッションを掛け合わせて、自社ブランドのアイデンティティを構築します。
ブランドアイデンティティとは、ブランドの核となる世界観・価値観・メッセージのことです。例えば、「私たちのブランドは○○のために存在し、△△という価値を提供する」という軸を定め、それを体現するブランドコンセプトやスローガン、ストーリーを作り込みます。必要に応じて「ブランドピラミッド」などの手法を使い、表面的なキャッチコピーから根底にある理念までを一貫させることがポイントです。
ここで大事なのは「なぜ私たちはこの商品・サービスを世の中に届けるのか?」という問いに明確に答えを出すことです。その答えがクリアであればあるほど、社内外でブランドに対する共通認識が醸成され、以降の戦略展開でも芯がブレなくなります。
STEP
コミュニケーション戦略の実行
確立したブランドアイデンティティを実際に社外へ発信していくフェーズです。マーケティングコミュニケーション全般の戦略を立て、一貫したブランドメッセージを多面的に届けます。
具体的には、WebサイトやSNS、テレビCM、紙媒体広告、PRイベントなどあらゆるチャネルでブランドのデザイン指針と言葉遣いを統一し、どの接点においても同じ世界観を感じてもらえるようにします。例えばSNSではターゲットとフランクに対話しつつ、プレスリリースでは企業の理念をしっかり伝える、といったように各チャネルの特性に合わせ表現方法を調整しながらも核となるメッセージは統一することが重要です。
複数のチャネルを使う場合でも、「どの媒体でもこのブランドは一貫した人格・価値観を持っている」と認識してもらえるように工夫しましょう。これにより顧客の心の中に確固たるブランドイメージを築くことができます。
STEP
モニタリングと改善(PDCA)
ブランド戦略は立てて終わりではなく、継続的な改善サイクルが不可欠です。実施したブランディング施策が狙い通り機能しているか、定量・定性の両面でモニタリングしましょう。具体的には、WebやSNSのアクセス解析・エンゲージメント指標、顧客アンケートによるイメージ調査、営業現場での声などを収集し、ブランドの浸透度や認知イメージの変化を把握します。そこで得られたデータから「どのメッセージが響いたか」「どのチャネルが効果的だったか」を分析し、必要に応じて戦略や施策を調整します。
このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回し続けることで、市場環境や顧客の嗜好変化に合わせてブランドを進化させ、常に最適な形で価値提供できるようになります。
例えば新たな競合が出現したらポジショニングを見直す、トレンド変化に合わせメッセージをアップデートする、といった微調整を重ねてブランド力を維持・向上させましょう。
以上がブランド戦略を進める基本ステップです。規模の大小を問わず、企業が軸となるビジョンを掲げ、それに沿った価値提供を続けていけば、時間はかかっても確実に市場での存在感は高まっていきます。
ブランド戦略は長期にわたる投資ですが、明確な方針と粘り強い実行により、やがて大きな無形資産として企業にもたらされるでしょう。経営者・事業責任者として、自社のブランドを戦略的に育て上げ、競争優位と顧客から愛される状態をぜひ実現してください。
参考文献