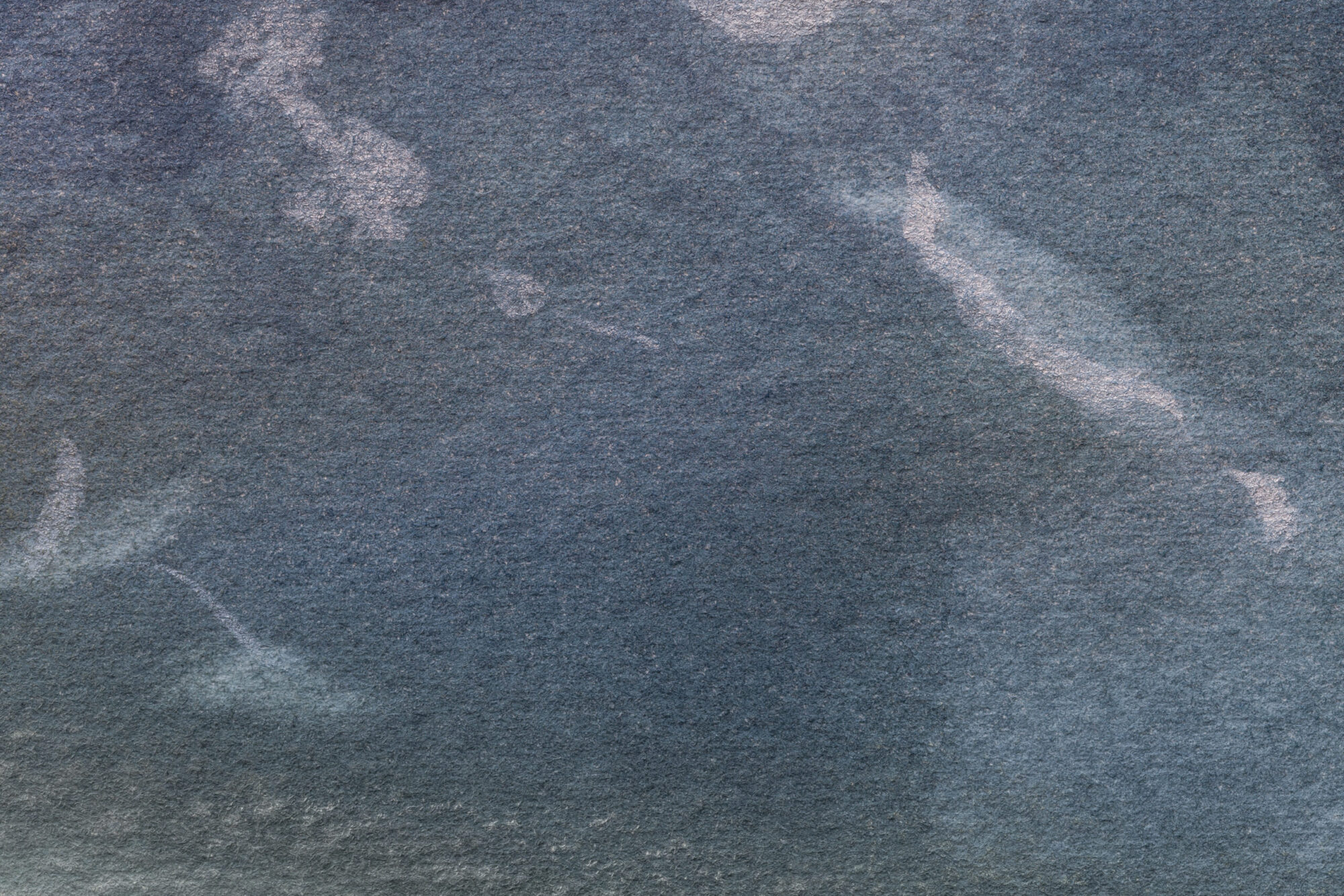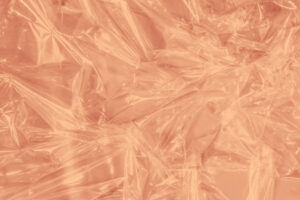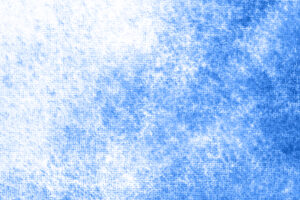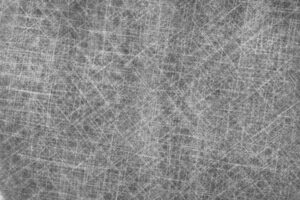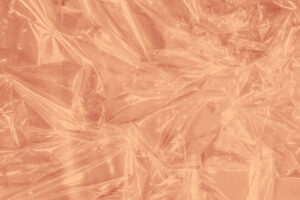目次
1. ブランドが迷走する主な要因
ブランディング戦略は常に成功するとは限らず、企業の試みが顧客に響かない場合にはブランドが迷走してしまいます。ここでは、ブランドが失敗に陥る主なパターンを専門的な視点から整理します。
ポジショニングのミス(市場での位置づけの誤り)
自社のブランドを市場でどのように位置づけるかを誤ると、顧客に訴求できないだけでなく競合との差別化にも失敗します。例えば、高級ブランドが安価な製品ラインを展開した結果、ブランド価値が低下してしまったケースがあります。
適切なポジショニングを欠くとブランドは「唯一無二の価値」を示せず、マーケット内での存在感を失いかねません。
ブランドメッセージの不一致(コアメッセージと実態の乖離)
ブランドが約束するイメージと提供する製品・サービスが食い違うと、顧客の信頼を損ねます。言い換えれば、ブランドが顧客にもたれているイメージを裏切ってしまう状況です。あるカジュアル衣料ブランドは「高品質・低価格」というブランドイメージで成功していましたが、全く異なる分野の商品を展開した際にそのメッセージとの乖離が顕著となり、消費者を困惑させました。
ブランドが発信するストーリーと実際の顧客体験に齟齬があると、ブランド自体の信憑性が揺らいでしまいます。
ターゲットの誤認(狙うべき顧客層のズレ)
本来狙うべき顧客層を取り違えると、どれほど良い商品でも支持を得られません。顧客が求めているものやニーズを見誤ることで、ブランドの訴求ポイントがずれてしまいます。典型例として、衣料品チェーンがその顧客層とは無関係な新規事業(例えば食品分野など)に乗り出した結果、顧客の関心を引けず大きな損失を出したケースがあります。
ターゲット設定を誤ることは、ブランドのSTP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)の根幹を揺るがし、戦略全体の失敗につながります。
拡張戦略の失敗(ブランド拡張時の誤算)
確立したブランド名に頼って新分野へ拡張する戦略は魅力的ですが、ブランドの核と関連性の薄い領域への拡大は危険を伴います。ある食品メーカーでは「総合食品メーカー」を目指して事業領域を次々と広げましたが、大量の在庫を抱えて安売りを強いられる事態に陥り、結果としてブランドイメージが大きく低下しました。
このように無計画なブランド拡張は、元のブランドにも悪影響を及ぼし、築き上げたブランド価値を損なう可能性があります。
競争環境の見誤り(競合との違いを作れなかったケース)
市場における競争状況を正しく把握できないと、自社ブランドの優位性を打ち出せずに埋没してしまいます。競合他社の動きを的確に捉えずに戦略を進めると、差別化要素のないまま価格競争に巻き込まれたり、逆に的外れな方向に舵を切ってしまうことがあります。
例えば、ある飲料メーカーはライバル製品に対抗するあまり従来の人気商品の方向性を変えてしまい、顧客が本当に望んでいたものを見失った結果、クレームが殺到し販売戦略を撤回する事態となりました。競争環境を見誤ることは、自社の強みを活かせない戦略ミスであり、市場からの後退を招きます。
-
-
2. 日本国内の具体的なブランド失敗事例
以下に、日本国内で実際に起きたブランド戦略の失敗事例を紹介します(企業名は伏せています)。それぞれの事例が上述のどのパターンに該当するかを分析します。
- 老舗食品メーカーの事例
-
100年以上の歴史をもつ食品メーカーが、自社ブランドの下で取り扱う製品カテゴリーを大きく拡大しました。本業以外の新商品にも次々と手を広げた結果、供給過多に陥って在庫を抱え込み、売上確保のため値下げ販売を余儀なくされ、この戦略ミスにより長年培ってきたブランドの格が下がり、消費者のブランドに対する印象も悪化してしまいました。
これはブランド拡張の失敗にあたり、コア事業とのシナジーを欠いた拡大戦略がブランド価値の希薄化を招いた例です。
- 家具販売チェーンの事例
-
高級路線で顧客の信頼を得ていた家具小売チェーンが、内部の経営方針対立を機に戦略を大きく変更しました。従来は丁寧な接客と会員制による差別化を図っていたにもかかわらず、路線変更後は頻繁なセールと価格改定で集客を図ろうとしたため、これまでの顧客層からの信頼が著しく低下しました。家族経営の内紛によるイメージ悪化も相まってブランドは迷走し、結局、市場でのポジションを失う結果となりました。
このケースはポジショニングのミス(及び競争戦略の誤り)に分類でき、競合他社(低価格家具量販店)に対抗しようと自社の持ち味を見失ったことが原因といえます。
- 衣料品企業の事例
-
国内大手の衣料品チェーンが、本業とは異なる食品分野(野菜の宅配販売)に進出した事例です。同社は当初、培ってきた物流ノウハウ等を活かして新規事業に乗り出しましたが、肝心の売上は低迷し、開始からわずか2年で数十億円規模の赤字を計上して撤退を余儀なくされました。
この失敗の背景には、ターゲットの誤認とブランドメッセージの不一致がありました。同社は「高品質・低価格のカジュアル衣料」という強いブランドイメージで成長してきましたが、新事業では「高品質・少し高い価格帯」という従来とは異なるポジショニングの商品を提供してしまいました。
その結果、顧客はブランドに何を期待すべきか分からなくなり、既存ブランドの価値も毀損されてしまったのです。
- 電機メーカーの事例
-
大手電機メーカーが自社内に立ち上げた超高級AV機器のサブブランドの例です。技術力を結集した特別仕様の商品群で「究極の高級ブランド」を標榜しましたが、価格帯やコンセプトが一般顧客とかけ離れていたため市場での支持を得られませんでした。製品設計において開発陣の思い入れが強すぎた結果、消費者視点での価値提案が不十分となり、コンセプトも統一されないままブランド構築に失敗しています。
これはターゲットニーズの読み違えに起因する失敗で、顧客が本当に求めている価値や体験を十分に掴めなかったことが大きな要因と評価できます。
- コンビニチェーンの事例
-
全国に店舗展開するコンビニエンスストアが、自社プライベートブランド商品のパッケージデザインを刷新したケースです。従来の慣れ親しんだデザインを捨て、ベージュ基調にイラストを配した統一パッケージへと変更したところ、「おしゃれで可愛い」との好意的な声がある一方で「商品が見分けにくい」「美味しそうに見えない」など否定的な反応も多く、生産現場にも混乱が生じました。
結局、翌年にはデザインを大幅に調整する事態となりました。この事例はブランドメッセージの不一致の典型で、デザイン性を重視するあまり肝心の消費者ニーズ(必要な商品をすぐ見つけたい、美味しそうな商品を探したいという要望)を汲み取れていなかったことが原因です。
ブランドのビジュアル表現が実際の購買体験と乖離したことで、一時的にブランドが迷走した例と言えます。
3. ブランドが迷走しないための対策
上述の失敗パターンを踏まえ、ブランド戦略で迷走を避けるために経営者が講じるべき対策を解説します。
明確なポジショニングの確立
市場環境と自社の強みを徹底的に分析し、自社ブランドの立ち位置を論理的に定義することが重要です。フレームワークに基づく環境分析で「どの顧客に、何の価値を提供するのか」を明文化し、一度決めたブランドの軸はぶれないよう組織全体で共有します。自社が狙うポジションに確信を持ち、継続的にその価値を磨き上げる姿勢が求められます。
ブランドストーリーの一貫性を保つ
ブランドの約束する世界観や価値観と、提供する商品・サービスとの整合性を常に維持するよう努めます。顧客がブランドに期待するイメージを裏切らないことは、長期的な信頼関係の構築に直結します。
具体的には、マーケティングメッセージから現場でのサービス提供に至るまで、ブランドの核となるストーリーが一貫して反映されているかを定期的に点検します。
ターゲット市場の再検証
時代の変化や顧客ニーズの多様化に応じて、自社の想定するターゲットが適切かを継続的に見直します。ブランド戦略開始時に設定したペルソナや市場セグメントが時間とともにズレていないか、データに基づき検証するプロセスが必要です。
市場環境や顧客の価値観が変化した場合には、それに合わせてブランドの訴求ポイントや提供価値も柔軟に調整します。
成功するブランド拡張のポイント
新たな商品カテゴリーへ進出する際は、自社ブランドの核となる強みや価値から大きく逸脱しない戦略を立案します。ブランドと新商品との間にシナジーが見込めるかを慎重に見極め、拡張によってブランド自体も強化されるような相乗効果を狙うことが望ましいかと思われます
。市場調査を徹底し、消費者視点で新商品がブランドの世界観に違和感なく溶け込むか検証することで、拡張による失敗リスクを低減できます。
競争優位性を確保する戦略
競合他社に埋没しないためには、自社ブランドならではの差別化要因を明確に打ち出し、それを継続的に強化する戦略が不可欠です。他社が容易に模倣できない独自の価値提供や顧客体験を設計し、自社ブランドの優位性として訴求します。
ポジショニングの段階から競合との差異化ポイントを織り込むことで、たとえ競合と比較されても自ブランドが優位性を発揮できる状態を作り出せます。また、競合動向や市場トレンドを定期的にモニタリングし、必要に応じてブランド戦略をアップデートする機動力も持つべきです。
4. まとめ:ブランドを成功に導くための視点
最後に、経営者が意識すべきブランディングの本質と、長期的にブランド価値を維持するための施策をまとめます。ブランディングの本質は、顧客との信頼関係にもとづき一貫した価値を提供し続けることです。ロゴやスローガンといった表面的な要素だけでなく、企業活動の隅々に至るまでブランドの約束が体現されている状態を作ることが重要です。
加えて、ブランドは一度築けば安泰というものではなく、環境変化に応じた不断の見直しと育成が求められます。市場の変化や競争状況、顧客ニーズを継続的に分析し、戦略を改善・適応させていく姿勢が、ブランド価値を長期にわたり維持・向上させる鍵となります。
経営者は短期的な成果に一喜一憂することなく、ブランドを長期的な企業資産として捉え、腰を据えて育てていく視点を持つことが肝要です。
参考文献・事例