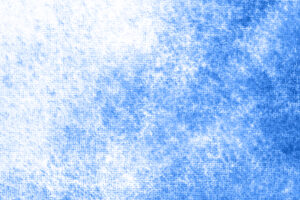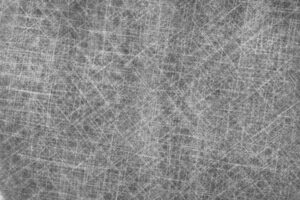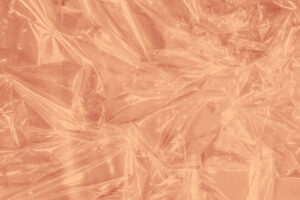目次
はじめに
ビジネス環境が激しく競争する現在、市場で生き残るためにはブランドの力が欠かせません。単に優れた商品やサービスを提供するだけでは不十分で、強いブランドを構築することが重要だと指摘されています。
ブランドは企業名やロゴといった表面的なものだけではなく、企業の価値観や信念を体現し、消費者にとってそのブランドがどんな「意味」を持つのかを明確にすることで競合との差別化を図り、顧客に選ばれる存在となることが求められます。
本記事では、*選ばれるブランド」が持つ共通点と、「選ばれないブランド」に陥りがちな典型例について解説します。さらに、国内の具体的なブランド事例を成功・失敗の両面から紹介し、最後に学んだポイントを実務へどう応用できるかをまとめます。
選ばれるブランドの共通点
「選ばれるブランド」にはいくつかの共通する特徴があります。ブランド戦略がうまくいっている企業は、自社のアイデンティティやメッセージを明確に打ち出し、一貫して顧客に届けています。また、商品やサービスそのものだけでなく、顧客が得る体験やブランドを取り巻くコミュニティ作りにも力を入れており、市場の変化にも柔軟に対応しています。以下に、その主要なポイントを詳しく見ていきましょう。
ブランドアイデンティティの明確化
まず、成功するブランドは自社のブランドアイデンティティ(何を提供し、どのような価値観を持ち、どんな立ち位置なのか)を明確に定義しています。ブランドの存在意義や使命がはっきりしていることで、消費者はそのブランドを理解しやすくなり、強い共感を抱きやすくなります。実際、AppleやNikeといったトップ企業は自社のアイデンティティを強烈に打ち出し、一貫したブランドイメージを築くことで消費者の心に深く根付いています。
自社の強みや世界観を一言で表せるほどに鮮明なアイデンティティを確立しておくことが、選ばれるブランドの土台となります。
一貫性のあるメッセージとデザイン
ブランドメッセージやデザインの一貫性も、選ばれるブランドに共通する重要な要素です。どの媒体やチャネルで発信するときもぶれないメッセージと統一感のあるビジュアルを保つことで、消費者の信頼を得てファンを増やすことができます。
例えばAppleは、製品の設計からマーケティングまで一貫したメッセージ(「革新」と「洗練されたデザイン」)を発信し続けることで、消費者との深い絆を築き上げています。
このように全てのコミュニケーションでブランドの核となる価値やビジョンを統一して伝えることで、顧客はブランドに対して安心感を持ち、「このブランドなら期待を裏切らない」という信頼感を形成します。一貫性は強いブランド構築に不可欠であり、逆に言えば一貫した発信があって初めてブランドのメッセージが消費者に浸透していくのです。
顧客体験の最適化
商品やサービスそのものだけでなく、顧客がブランドと接触する際の体験(カスタマーエクスペリエンス:CX)を最適化することも、選ばれるブランドの重要な共通点です。店舗での接客や雰囲気、ウェブサイトやアプリの使い勝手、購入後のサポートに至るまで、あらゆる接点でポジティブな体験を提供できるブランドは顧客ロイヤルティを高めます。事実、ブランドエクスペリエンス(顧客がブランドから得る体験)こそが顧客がそのブランドを選ぶ理由になるとも言われます。
AppleやNikeなどはデザインや世界観を通じて顧客に特別な体験を提供し、高いブランドロイヤルティを築いています。心地よい店舗内環境、分かりやすいUI、迅速で丁寧なカスタマーサービスなど、顧客視点に立った体験設計を徹底することで、「またこのブランドで買いたい」「このブランドと関わり続けたい」と感じるファンを増やすことができるのです。
市場ニーズとトレンドの適応力
市場環境や消費者ニーズの変化に柔軟に適応できるかも、ブランドの盛衰を分ける大きなポイントです。選ばれるブランドは固定観念にとらわれず、新しい技術やトレンド、ライフスタイルの変化に合わせて自らを進化させます。典型的な例として、写真フィルム市場で一時代を築いたKodak(コダック)と富士フイルムの対照的な運命がよく引き合いに出されます。デジタル技術への変化に対応しきれなかったコダックが破綻に追い込まれた一方で、富士フイルムは自社の技術を化粧品や医療など新分野へ活用するなど俊敏に対応し、成長を遂げました。
このように時代の潮流を読み取り戦略を見直す柔軟性があるブランドは、市場から継続的に支持されます。流行のデザインや新しいコミュニケーション手段(例えばSNSや動画プラットフォーム)を積極的に取り入れること、あるいは消費者のライフスタイル変化に合わせて商品ラインナップやサービス提供方法をアップデートしていくことが、ブランドを時代遅れにさせず常に選択肢の中に居続ける秘訣です。
コミュニティ形成とエンゲージメント戦略
強いブランドは単に商品を売るだけでなく、顧客とのコミュニティ形成にも注力しています。ブランドを愛する顧客同士が交流できる場や、ブランドとファンとの双方向のコミュニケーションを促す仕組みを作ることで、顧客はブランドに対して愛着と帰属意識を持つようになります。ブランド・コミュニティは企業と顧客、あるいは顧客同士をつなげ、ロイヤルティを育むために不可欠なものだと言われます。
コミュニティがうまく機能すればブランドへの愛着が強化されるだけでなく、売上や利益の向上、さらに顧客との共創による商品アイデアの創出といったメリットも生まれます。
具体例として、Appleはユーザーフォーラムやイベントで熱狂的なファン同士が情報交換できる場を提供し、LEGOはユーザーがオリジナル作品を投稿・共有できるコミュニティを運営しています。こうしたエンゲージメント戦略によって生まれたファンはブランドの強力な支持者・伝道者となり、新規顧客を呼び込む力ともなるのです。
選ばれないブランドの典型例
一方で、ブランド戦略に失敗し「選ばれないブランド」となってしまうケースには、いくつかありがちなパターンが見られます。ここでは、ブランドが顧客から見放されてしまう典型的な原因を挙げてみます。自社のブランドがこれらに当てはまっていないか、反面教師としてチェックしてみてください。
不明確なポジショニング
まず致命的なのは、ブランドのポジショニング(存在意義や役割)が不明確なケースです。自社ブランドが「世の中でどんな価値を提供するのか」「顧客にとってどんな存在なのか」がはっきり定まっていないと、発信するメッセージにも芯がなくなり、消費者にブランドの印象を残すことができません。ブランディングがうまくいかない原因の第一に「自分たちの存在意義の欠如」が挙げられるほどで、何を目指すブランドなのか分からないようでは顧客に選ばれることは難しいと考えられます。
例えば、新興ブランドがあれもこれもと機能やコンセプトを盛り込みすぎた結果、結局「何のブランドなのか分からない」という状態に陥ることがありますが、それでは消費者の心に残らず埋もれてしまいます。逆に、ブランド目的を短い言葉で言い表せるくらいまで研ぎ澄ませることができれば、顧客の記憶にも刻まれやすく、支持も得やすくなります。
一貫性の欠如(メッセージ・デザイン・体験)
次に、ブランドの一貫性が欠如していると、顧客からの信頼を失いやすくなります。前述のように一貫性はブランド成功の鍵ですが、その反対にコロコロとメッセージが変わったりデザインが統一されていなかったりすると、消費者は混乱し「このブランドは何を大事にしているのだろう?」と不信感を抱きかねません。例えば、ある年は高級路線の広告を出していたのに翌年には急にポップで安価な印象のキャンペーンを打ち出したとしたら、顧客はその急激な変化についていけず戸惑ってしまうはずです。
ロゴデザインの頻繁な変更や、接客態度・サービス品質のばらつきも一貫性の欠如の表れです。こうしたブレはブランドイメージの希薄化につながり、「信頼できないブランド」「芯のないブランド」と見なされて選択肢から外されてしまいます。実際、長年親しまれたロゴマークを拙速に変更して失敗したGap(ギャップ)の事例では、戦略的な計画もなくデザインを変えた結果、顧客の強い反発を招いてわずか1週間で旧ロゴに戻す羽目になりました。
このケースは、一貫性を軽視したブランド変更の危険性を物語っています。
顧客の期待とのズレ
ブランドが顧客から見放される原因としてしばしば指摘されるのが、顧客の期待を裏切ってしまうことです。長年培ったブランドイメージや約束してきた価値に反するような商品展開やメッセージを打ち出すと、コアなファンほど強く失望し、場合によっては炎上や不買運動につながることもあります。ブランド失敗の事例を見ると、常に根底に「顧客への裏切り」があると言われます。
例えば、高級ブランドのGucciがかつて手頃な価格帯の商品ラインを広げた際には、一時的に売れたものの「Gucci=高級」という従来の顧客の期待を裏切ったためにブランド価値を大きく毀損してしまいました。
また、コカ・コーラが1980年代に味を変更した「ニューコーク」は、消費者が愛着を持っていた従来の味を捨てたことで猛反発を受けた典型例です(結局旧来の味がすぐに復活しました)。このように、ブランドに対して顧客が抱く期待や前提を大きく外れる試みはリスクが高く、慎重な検討が必要です。もしブランドの方向転換やリニューアルを行う際は、現在の顧客が何をそのブランドに求めているのかを十分に把握し、それをないがしろにしない形で進めなければ、かえって支持を失う結果になりかねません。
競合との差別化不足
市場で埋もれてしまうブランドの典型は、競合他社との差別化ができていないブランドです。明確な独自性や強みが打ち出せていないと、消費者から見てそのブランドを選ぶ理由がありません。差別化されていないブランドは、最終的に価格でしか勝負できなくなってしまい、激しい価格競争に巻き込まれて収益性も低下します。
実際、ブランドイメージが確立されていない場合、消費者は製品やサービスを選ぶ際に価格を優先し、少しでも安い競合に流れてしまう傾向があります。
これはつまり、「このブランドでなければダメだ」と思われていない状態であり、極端に言えば他社でも代替可能な存在と見なされているということです。例えば、多くの後発スマートフォンメーカーが似たようなデザイン・機能の商品を出して価格で競い合った結果、「結局どこの製品でも大差ない」という印象を与えてしまっているようなケースがあります。こうなると顧客はブランドではなく値段だけで選択するため、ブランドロイヤルティは育ちません。「価格以外の比較軸」で自社を選んでもらえるような差別化ポイントを持たないブランドは、長期的には厳しい戦いを強いられると考えられます。
長期的な戦略の欠如
最後に、長期的なブランド戦略が欠如している場合も、ブランドは失敗に陥りやすいです。場当たり的にその場しのぎのマーケティング施策ばかり行っていると、ブランドの軸が定まらず一貫性も失われ、結果として顧客からの信頼を得られません。短期的な売上アップに囚われすぎて頻繁にブランドの方向性を変えてしまったり、流行に飛びついてはすぐ捨てるような姿勢は、消費者に不安定な印象を与えます。
また、社内的にもブランドのビジョンが共有されず、社員一人ひとりがバラバラのメッセージを発信してしまう原因にもなります。前述のGapのロゴ変更の失敗例は、顧客の声を無視して戦略なきリブランディングを強行したことが原因でした。
このように筋の通った長期ビジョンや計画なくブランドを動かすことの危うさは、多くの失敗事例が物語っています。逆に言えば、成功するブランドは5年後、10年後を見据えたブランド像を描きつつ、それに沿って一貫した投資や施策を積み重ねています。長期戦略なくして強いブランドは築けないと言えるでしょう。
具体的な国内事例
ここで、上記のポイントを体現している国内ブランドのケーススタディを紹介します。ひとつは成功したブランドの例、もうひとつは一度低迷しながらリブランディングによって復活に成功した例です。実際の事例から、理論だけでは見えにくいブランド戦略の重要性を感じ取ってみましょう。
成功事例:無印良品(MUJI)
日本発のライフスタイルブランドである無印良品は、ブランド戦略の成功例として世界的にも知られています。無印良品の最大の強みは、明確なブランド哲学を打ち立て、それを徹底して貫いていることです。
同社は「これでいい」という独自の哲学のもと、シンプルで本質的な価値を提供することをブランドの軸としています。商品開発から店舗デザイン、マーケティングに至るまでこの哲学を一貫して反映させており、消費者に「無印らしさ」が伝わる強固なブランドイメージを築いています。
例えば、無印良品のどの商品を手に取っても共通して感じられるシンプルで飾らないデザインは、全ての製品が同じ価値観にもとづいて設計されているためであり、それがブランド全体の統一感につながっています。
また、無印良品は顧客体験にも非常に気を配っており、実店舗では内装や陳列、接客に至るまでブランド哲学を体現する工夫を凝らしています。店に入るだけで無印良品の世界観に浸れるような体験を提供し、来店そのものがブランド体験になるよう設計されています。
さらに、無印良品は日本国内に留まらず海外展開にも成功していますが、その背景には各国の文化やニーズに合わせて商品ラインナップを調整する柔軟な市場適応戦略があります。
例えば現地の生活様式に合わせた商品の投入や、ECサイトと店舗を連携させたOMO施策など、グローバル市場でも受け入れられる工夫を行っています。
これらの取り組みにより、無印良品は「明確なアイデンティティ」「一貫したメッセージとデザイン」「優れた顧客体験」「市場適応力」のすべてを高次元で実現し、国内外で高い支持を得るブランドとなりました。
失敗事例:湖池屋のリブランディングによる復活
次に、湖池屋(コイケヤ)の事例を見てみましょう。湖池屋は1962年創業の老舗スナック菓子メーカーで、「カラムーチョ」に代表されるポテトチップスで有名なブランドです。長らく日本の菓子市場を支えてきた湖池屋ですが、時代が下るにつれて市場のコモディティ化や価格競争の波にさらされ、かつての輝きが薄れつつありました。そこで湖池屋は2016年に大胆なリブランディングを実施し、ブランドイメージの刷新に踏み切ります。
湖池屋が着目したのは、自社の強みである「日本初のポテトチップス量産メーカー」という伝統と格でした。リブランディングではロゴデザインを一新し、親しみやすいカタカナ表記から歴史を感じさせる漢字のロゴへ変更。パッケージも白黒を基調としたシックでシンプルなデザインに統一し、老舗メーカーならではの重厚感や高級感を演出しました。
この新しいビジュアル戦略によって、湖池屋はそれまでの「安価なお菓子」というイメージから脱却し、プレミアム感のあるポテトチップスというポジションを確立することに成功します。
実際、リブランディング後に発売した「KOIKEYA PRIDE POTATO」シリーズは高価格帯ながらヒット商品となり、消費者に「湖池屋=高品質でこだわりのあるブランド」という印象を定着させました。結果として湖池屋は価格競争に巻き込まれがちなスナック市場において差別化に成功し、ブランド復活を遂げています。
湖池屋のケーススタディから学べるのは、たとえブランドが成熟市場で埋もれかけていても、自社の核となる価値を見つめ直し、それを軸に据えてブランドを再構築することで再び選ばれる存在になり得るということです。言い換えれば、ブランドの失速要因であった「ポジショニングの曖昧さ」や「競合との差別化不足」を、リブランディングによって解消した好例と言えるでしょう。湖池屋は伝統にモダンさを掛け合わせることでブランドアイデンティティを明確化し、一貫した高級路線のデザインとメッセージで顧客の印象を刷新しました。
その結果、古くからのファンのみならず若年層など新たな顧客層も取り込むことに成功し、売上も伸びています。この事例は、ブランド戦略の立て直しによって「選ばれないブランド」から「選ばれるブランド」へと転じた典型と言えます。
まとめと実務への応用
最後に、「選ばれるブランド」と「選ばれないブランド」の違いを踏まえて、実務で活かせるポイントを整理します。選ばれるブランドは一貫して明確な価値提案を行い、あらゆる接点でその価値を体現し続けています。具体的には、ブランドの存在意義を明確化し、それに沿ったメッセージやデザインをブレずに発信することで顧客との信頼関係を築き、優れた顧客体験やコミュニティ作りを通じて長期的なロイヤルティを獲得しています。一方、選ばれないブランドは方向性の曖昧さや発信のブレによって顧客からの理解・信頼を得られず、競合に埋もれてしまったり一度きりの購入で終わってしまったりしがちです。
実務への応用ポイントとして、まず自社ブランドの核となるコンセプトや使命をチーム内で共有し、それを軸にプロダクト開発やマーケティング施策をデザインしてください。全てのチャネル(広告、SNS、店舗、顧客対応など)でブランドのトーン&マナーが統一されているか見直し、もし一貫性を欠いている要素があれば早急に整合性を持たせるべきかと思います。
また、定期的に顧客視点に立ってブランド体験を点検し、改善すべき点(例えば購入フローの煩雑さやアフターサポートの質など)があれば迅速に対応することが重要です。加えて、市場環境の変化や顧客の声に耳を傾け、必要に応じてブランド戦略の微調整やリブランディングも検討しましょう。ただしその際は、既存顧客の期待をないがしろにしないよう注意深く計画し、短期的な流行に飛びつくのではなく長期的なブランド価値向上につながるかを判断基準にすると良いでしょう。
ブランドは一朝一夕に築かれるものではありませんが、だからこそ戦略的かつ一貫した取り組みが成果につながります。自社のブランドが持つ強みを磨き上げ、顧客との絆を育むことで、競争の激しい市場においても「あなたのブランドだから選ぶ」と言ってもらえる存在になれるはずです。今回紹介したポイントや事例を参考に、自社ブランドの現状を見直し、長期的に愛され選ばれるブランド作りに役立ててください。
参考文献・事例:
- ブランディングの成功事例10選|成功のポイント・注意点も解説(株式会社イマジナ)【URL】https://www.imajina.com/brand/entry/4290
- 〖成功事例から学ぶブランディングとは〗ブランド構築する目的・意味や方法をわかりやすく説明します(100years-BRAND_lab)【URL】https://gift-to.co.jp/media/branding_case_study_success_story/
- ブランドエクスペリエンスの重要性と成功事例(株式会社チビコ)【URL】https://chibico.co.jp/blog/brand-strategy/brandexperience-061/
- 〖必読〗上手に運営されているブランドコミュニティの10の事例(Sankaブログ)【URL】https://sanka.io/ja/blog/brand-community-examples/
- 失敗事例から学ぶブランディングの要注意ポイント(btraxブログ)【URL】https://blog.btrax.com/jp/branding-fails/
- 失敗事例から学ぶブランディング。ブランディングの失敗が指すものとは?(BRAND THINKING)【URL】https://www.brandthinking.net/what/5496
- 成功事例・失敗事例から見るブランド戦略の効果(Innovaブログ)【URL】https://innova-jp.com/media/branding-strategy
- 戦略のないブランディングはなぜ失敗するのか?(Bulanco/Swings)【URL】https://bulan.co/swings/failed-branding-strategy
- 無印良品のブランド戦略を徹底分析|シンプルさの戦略と未来展望(マーケティング戦略部)【URL】https://yushutsulabo.com/muji-brand-strategy/
- リブランディングの事例13選!食品・アパレル等多数紹介(株式会社ライデン)【URL】https://www.ryden.co.jp/blog/691/